コミュニケーション「術」は必要か? 学生に必要な力を考える
この日、初対面となった上出さんと高野教授。二人の共通点は、冒険の力に魅了され、身一つで世界各地を旅してきた経験です。危険地帯や犯罪組織、過酷な自然環境であっても果敢に赴き、対話を通じて活動を広げてきました。上出さんは現在、ニューヨークを拠点にフリーランスのプロデューサーとして活動中。テレビ東京時代に手掛けた『ハイパーハードボイルドグルメリポート』では、リベリアの元少年兵、台湾のマフィア、ロシアのカルト教団など、バックグラウンドや価値観が異なる人々の食卓をカメラ片手に単身で取材してきました。

上出 遼平(かみで・りょうへい)
1989年東京都生まれ。2011年早稲田大学法学部卒業後、株式会社テレビ東京に入社。ドキュメンタリー番組『ハイパーハードボイルドグルメリポート』シリーズの企画から撮影、編集まで全工程を担う。同番組にて第57回ギャラクシー賞受賞。2022年にテレビ東京を退社し、米国・ニューヨークへ移住。著書に『ハイパーハードボイルドグルメリポート』(朝日新聞出版)、小説『歩山録』(講談社)、『ありえない仕事術 正しい“正義”の使い方』(徳間書店)など。
一方、早稲田大学を卒業後、バックパック一つで中国からヨーロッパまでを巡ったり、犬ぞりやスキーで北極海を横断したり、アマゾン川をカヌーで下ったりと、零下50度からプラス60度に至る地球上の各地で、冒険家として活動してきた高野教授。数々の遠征の経験を踏まえ、現在はサステナビリティーを目指す教育・研究活動にも従事しています。
高野好奇心が強く、「やらずに後悔するよりは、やって後悔した方がいい」という性格。次から次へと関心事が生まれ、いつの間にか世界を旅していました。自分の“当たり前”を壊してくれるような、大自然や少数民族と暮らした経験が、他の人の役に立つかもしれない。そうした気持ちで学びの場をつくっています。ただ、“教育”という言葉は好きではなくて、学生との付き合いの中で学び合い、私自身が成長している感覚なんです。
上出今回の依頼を受けたときに、ガチの冒険家が早稲田で教授をされていることに驚きました。対談が実現できて光栄です。
高野自分もかつてそうだったのですが、敷かれたレールを外れてみるのは、学生にとって勇気が必要なこと。ハードボイルドな生き方を地で行く上出さんが、世界中の人々とどうやってコミュニケーションを取っているのか、現役生の指針になるようなお話が飛び出るのが楽しみです。

高野 孝子(たかの・たかこ)
1963年新潟県生まれ。1986年早稲田大学第一文学部卒業、1989年同大学院政治学研究科修了、2000年ケンブリッジ大学修士課程修了。2005年エジンバラ大学博士課程修了。博士(School of Education)。特定非営利活動法人ECOPLUS代表理事。早稲田大学留学センター教授などを経て、現在文化構想学部教授。著書に『地球(ガイア)の笑顔に魅せられて』(海象社)など。
独り善がりな物差しを捨て去り、相手を尊重するのが、コミュニケーションの第一歩
“コミュ力”という言葉がもてはやされ、書店にはコミュニケーション関連の実用書が並び、企業は人材にコミュニケーションスキルを求めたがる…。一方で、相手の顔色をうかがったり、他人に気を使い過ぎたりと、誰もがコミュニケーションが得意なわけではありません。バックグラウンドの異なる人に対し、自分の意見をうまく伝えるには、どのような心構えが必要なのでしょうか。
上出まず、コミュニケーション術の本を読んでるやつはダメですね(笑)、他にやるべきことがあるはずです。でも、コミュニケーション能力の高低って、不明瞭な部分が大きいですよね。相手の顔色をうかがってしまいがちな人に、少なくとも言えるのは、「承認されるのを諦めろ」ということです。相手に対し何かを期待するから、コミュニケーションがうまくいかなくなる。「自分はこう見られたい」という自我が邪魔するためでしょう。そうではなくて、「おまえなんて、マジでどうでもいい」という視点で自分を見つめ、自分を取り繕おうとせず、本音で相手と接する。すると相手が心を開いてくれるのだと思います。高野先生は、何か心掛けていることはありますか?
高野コミュニケーションは本来、相互理解が目的であるはずですが、なぜかこのような話題になると、手段が重視され、言葉や動作、表情を思い浮かべがちです。でも、そうしたものに頼る必要はありません。私が心掛けているのは、一緒に何かをすることです。お茶を飲んで談笑するのではなく、身体を使って共同作業をする。歩くとか、物を運ぶとか、シンプルなことでいいんです。すると言葉じゃない本質的な部分で、相手のアイデンティティを理解できます。大学時代、オーストラリアの人里から離れた場所で、複数の国籍の人と3カ月間暮らすプログラムに参加したことがありました。シェルターを造ったり、水の在りかを探したりと、共同生活を送っているうちに絆が深まるんですね。例えばみんなで木材を運んでいて、誰かが落としてしまったとき、他の人の対応を見て、「ああ、こいつ結構いいやつだな」と分かるといった具合です(笑)
上出言葉だけのコミュニケーションは、相手を理解する上ではあまり効果的ではないのかもしれませんね。
高野今の学生のコミュニケーションについて、少し俯瞰(ふかん)して見ると、コロナパンデミックの影響は大きいのかもしれません。コミュニケーションうんぬん以前の問題として、人と関わる機会が減ってしまっている。すると成長する機会も失われ、ますます対人関係が億劫(おっくう)になってしまう。こうした流れの中で、コミュニケーションの形もゼロから見直されているのでしょう。

高野上出さんは、未知の世界に行っても、「飯を見せてもらう」という自分の遂げたいミッションを達成してきます。それって、簡単なことじゃありませんよね? 相手の懐に入る上で、コツはありますか?
上出他者へのリスペクトです。そのためには、まず危険の中に身を投じることです。良好なコミュニケーションって、「自分の命がいかに脆弱(ぜいじゃく)か」という無力感により生まれる、相手への尊重から始まるんです。でも僕らのような都会で育った人間は、自分の弱さを感じる機会が少ない。以前アフリカで、ごみの山で暮らす青年を取材したことがあります。経済的な物差しでいえば、僕と彼には天と地ほどの差があるわけです。でも、命という物差しにおいては全く差がない。むしろ生きていく能力という物差しでいえば、どう考えたって彼のことをリスペクトせざるを得ない。だって自然発火するごみの炎を使って赤飯を炊くんですよ。僕にはそのアイデアもスキルもありません。そんな状況にもかかわらず、正体不明なアジア人に接しようとする彼に、僕は「すごすぎる…」と畏怖の念を抱きました。そういう感情って動物的に伝わるものなのか、だんだんと向こうも心を開いてくれます。すると、言葉なんて通じなくてもコミュニケーションができるんです。
高野自分の力ではどうにもならない世界に身を投じることで、“生かされている自分”に気付くと、相手へのリスペクトにつながるということですね。
上出東京のように「死ぬかも…」と思うことがない安全な場所では、自分を「強いと過信してしまう人が多い。その思い上がりが、いつの間にかコミュニケーションの障壁になっていると感じます。

別世界の人との接し方は、ヒト以前に自然が教えてくれた
高野上出さんには『日本という先進国から来たディレクターなんだぜ』みたいな上から目線がない。だから海外の人とも気持ちが通じ合うのではないでしょうか?
上出おそらく、自然と接することでそういった感覚が育まれたのだと思います。若いときから山登りをしていたのは大きいです。例えば、山奥で雨に打たれた経験があると、屋根や傘のような文明の利器に頼ってきた自分の弱さを知ることができます。そうした経験を重ねていると、どこにいても『今この状況で、どちらの方が生存力が高いのか』と相手を見定めるようになる。会社のお偉いさんと会ったとしても、高価な時計や服装が気にならなくなるんです。さらに海外に出てみると、『東京で育った人間なんて、世界最弱だ』と気付かされ、相手をリスペクトせざるを得なくなります。ヒトとクマの関係にも似ていますよね。山の中で食糧を探す力も、対峙(たいじ)してけんかする力も、ヒトの方が圧倒的に弱い。にもかかわらず、人間は偏った万能感を抱き、距離感を間違えるから、結局ひどい目に遭ってしまう。自然は自分のおごりを思い出させてくれます。

高野私はミクロネシアのヤップ島に青少年を連れて行くプログラムを行ってきました。ヤップ島は今でも石貨を使う文化で知られていて、身近にある資源だけで暮らす自給自足の力を、現代も住民の方々が持っているんですね。そこに産業国である日本から若い人たちを連れて行くわけですが、みんな着いた瞬間に『ここでは生きていけない』と悟るんです。そして、『どうやったら火を付けられますか』『どれが食べられる植物ですか』『皆さんの芋をいただいてもいいですか』と、懸命に現地の人とコミュニケーションを取るようになる。上出さんの言う畏怖の念の大切さは、すごく理解できます。
上出切迫した必要性から生まれる感覚って、海外や自然だけでなく、日本の都会でも基本になると思います。そもそもコミュニケーションが必要になるのって、基本的には自分が聞きたいこと、語りたいことがあるときです。以前、靖国通りで右翼団体の方に突撃取材をしたことがあります。彼らは必死で機動隊ともみ合っていた最中だったのですが、『なぜ500人もの機動隊の中に、たった2人で立ち向かっていくのか』という明確な興味を示したら、相手も真摯(しんし)に答えてくれました。話す目的を明確にするのも重要で、それを抜きにしてコミュニケーション術や外国語を学んでも、意味がないんです。


“考えさせない”社会では、コミュ力は育たない
「相手を尊重する」「共同作業をする」「目的を明確にする」。二人の考えるコミュニケーションの本質は、至ってシンプルです。にもかかわらず、なぜ私たちはコミュニケーションに悩まされるのでしょうか。
上出僕が会社を辞めて、アメリカへ飛び出した理由に、日本特有の“減点方式”に嫌気が差したことがあります。例えばアメリカでお気に入りの服を着て歩いていると、「その合わせ方いいね」「どこで買ったの?」と、良いところを見つけ出そうとしてくれる。一方の日本では「そんな服を着ていて大丈夫?」みたいな、ネガティブな目線から話が始まりがちです。組織でも出世するのは失敗を恐れずチャレンジした人より、保守的で減点されなかった人。だから誰も挑戦しなくなる。そんな閉塞(へいそく)的な雰囲気の中で、コミュニケーションが大事だなんて言われても、困りますよね。

高野それは感じます。アメリカでは人の良いところを評価しようとするから、相手に対して怖がる必要がなく、ありのままのフラットな状態でいられることが多いです。
上出やはり島国であることが影響しているのでしょうか。小さな空間では、裏切り者をいち早く見つけることが生存戦略となり、それが縄文時代から脈々と受け継がれてきた。しかし現在、グローバル経済の時代になり、国際競争から逃れられなくなった。経済が低迷する中、みんな余裕がなくなって、内輪のコミュニティーを強化しようとする。だからヘイトスピーチや陰謀論が生まれてしまっているように感じます。

高野島国でも希望はあるはずです。例えばイギリスも島国ですが、小学校では自分で課題を設定して調査したり、文字や図表でアウトプットしたり、プレゼンをしたりと、自分の考えを他者が理解できるように思考を鍛えます。そんな教育はハードではあるものの、自ら考える力が養われ、「相手は違って当たり前」「他者を理解し、尊重すべき」という価値観が育まれるでしょう。
上出考えさせない教育は、日本の課題ですね。だからみんな自分の物差しを持てなくなり、他人の評価ばかりを気にするようになって、コミュニケーションも取りづらくなるのでしょう。
高野自分の頭で物事を考えないまま大学に入り、突然「自分で将来を決めなさい」と言われても、びっくり仰天ですよね。それで慌ててしまい、「どこでもいいから雇ってください」と就活中心の価値観に陥ってしまう学生も少なくないです。社会に出ても自分で考え、自分の言葉で話すのが難しくなり、企業側もますますコミュニケーション能力を強調するようになる。環境の要因が大きいので、学生さんたちは全く悪くないのは確かです。

日本から脱出せよ。必ず良い生き方が開かれる
閉塞感がまん延する現代日本。これから社会に出る次世代の学生は、どのように生きるべきなのでしょうか。二人に実践論を伺いました。
上出絶対に一度、日本を出た方がいいと思います。「こんな生き方もアリなんだ」と感じる経験をたくさん積めば、その先の人生における礎になるからです。小さな世界で生きていると、「こうじゃなければならない」と考え方がどんどん硬直し、コミュニケーションの幅も狭まってしまいます。固定的な考えを壊してくれるのは、旅しかありません。
高野旅といっても、パッケージツアーではなく、自分の足で歩くことがポイントですね。本やインターネットで読んだ世界を、はるかに凌駕する経験が重要ですから。私自身も、さまざまな人との出会いの中で、「健全な自然さえあれば、人は生きていける」という、人生の指針のような考えを体得しました。実は私も学生時代に参加したことがあるのですが、早稲田はさまざまな留学プログラムを提供しています。まずは一歩踏み出してみるのがお勧めです。
上出文明から離れ、自然と触れ合っていると、東京では当たり前のことが、いかに特別なことかを実感します。自分の基準を自然の方に移していくことで、物事における必要なハードルが下がっていき、強く生きる力を身に付けられます。旅を経て日本に戻ったとしても、必ず役に立つはずです。海外が難しければ、まずは日本で山登りをするのもいいでしょう。
高野人との出会いの中で、自分を見つめ直すのも大切だと思います。多様な人に出会い、「こんな生き方もあるんだ」という発見に恵まれると、自分自身が“よく生きる”ことにつながるからです。よく生きることは、コミュニケーションの源泉のようなもの。その出会いはインターネットでは味わえません。ちょっとつらかったり、痛みを伴ったりする、“生身”の経験が、自分を強くしてくれるんですよね。
上出肉体的に負荷がかかる、直接的に痛みを感じる経験は、相手の痛みを知る思考にもつながります。そうした機会が極端に減ると、平気で人を傷つける世界に変わってしまうのでしょう。“痛みがいかに、クリティカルに人間の尊厳に関わるのか”を体験するためには、衝突や事故が起こる環境へ、自ら出向くしかありません。ぜひ若い皆さんにはそうした経験を通じて、強く優しい人間になってほしい。世界を広げる経験は、コミュニケーションなんて余裕に感じられるようなかけがえのない力を、私たちに与えてくれるはずです。

相澤 優太(2010年第一文学部卒)
撮影
布川 航太
編集
株式会社KWC
デザイン・コーディング
株式会社shiftkey
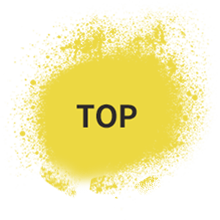













上出「ヤバい世界のヤバい奴らは何食ってんだ」をキャッチコピーに、普通は誰も踏み込まない場所で、「飯を見せて」とお願いしてきました。知られざる彼らの日常や思考に密着するわけですが、そう言うと表面上はずいぶんと俗悪な仕事をしてきたように聞こえるかもしれません(笑)。何かを伝えることの大切さを知ったのは、早稲田の学生時代のことです。ハンセン病で隔離された中国の村でボランティアをして、自分が想像する世界の外側にあるような、抜け出すことのできない差別を受ける人々と出会ったことでした。映像ディレクターとしての僕の人生に大きな影響を与えたと思います。