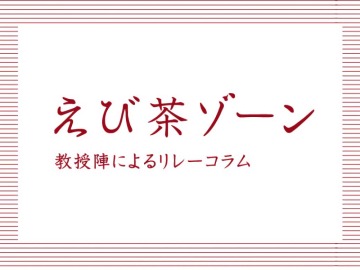
一昔前は時間がかかって苦労した課題や作品も、今や便利なツールが一瞬で解決したり制作したりしてくれる上、玄人並みに仕上げることができる時代となった。
特に、2020年のコロナパンデミック以降、情報機器を活用した講義が当たり前となったことは、学生のコンピューターリテラシーの向上を促し、短期間で質の高い課題や作品を生み出す原動力となった。加えて、オンライン授業やテレワークなどといった社会現象を受けて、情報機器自体もさらなる進化を遂げたことは、学習や業務における利便性を向上させることに大いに貢献した。
しかしながら、メリットばかりではない。便利な環境が構築された反面、学生が取り組む課題量は増加した。なおかつ、誰もが質の高い作品を生み出せるようになったことは、独創性や創意工夫が問われることになり、必然的に一つの課題に取り組む時間が増え、それが複数に及んだ結果、心の余裕を無くしてしまう学生を続出させることにつながってしまったのである。
時間をかけて試行錯誤し、完遂する喜びを味わうことは教育において必要不可欠だろうが、時短や効率化が推し進められ、生成AIまでもが実用化され始めた時代において、この思いはどこまで通用し続けるのだろう。そして、教員を志す学生たちは、現代の環境にもまれて、将来の教育にどのような望みを託すのだろう。同僚となった際にはぜひゆっくり話してみたいものである。
(R.O.)
第1157回








