「障がい者と健常者の境を無くしていきたい」
大学院スポーツ科学研究科 博士後期課程 4年 岡田 美優(おかだ・みゆ)

早稲田キャンパス 3号館前にて
2022年に一般社団法人Knockü(のっきゅー)を設立し、障がいの有無に関わらず参加できるパラスポーツのイベントやコミュニティーの運営、またパラスポーツを通じた教育研修プログラムを実施している岡田さん。早稲田大学大学院ではパラスポーツ事業の効果を研究し、スポーツ庁の「障害者スポーツ振興ワーキンググループ」の委員に選出され、公の場での発信も行っています。さまざまな側面からパラスポーツにアプローチする岡田さんに、パラスポーツへの傾倒の経緯や大学院進学の理由、一般社団法人Knocküでの活動、そして今後の展望について聞きました。
――パラスポーツに興味を持ったきっかけは何ですか。
両親が特別支援学校の教員だったことと、私自身ハンドボールを11年続けていたことで、障がい者支援とスポーツの両方に元々興味がありました。大学3年生のときにたまたまパラスポーツのボランティアに参加する機会があり、それをきっかけに関心が高まったんです。その後、パラスポーツ先進国であるドイツでパラスポーツの普及に努める、ケルン大学名誉教授のホルスト・ストローケンデル博士が来日した際の講演を聴いて、車いす操作の技術を学んだのですが、それがとても面白くて。パラスポーツには障がいのある人とない人が一緒に参加できるような仕組みやルールがあり、特に車いすスポーツはマイノリティー側(障がい者)がマジョリティー側(健常者)に合わせるのではなくて、マジョリティー側がマイノリティー側に合わせる形で一緒にスポーツを楽しめるので、より一層魅力的でした。もっと深くパラスポーツを学びたいと感じたことが、ドイツ留学への契機になったと思います。

Knocküの活動で車いすハンドボールが行われている様子
――ドイツ留学ではどのようなことを学びましたか。
ドイツでは、ホルスト・ストローケンデル博士の授業や講習会にたくさん参加しました。また、ドイツ各地にあるスポーツクラブを巡りながら、障がいのある人とない人がどのように共にスポーツをしているのかを実際の現場で学びました。ドイツでは、地域住民や市民が主体となって活動し、障がい者も利用できる民間のスポーツクラブがどこの地域にも存在していて、スポーツクラブで運動することが障がい者にとってとても身近であることに衝撃を受けました。
一方日本では、障がい者が民間のスポーツ施設を利用することには大きなハードルがあります。なぜなら障がい者は障がい者スポーツ専用・優先施設で活動することが想定されている上、全国で 25カ所しか設置されていないためです。このことから、地域に根差した、障がい者と健常者の境がないスポーツ環境を、日本でも実現したいと強く思ったんです。
写真左:ホルスト・ストローケンデル博士が、車いすのキャスター上げという操作技術を日本から来た理学療法士に指導したときの一枚
写真右:ドイツのパラスポーツイベントの様子
――ドイツから帰国後、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科に進学しています。その理由と大学院での研究内容を教えてください。
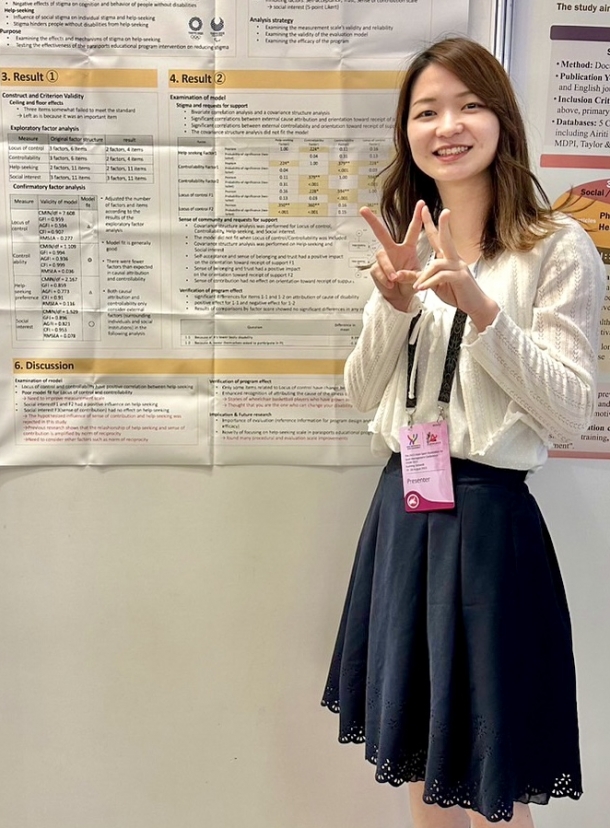
今年 8 月、マレーシアでの学会発表にて。パラスポーツ事業におい て、明確な目標や成果指標を設定せずに施策を作っている現状に問題提起をした。効果がより可視化され、社会課題解決や社会貢献活動の ための投資額がますます増えることを期待しているという
ドイツ留学を通して、国の政策や施策によってパラスポーツの実態が大きく変わってくることを実感してから、パラスポーツビジネスの仕組み作りにとても興味が湧き、より深く勉強したいと思いました。早稲田の大学院はスポーツビジネスや地域スポーツクラブについての研究で有名でしたし、国際学会に参加されている先輩も在学していたことから、さまざまな挑戦ができるのではないかと考えて進学を決めました。
現在は総合型地域スポーツクラブや組織論を専門とする作野誠一先生(スポーツ科学学術院教授)のゼミに所属して、パラスポーツ事業の効果について研究しています。具体的には、障がい者も参加できるスポーツクラブが存在することが、地域社会や障がい当事者の方々に対し、どのようなインパクトを与えるのかを評価しています。
――2022年には一般社団法人Knockü(のっきゅー)を設立していますね。
障がいの有無に関わらず、パラスポーツに参加できる環境を実現するために、Knocküを立ち上げました。実は2020年の大学入学とほぼ同時に、任意団体として活動を始めていましたが、パンデミックのためオンライン上での活動がメインでした。Knocküで発信した情報を見た学校などから講演依頼を受けることもあった中で、お仕事をいただく上では信用に足る団体であることが重要だと思い、2022年2月に一般社団法人化しました。
初めはお金も仲間も実績も何もかもが無い状態で、確かなビジョンのみを携えてのスタートでした。一から全て自分の力で築きあげなくてはならなかったので、とても苦労しました。今振り返るとここまでは、いばらの道のようでした。例えば、パラスポーツで使う車いすは 一台20~30万円と高額で、資金調達のために民間企業へ電話を掛けて支援をお願いしても、断られることがほとんどでした。さらに、車いすが利用可能な体育館が限られているなどの課題もありました。少しずつ実績を作っていく中で、次第に自分のビジョンに共感してくれる仲間や協力してくれる企業、施設が増えていきました。

Knockü 設立メンバーとの1枚。「Knockü」という名前には、障がい者自身が、自分は健常者には理解してもらえないだろうと閉ざしている心や、健常者が無意識のうちに障がい者に対して抱いてしまう距離感に対して、互いに心の扉をknockして分かり合えたらという思いが込められている
現在はKnockü S.C.(のっきゅースポーツクラブ)を運営して、障がいの有無、競技志向などにとらわれずにスポーツができるチーム環境を提供しています。またKnocküカップ(のっきゅーカップ)という、誰もが自分のレベルに合わせて参加することができる車いすハンドボールの大会を運営しています。自治体などから依頼を受けて、パラスポーツのイベントで車いすハンドボールのブースを出すなど、パラスポーツの普及活動を行なうこともあります。

Knockü S.C.のメンバーの写真
――ところで、スポーツ庁の「障害者スポーツ振興ワーキンググループ」の委員としても活動しているのですね。
ドイツへの留学は文部科学省が実施している留学促進キャンペーン「トビタテ! 留学JAPAN」を利用したのですが、そのつながりで親しくなった方にスポーツ庁の「障害者スポーツ振興ワーキンググループ」に推薦していただき、2022年12月から参加しています。会議では毎回テーマが設けられるのですが、前回は障がい者スポーツ施設の活用についてでした。障がい者がスポーツをする場を、専用施設から徐々に地域のスポーツクラブに移行するような仕組みが必要なのではないか、という提言を私がしたところ、報告書にも記載していただき、自分の意見が施策に反映されている実感を持てました。
――岡田さんの今後の活動の展望を教えてください。
今年の3月にも2週間ほどドイツへ留学したのですが、そこで8人のスポーツクラブの経営者に直接インタビューをさせていただいたことで、“障がい者が日常的にスポーツを楽しむことができるドイツの仕組みを日本でも実現したい”という思いを新たにしました。そのためにまずはKnocküでの活動を広げるとともに、パラスポーツビジネスの研究を続けることで国の施策や政策面にも働きかけを行い、アカデミックな観点からもアプローチしていきたいと思っています。時間は掛かるかもしれませんが、いつかできると信じて挑戦していきます。
第855回
取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)
文化構想学部 2年 浮谷 雛梨
【プロフィール】
 神奈川県出身。福島大学人間発達学類卒業。小学校から大学までハンドボールを11年間続け、全国大会にも出場する。2022年には一般社団法人Knocküを設立し、代表理事を務める。休日にはキャンプに行ったりサイクリングをしたりと、アクティブに過ごすのが好きなのだとか。
神奈川県出身。福島大学人間発達学類卒業。小学校から大学までハンドボールを11年間続け、全国大会にも出場する。2022年には一般社団法人Knocküを設立し、代表理事を務める。休日にはキャンプに行ったりサイクリングをしたりと、アクティブに過ごすのが好きなのだとか。
X(旧Twitter) : @miyu_rollstuhl










