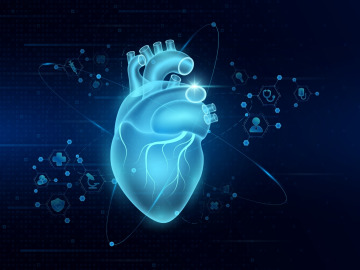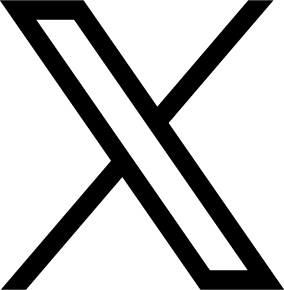理工学術院総合研究所の若手研究者育成・支援プログラム 『アーリーバード』。12月8日夕方、この日は、メンバーである若手研究者発案・企画の『クラウドファンディング勉強会』を開催しました。

クラウドファンディング(CrowdFunding)は、群衆(Crowd)と資金調達(Funding)を組み合わせた造語で、個人や団体が、アイデアの実現などの「ある目的」を達成するために、インターネットを通じて不特定多数の一般の方から出資を募ることをいいます。この仕組みを、研究費の調達方法としても活用することが最近注目されていますが、「聞いたことはあるけど、実際どんな人が活用しているのか」「本当にお金が集まるのか?」など、疑問がいっぱいです。
そこでアーリーバードでは、研究費調達手段としてのクラウドファンディングを理解するとともに、他大の若手研究者との交流を目的として、京都大学ウィルス・再生医科学研究所 助教の飯田敦夫先生をお招きし、現在に至るまでの研究者のキャリア、ポスドク生活についてのお話を伺いつつ、クラウドファンディングをどのように研究に活用してきたかについてご講演をいただきました。
「自分だけの、オリジナルな研究を始めたい!」
ポスドクの期間中に、研究室の研究活動をちょっとはみだして、自分だけのオリジナルのテーマに挑戦してみたい!というのは、どの若手研究者もいつか は直面する課題です。飯田先生は、そのような時にクラウドファンディングを上手に活用し、オリジナリティあふれる研究の展開につなげることができたと説明 します。 実際、現在飯田先生は、所属する研究室でのゼブラフィッシュをモデルとした発生生物学の研究だけでなく、魚類なのに体内受精で妊娠し、お腹の中で子供をそだてて出産する魚『グーデア科胎生魚』研究の第一人者としてもご活躍されているのです。
「研究費の補助的な選択肢として。ほどほどに」
一般の方に、自分の研究のおもしろさや大切さを伝え、出資したい!とまで思っていただくことは容易ではありません。クラウドファンディング挑戦にあたっては、研究をわかりやすく説明する動画コンテンツ作成して配信サイトに掲載したり、思わず出資したくなるような、魅力的なリターン(おかえし)を考えたり。また、SNS上の一般の方からの質問への細やかな対応は、慣れるまでに苦労したとのこと。 同じ研究テーマで、2回目以降の資金獲得の難しさを考慮すれば、クラウドファンディングは科研費の代替となるような研究費としてではなく、あくまでも補助的な選択肢として、有効であると説明しました。
「アウトリーチ ⇒ 研究費獲得 ^_^ 」
ポスドクという立場で、自分オリジナルの研究を一般の方に分かりやすく紹介するような機会はほとんどありません。クラウドファンディングへの挑戦を通じて、一般の方に自分の研究の面白さや大切さを伝える→一般の方の賛同・協力を得て研究を展開するという、社会とのつながりを意識しながら研究ができるようになった事を考えれば、金額や労力にかえられない価値があったと言います。実際、動画配信やSNSの活動などがきっかけとなり、魚類研究に関するテレビや新聞等マスコミからのインタビュー取材の機会が増加したそうで、自身の研究そして研究者としての自分自身が一般の方に認知されたことを実感できたと語りました。
飯田先生の研究者としてのパッションに圧倒されたあっという間の2時間。勉強会のあとは、余韻そのままに飯田先生と飯田先生と同じ研究分野の他大の研究員の皆さんを交えて、懇親会(通称:イブニングバード)を開催。お互いの研究生活について、おいしいものを食べながら大いに語り合いました。
次回のアーリーバードでは、学会発表や研究費申請などにおいて、限られた時間・スペースで自身の研究を魅力的に伝えるられるよう、プレゼンテーション資料やポスターのデザインスキルを学ぶワークショップを開催します。 理工の若手研究者たち、今日も意欲的に頑張っています!
アーリーバードの活動はFacebookで随時お知らせしています。