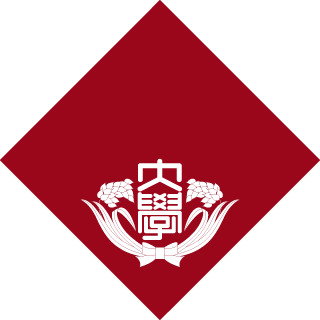早大アスリート特集第3回目は早稲田大学フェンシング部に所属している加納虹輝選手です。今年2月に行われたバンクーバーW杯で個人優勝、3月のブエノスアイレスW杯で団体優勝と、世界の舞台で結果を残しており、2020年の東京五輪のメダル獲得が期待されています。
今回のインタビューではオリンピックに懸ける思い、そして加納選手の到達点についてお聞きしました。

フェンシングとの出会いと早大の進学
――フェンシングを始めたきっかけは何でしょうか。
小学校6年生の時に北京五輪で現フェンシング協会の会長である太田雄貴さんが銀メダルを取ったところを見て、その時点でフェンシングというものを知りました。かっこいいなと思って地元のクラブに行き始めました。
――フェンシングには、フルーレ、エペ、サーブルの3種目がありますが、エペを選んだ理由は何でしょうか。
高校1年生の時までフルーレをやっていて、エペは遊び半分で大会に出ていたのですが、高校1年生の時に出たU17の代表選考会の大会の一つで、なぜかエペで優勝してしまって、そこから徐々にエペに興味を持ち始めました。
――本格的に始めたのはいつからでしょうか。
高校2年生になってからです。
――今までに影響を受けた選手はいましたか
現在男子エペ日本代表のコーチをしている西田祥吾コーチです。北京五輪にエペで出場されているのですが、僕がエペを始めるときに西田さんの北京五輪の動画がYouTubeに上がっているのを見てエペはかっこいいなと思いました。それもエペを始めたという理由です。影響は大きかったですね。
――数ある大学から早稲田大学を選んだ理由は何でしょうか。
高校の時の指導者が早稲田出身で、高校生の時に早大の練習に来ていましたが、その雰囲やOBからの推薦もあり、早大に入学しようと決意しました。
――東京五輪を意識し始めたのはいつ頃からでしたか。
大学1年生の時からシニアの大会に出場し始めていて、2年生の夏に初めて世界選手権に出場した時には、世界ランキングが圏外から17位まで上がっていました。その頃からオリンピックに行ける可能性が出てきたので、意識し始めました。
――早大の選手の中で刺激を受けた選手はいらっしゃいますか。
1つ上の松山恭助(2019スポ卒=現JTB)先輩ですね。種目は違いますが、松山先輩のここぞというときの強さや集中力は見ていて驚きますし、簡単に取り入れられるものではありませんが、努力しないといけないと思いながら試合を見ています。

2つの世界大会から得た課題と収穫
――6月に行われたアジア選手権はベスト16で敗退しましたが、この結果はどのように捉えていますか。
その日、調子は悪くなくて上手く調整もできていたのですが、日本人選手同士で当たってしまうと、普段練習していることもあり、手の内が分かっていたので、お互い五分五分の状況で負けてしまったのは、しょうがないなと思いつつも悔しかったです。ただ、調子は悪くなかったので、その後の世界選手権に向けて気持ちをすぐ切り替えました。
――アジア選手権から7月の世界選手権までの間に特別な調整は行っていましたか。
世界選手権の前にロシアで10日間ほど合宿をしたのですが、ロシアはかなりの強豪で、強い選手たちと剣を交えることによって、感覚が研ぎ澄まされていきました。そこでレベルアップができて、後半は徐々に練習を軽くしていき、コンディションを上げるようにしていました。
――世界選手権の個人戦を振り返っていただけますか
調整がうまく行ってコンディションも万全な状態だったので、ベスト64、32、16を楽に勝てたと言いますか、圧勝することができました。ベスト8で当たった選手はロシアの選手でしたが、あまり得意とはしていない選手で、強いというのもありますがここはヤマ場だと思っていました。ここを勝ったら優勝できるのではないかと思っていたのですが、そこを乗り越えられなかった自分の甘さがあったと思います。
――勝ち進むにつれ接戦が多くなっているように感じました。接戦となった時に意識していることはありますか。
基本的には次の1点をどう取るか、そこだけに集中しているので、接戦や点数はそこまで気にしないように心がけています。
――リーチのある外国人選手を相手にしたときに意識していることはありますか。
まず相手よりも動く。動き負けは絶対にしてはいけないので、ただ動けばいいというわけではないですが、相手よりも動いて自分にチャンスが来るように作っていくことを心掛けています。
――以前持ち味と話されていたスピードで相手を翻弄(ほんろう)する戦略は、世界選手権では発揮できましたか。
そうですね。自分なりにいい感じにはできていました。ただそれだけ動くにあたって体力も必要になってくるので、ベスト16、8まで勝ち上がってくると、かなりしんどくなってきてしまいます。そこでも相手より動いていく必要がありますが、世界選手権のベスト8の試合では、後半、特に最後の方は動き負けてしまいました。
――団体戦は2大会とも力を出し切れていなかった印象がありますが、敗因はどこにあると考えていますか。
前半にリードをされてしまう展開が多かったですね。日本の戦い方として前半リードするということがかなり重要で、そこでリードを取れなかったということが大きいと思います。その要因として立ち上がり、スロースターターな選手が多いところがあるので、そこが今後の課題です。1試合目、2試合目から出し切って相手を翻弄(ほんろう)していくということが課題だと思っています。
――それでは団体戦の収穫は何だったでしょうか。
アジア選手権の準決勝で中国に負けてしまいました。中国には今までに何回か当たっていたのですが、大事なアジア選手権で戦法を変えてきて、応えきれませんでした。戦法を変えてきた時にも自分で考えて対応していけるようになっていかなければならないと思いました。
――団体戦でベンチにいるときは何を考えているのでしょうか。
試合をしている選手を見て、まだ自分が試合をしていない選手であれば、どういう癖があるかを見つつ、チームの雰囲気も重要なので、仲間の選手を応援することを意識していますね。
――団体戦は中国や韓国がライバルとなってくると思うのですが、そこに勝つにはどういったところが必要になるでしょうか。
個々の実力はもう問題ないと思っています。あとは、団体戦は1試合1試合が個人戦と比べると短いので、短い中で距離や歩調を合わすとか、相手の癖を見抜くとか、早い判断ができるようになる必要があるかなと思います。

「特別な大会」――東京五輪ではメダルを
――オリンピックに対してどのようなイメージをもっていますか。
まだオリンピックに出場したことがないので、どんなものかも分からない上に、出場できるかも分かりませんが、楽しみにしています。世界選手権やW杯といった今までの世界大会と違って特別な大会だと思いますし、そこでメダルを取ることで注目されます。人生において出場できて最高でも4、5回だと思うので、少ないチャンスしかなく、貴重な大会だと思っています。
――東京五輪に向け、ステップアップしなければならないことは何でしょうか
東京五輪に出るためには個人戦より団体戦が重要になってくると思うので、団体戦のチーム力をつけることが必要です。最近は団体戦を練習の中で取りいれました。それから海外の選手と合宿をして、海外選手との団体の戦い方を学んでいく必要があると感じています。
――今のオフシーズンは何をされているのでしょうか。
フェンシングの練習は世界選手権が終わってから今日(8月6日)まで1回もやっていないのですが、チーム自体は19日までオフということになっているので、その期間はトレーニングをメインにしています。
――最後に東京五輪の意気込みをお聞かせください。
3月で東京五輪の出場が決まるので、そこで団体の出場権をまず獲得することです。そして東京五輪では個人、団体でメダルを獲得できるように頑張っていきたいと思います。
早稲田スポーツ新聞会
記事 小原央 写真:馬塲貴子