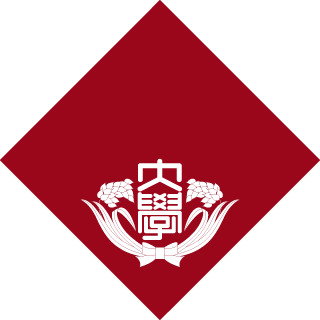VIVASEDA代表 大学院環境・エネルギー研究科修士2年 大井 晃亮
 2020年9月からは学生オリパラプロジェクトVIVASEDA代表として、大学、企業など様々な関係者と活動を行う際の調整や、メンバーをまとめる役割を務めさせて頂いております。
2020年9月からは学生オリパラプロジェクトVIVASEDA代表として、大学、企業など様々な関係者と活動を行う際の調整や、メンバーをまとめる役割を務めさせて頂いております。
私がVIVASEDAへの参加を決めた理由は、自国開催のオリンピック・パラリンピックに学生という立場で関わることができるのは非常に貴重な経験となると考えたためです。
団体が立ち上がったばかりの頃は手探りの中、活動を進めることも多くありました。そんな中でも、メンバー同士協力しながら東京2020大会に向けて多くのプロジェクトを始動させることができました。しかし、2020年からは新型コロナウイルスの感染拡大が始まり、予定していたプロジェクトは軒並み中止となってしまいました。さらに、東京大会が延期され、メンバーの士気が下がっていると感じることもありました。しかし、東京大会の開催が確実なものになると、メンバーに活気が戻り、再び活動に懸命に取り組むことができたのかなと思います。まさにこの2年半は変化に富んだ激動の期間でしたが、同時に多くの学びもありました。
苦労したことは2021年に東京大会が延期となり、自分自身もどうして良いかわからない中、団体としてどのように活動を継続するかを考えなければならなかったことです。しかし、そういった逆境の中でも、工夫を重ねて活動を継続し、粘り強く取り組むことの大切さを学びました。
これからはVIVASEDAで学んだことを活かして、自分で立ち上げたプロジェクトに多くの人を巻き込みながら、リーダーシップを発揮することのできる人材になりたいと考えています。
OISインターンシップ 政治経済学部4年 國岡 千乃
 幼少期からスポーツが大好きで、その魅力を伝えるスポーツジャーナリストになりたかったためにOISのインターンシップに参加しました。
幼少期からスポーツが大好きで、その魅力を伝えるスポーツジャーナリストになりたかったためにOISのインターンシップに参加しました。
大会期間中は毎日異なる会場に出向き、試合を終えた選手にインタビューをしました。その内容はオリンピックの公式サイトに談話として掲載されました。英文で執筆をするため、日本人選手の場合は自分で英訳を行い、原稿をリリースしました。特に印象に残っている取材は2つあります。1つ目は、現在私が大学で競技をしているホッケーの取材です。プレーはもちろん、インタビューからチームのまとめ方、試合中の立て直し方などを伺うことができ、同じスポーツの競技者として学ぶことばかりでした。これから少しでも学んだことをチームに還元したいと思います。2つ目は、カヌースラロームの取材です。前回2016年リオデジャネイロ大会の銅メダリスト、羽根田卓也選手が決勝を10位で終えた後、取材陣に対して見せた涙が印象に残っています。羽根田選手の活躍により競技が注目されるようになった嬉しさ、地元開催も相まって高まった結果への期待には応えることができなった悔しさ、決勝の舞台でレースができた楽しさ、様々な感情が詰まった涙を見て、この日のために人生をかけて挑戦をしたアスリートの尊さを改めて感じました。
この活動を通して、学んだことは準備の大切さです。インタビューをするときは、競技や選手の情報を事前知識として把握したうえで、試合を見て簡潔かつ的確な質問をしなければいけません。私は英語が得意ではありませんでしたが、語学力も大切な準備のひとつであったと大会期間中に痛感しました。これらの準備は取材対象であるアスリートへ敬意を払う、ということに通ずると思いました。
幼い頃からの夢をオリンピックでかなえることができ、送り出してくれた大学や受け入れてくださったOISに感謝しています。ジャーナリズムとは異なる進路を選択しましたが、今後も様々なことにチャレンジしていきたいと思います。
イタリアチームボランティア 人間科学部4年 西岡 実李
 2019年の「イタリア競歩チームの事前練習」では、選手の荷物監視・タクシーの手配・選手への給水を行いました。2021年夏の「所沢キャンパスでの事前練習」では、新型コロナウイルス蔓延中ということで、感染対策が第一であったという印象です。例えば、選手がジムを使用した後に器具を消毒したり、ディスタンスが取りづらい場所で学生と代表選手が鉢合わせにならないように無線で状況を伝え合ったりしました。
2019年の「イタリア競歩チームの事前練習」では、選手の荷物監視・タクシーの手配・選手への給水を行いました。2021年夏の「所沢キャンパスでの事前練習」では、新型コロナウイルス蔓延中ということで、感染対策が第一であったという印象です。例えば、選手がジムを使用した後に器具を消毒したり、ディスタンスが取りづらい場所で学生と代表選手が鉢合わせにならないように無線で状況を伝え合ったりしました。
参加を決めたきっかけは主に2つあります。1つ目は、責任感を感じたからです。オリンピックという国際交流・理解を目的にした大会が東京で行われるからには、盛り上げる一員になりたいと思いました。2つ目は、水泳選手と留学の経験があったからです。スポーツ・海外への関心が掛け合わさることでボランティアへの意識へ結びつきました。
活動期間を振り返り最も感じたことは、選手とボランティアの「つながり」です。感動を生み出すアスリートのサポート役として欠かせない存在だと感じました。特に、新型コロナウイルス蔓延により辞退するボランティアが多い中での開催でしたので、私たちの必要性が際立ったと感じました。結果として、微力ですが五輪全体が盛り上がることに貢献できたと感じます。
活動として苦労したことはありませんが、新型コロナウイルス蔓延下という精神的な苦しさを感じる瞬間はありました。五輪開催に反対している医療従事者の方のニュースが放送され、複雑な気持ちになることはありました。しかし、いざ五輪が始まると盛り上がりを見せている様子はとてもうれしかったです。自分が後悔しない道(ボランティア参加)を自分の意思で選ぶことの大切さを学びました。
これからの目標は、多様性が当たり前に認め合える環境づくりに貢献することです。就職先では食の多様性と自然環境の保全の両方に関わることになるので、全ての命を大切に考えて客観視できる人間になりたいです!
アシックス通訳ボランティア 文化構想学部2年 秋吉 正太
 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会でアシックスがアスリートに行うサービスに通訳として携わった。志望した理由は二つあり、一つはインターナショナルスクールで培われた自分の言語力がビジネスの場でどれくらい通用するか確かめたかったからだ。二つ目は、大会運営の裏側で、それぞれの機関が果たす役割を間近で見たいと思ったからだ。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会でアシックスがアスリートに行うサービスに通訳として携わった。志望した理由は二つあり、一つはインターナショナルスクールで培われた自分の言語力がビジネスの場でどれくらい通用するか確かめたかったからだ。二つ目は、大会運営の裏側で、それぞれの機関が果たす役割を間近で見たいと思ったからだ。
活動内容は、世界各国のアスリートにアシックスのサービスを提供する際の通訳業務だ。オリンピックでは選手の足のサイズを測定し、足に合った伸縮性のあるサンダルを提供する。またパラリンピックではクールタオルの提供、身体に合わせた競技着の裁縫、開発途上国の選手への用具の提供も行った。
活動で学んだことは自分の「当たり前」を一度疑ってみること、そして「裏側」を知ることの重要性だ。靴一つにおいても国や地域、また競技によって履いたときの「快適さ」の定義や状態が異なるため、こちらがきつくないかと心配しても逆にその選手の好みだったという経験をした。このとき、自分たちの「当たり前」を押し付けるのではなく、相手の立場にたつことの重要性を学んだ。また、今回アシックスは無料で多岐にわたるサービスを選手に提供した。すぐに現れる利益はないが、選手団がアシックス製品を使うことによって選手村での宣伝効果があることを知った。また商品を試した際にアシックスと契約を希望する選手を目の当たりにしたとき、自分の知らなかった利益の生み出し方に気づいた。社会で起きる事象においても、その背景に注目することで、目的や意義を発見できるようになると考えた。