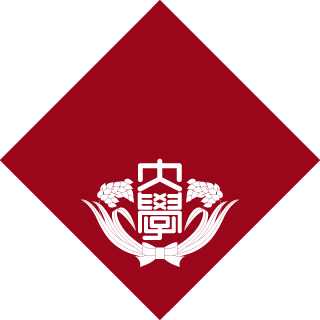地域・地方自治体が直面する課題を学生たちが考え、解決策を提案する。石川県珠洲市での地域連携ワークショップは今年度で4回目を迎えました!
今回のテーマは『空き家の活用アイデア求む!〜すぐ住める「賃貸」の空き家を増やすには?〜』。珠洲市には移住希望者が一定数いるものの、すぐに入居できる賃貸物件は少なく、また、空き家所有者は「賃貸」ではなく「売却」を希望しているという、移住希望者と物件所有者のミスマッチが生じている背景があります。実現可能な、より具体性のある提案をということで珠洲市が本学学生たちの力に期待いただいていることが伺えます。
難易度の高いテーマではありましたが、学生たちは無事にプログラムを終え、事前調査や現地フィールドワーク、そしてチームでの議論を通して考案したアイデアを珠洲市の皆様にお伝えしました。
今回、応募者多数という状況もあり、当初の受け入れ予定人数を大きく拡大し2チーム11名を受け入れて頂きました。珠洲市役所の皆様、本当にありがとうございました。
7月のオリエンテーションでは、学生同士の顔合わせと珠洲市ご担当者から市の魅力やテーマ設定に至った背景などについてご説明頂き、珠洲市の基礎情報について理解を深めました。
また、学生たちの緊張をほぐすために交流会を実施し、ミニゲームを通して仲を深めました。
現地フィールドワークで珠洲市を訪れる前に事前調査とオンラインヒアリングに取り組み、そのうえでそれぞれのチームでテーマに関する仮説を立てました。
仮説検証として、8月7日(月)~10日(木)に3泊4日で待ちに待った現地フィールドワークを実施しました。現地では、本学校友でもある泉谷満寿裕市長との懇談をはじめヒアリングの場を多数ご調整いただき、実際に珠洲市に移住された方や空き家の所有者など、地域の方々の生の声をお聞きするとともに、街並みや観光資源、実際の空き家物件などをご案内いただきました。
とりわけ空き家物件を見学した際、今もそこに人が住んでいるかのような、時が止まったような空間に学生たちは各々思うところがあったようで、珠洲市のことを「他人事」ではなく「自分事」として捉えるきっかけになったと振り返る学生もいました。
9月初めの中間報告会では、現地で収集した情報を基に考察し、珠洲市役所の方々へ現状の考えを提案という形で報告しました。方向性についてお褒めいただく一方で、実現性について厳しい意見を頂いた提案もありました。学生はいただいたご意見やご指摘を真摯に受け止め、さらにそこから考え抜いて、最終報告会ぎりぎりまで話し合いを重ね、提案内容を調整していきました。
最終報告会は、早稲田大学(東京)と珠洲市をオンラインでつなぎ、ハイブリット形式で実施いたしました。泉谷市長をはじめ現地ヒアリングにご協力いただいた方々にワークショップ成果を聞いていただくことができました。
泉谷市長からは内容や考え方について高い評価をいただき、すぐにでも取り掛かれるのではないかと早速市職員へ相談されているものもあり、提案がこれから実際に施策に結び付くかもという期待を感じることができた報告会だったのではないかと思います。
最終報告会後に実施した学生同士での振り返り会では、「はじめは発言もなかなかできなかったが、今では単独でヒアリングができるくらい成長ができた」、「文字や数字では得ることができない現地での感覚があるということに気づけた」など、さまざまな成長や気づきがあったことを実感するとともに、約2か月半、共に一つのテーマに向き合った仲間の良い点を伝えあうことで、このワークショップで得たものを再確認し、活動を締めくくりました。
参加学生の声
- 数年前から「地域創生」に漠然と関心がありました。しかし、行動に移さないまま、気がつけば3年生になってしまっていました。名状しがたい焦燥感に駆られていたときに見つけたのがこのWSです。特に、珠洲市で掲げられていたテーマが興味深かったため、参加できるかはわからなかったけど、申し込むことにしました。応募の際は、就職活動と両立できるか不安はありました。開催時期がサマーインターンの時期と丸かぶりしているからです。しかし、今のところその心配は、徒労に終わっています。(これからどうなるかはわかりませんが、、、)
むしろ、参加してよかったと心から思っています。このWSを通じて得た出会いや気づきは、自分にとって確実に実りのあるものでした。心が動くほうに向かっていった結果、似た考えをもつ人たちに出会い、対話することができました。結局のところ、そういう過程を踏んでこそ、自分のやりたいことの輪郭は見えてくるのだと思います。
少しでも興味を持っているなら参加してみてください。きっと満足のいくものが得られるはず!
(文化構想学部3年) - ワークショップを通して考えた問題は、多くの人が頭を悩ませ、いまだ解決に至らない問題でした。問題の解決策なんてあるのかと思ってしまうこともありました。それでも、そのような問題の当事者として、少しでも解決の糸口がないか考えられたという経験は本当に貴重だと思っています。(創造理工学部1年)
- 私は2ヶ月間に渡る地域連携ワークショップを通じて、様々な気づきを得ることができました。
学部・学年の異なるチームメンバーは、1人1人得意分野がありとても勉強になりました。自分の至らなさを痛感することばかりでしたが、私自身が気づかなかった自分の長所に気づき活かしてくれるメンバーに恵まれ、成長することができたと思います。夏休みは忙しく、限られた時間の中での活動となってしまいましたが、難しい課題に対して私たちなりに答えを出すことができたと思います。
このWSに参加しなければ出会えなかったメンバーと、参加しなければ見ることができない景色を見ることができてよかったです。(商学部2年) - 私は今まで比較的多くの類似したプログラムを体験してきましたが、これだけ長期間にわたって濃密に、かつ「実際の課題を実行される可能性のある施策として」考えることのできるリアリティのある機会はありませんでした。それが故に普段こうした活動では捨象されがちな、チーム内での長期的な人間関係や実際になされた際の資源や効果の問題について、経験が得られたと感じています。過疎化の進む地域での地域社会の課題は、人口の減少し始めた日本全体がやがて抱える問題になる、という認識をしみじみと感じるようになったことも、この活動で得た大きな知見の一つでした。(商学部4年)