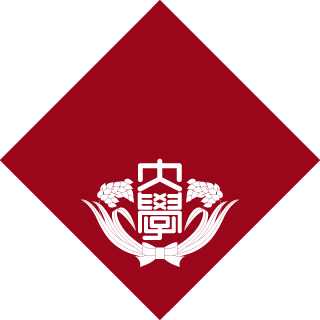地域連携ワークショップ(以下、地域WS)に参加した学生同士の親睦を深めることを目的とした「経験学生の集い」を、昨年5月の第1回に続いて開催しました。イベントには地域WSを経験し今春から社会人となる現役学生2名、社会人として活躍する校友2名がお越しくださり、学生生活の過ごし方や社会人としての日々についてのお話をたくさん聞かせていただきました。
概要
開催日:2023年2月4日(土)13:30~16:00
会場:戸山キャンパス 33号館3階教室
対象:2019年度~2022年度夏編の地域WS参加学生
内容:
第1部 トークセッション
第2部 交流会
トークセッション登壇者(五十音順):
大滝 佐和さん(商学部4年生、2年時に木島平村の地域WSに参加/金融機関に内定)
長谷川 拓海さん(教育学部4年生、2年時に珠洲市の地域WSに参加/テレビ局に内定)
宗廣 開弥さん(2022年3月政治経済学部卒、2年時に木島平村の地域WSに参加/まちづくり・交通インフラ関連企業にお勤め)
若松 美穂さん(2021年3月商学部卒、4年時に堺市の地域WSに参加/エネルギー関連企業にお勤め)

第1部 トークセッション
登壇者の方々にはワークショップに関わるお話のほかに、就職活動や現在のお仕事といったキャリアに関するお話などもたくさん聞かせていただきました。
地域WSに参加した理由やきっかけは?
- 大学2年生でコロナ禍となり時間を持て余してしまっていたため何か自分の成長につながることに取り組んでみたいと思った。せっかく早稲田に入学したのだから色々な学生や学外の方々と交流してみたかった。(大滝さん)
- 高校生の頃、地元のテレビ番組でこのワークショップに関するニュースを見たことがあり入学前から参加してみたかった。もともと地域活性化に興味もあったのでコロナ禍に何かチャレンジしたいと思った。(長谷川さん)
- 正直なことを言えば、ガクチカ(就職活動でよく聞かれる「学生時代に力を入れていたこと」の略称)を作りたかった。旅行や登山が趣味でいろいろな土地を訪れた際に感じていた地方衰退を学生の力でなんとかできないかと思った。(宗廣さん)
- 大学3年時に参加した復興庁主催のインターンシップが充実していたので、卒業を間近に控えたタイミングでもう一度自己成長の機会を欲していた。社会人になる前にさまざまな立場の方と関わることで視野を広げられると思った。(若松さん)
地域WSでの経験をその後の学生生活や就活にどのように活かしましたか?
- 地方創生や地域活性化への関心が強くなり、学問として体系的に学んでみたいという思いから関連する授業を積極的に履修した。そうした授業の多くが少人数で行われており他学部の学生や先生と密に関わる機会になった。将来の進路としてUターン就職を視野に入れていたので、その思いを決定づけるキッカケにもなった。(長谷川さん)
- それまでは講義形式の授業が多かったこともありグループワークのノウハウやコツのようなものをワークショップで学ぶことができた。特に他の学生たちと関わる機会が多くなるゼミでの活動や就職活動のグループディスカッションなどに活かせたと思う。また、同じチームで活動していた先輩が就職活動の相談に乗ってくださり、とても助かった。(大滝さん)
就活はいつ頃、どんなことから着手しましたか?
- 就活を意識し始めたのは3年生の5月頃。まずは「就活とはなにか?」を理解しようと思い、キャリアセンターのホームページで就活の流れを確認することから始めた。将来やりたいことが明確になっていなかったので、世の中にどんな企業や業界があるのか調べる意味も込めてインターンシップに取り組みつつ自己分析を行った。ワークショップのことだけを取り立てて面接などで話すことはしなかったが、自分のパーソナリティを話す上での裏付けの1つとして言及するようにしていた。 (大滝さん)
- 3年生の春の時点でUターン就職することを決めた。Uターン就職となると公務員またはメディア(テレビ、新聞)とある程度絞られることからインターンシップや公務員試験に向けた勉強を並行して取り組んだ。キャリアセンターのオンライン模擬面接やワークショップで関わった大学職員の方に相談するなど、大学のリソースも積極的に活用した。webマガジンの記者をしていた経験から情報発信にやりがいを感じてテレビ局への入社を決めるに至った。(長谷川さん)
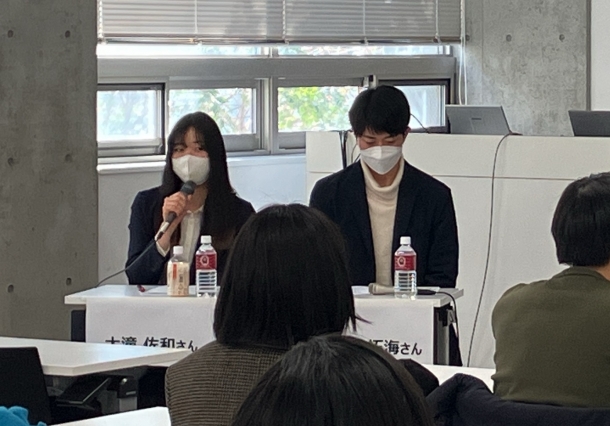
4年間を振り返りながら話してくださる大滝さん(左)と長谷川さん
地域WSでの経験が日々の仕事などに活きていると感じることは?
- 現在は300人程度の部署の総務スタッフとして勤務している。部内の人材育成や年度計画の策定、働き方改革などの施策を立案・実行するために必要なヒアリングでワークショップでの経験が活きていると思う。時として自身の考えと現場の声に差があることもあり、現場の社員がどうしたら快適に働くことができるかを考え抜かなければならない。「現場の声に耳を傾ける」というワークショップでの活動と通ずる部分があると思う。(若松さん)
- 「相手志向で物事を考える」という考え方が今でも活きていると思う。同僚、取引先など会社内外に関係者が多くいる環境にあっては相手の立場になって考えることが求められる。ワークショップでも異なる学部・学年の学生や地域の方々といった多様な方々と関わる中で、それぞれの思いを尊重しながら提案に落とし込んでいくプロセスを経るため相手志向を自然と意識できるようになった。(宗廣さん)
4年間の学生生活を振り返って「これをやっておけばよかった」と後悔していることは?
- 何かに集中する力を維持しておけば良かった。現在、4月の就職に向けた勉強に追われる日々を送っており苦戦しているから。学生生活には誘惑も多く、それによる生活習慣の乱れなどもあるが、受験生時代を時々思い出して集中できる習慣をつけておくと良いと思う。(大滝さん)
- 時間がないことや忙しいことを理由に挑戦を諦めてしまったことが多々あったこと。本当は興味があった分野の授業が6限、7限にあり、サークルやゼミを言い訳にして履修しなかったことは悔やまれる。忙しくとも時間を削りだす意識を持ってほしい。(長谷川さん)
- 今思うと、もっと色々な活動に参加して人脈を広げておくべきだったと思う。社会人になると人間関係は意外と狭い。今日のイベントに参加すること(第2部の交流会)もまさに人脈を広げるチャンス。また、学生時代は興味があることには臆することなくチャレンジした方が良い。(宗廣さん)
- 短期間でもいいので留学をしておけば良かった。学生時代はサークルが忙しいことを理由に留学や海外旅行などを敬遠してしまっていた。社会人になってみて世界視野で物事を考えられる人たちの志向の深さ・幅広さとの差を痛感している。早稲田は留学生も多いので、そうした環境も活かしてほしい。(若松さん)
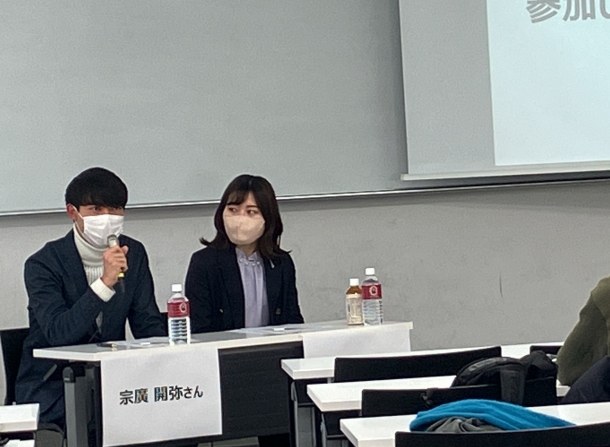
これからのキャリアプランなどを力強く話してくださる宗廣さん(左)と若松さん
第2部 交流会
交流会の前半は「地域WS」という共通点を持つ学生同士のつながりを広げることを目的に、同じ学年の学生同士のグループや参加地域・年度をシャッフルしてのグループなどに分かれての交流を行いました。就活に関する情報交換やワークショップ中の苦労話などに花が咲きました。
後半はトークセッション登壇者の方々にお一人ずつグループに分かれてもらい、参加学生は話を聞きたい方のところへ行ってより深い話を聞かせていただきました。大滝さん・長谷川さんには就活の具体的な進め方や学生生活の過ごし方などを質問する学生が多く見受けられた一方、宗廣さん・若松さんには4月から社会人になるにあたっての不安を吐露する学生もおり、思い思いの時間を過ごしました。
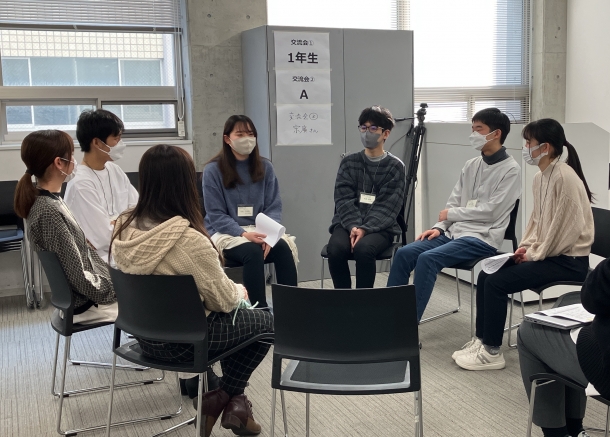
学年ごとのグループに分かれての交流会
イベントの閉会後も参加学生同士で談笑したり登壇者の方々へ熱心に質問したりと、この出会いが今後も学生たちのさまざまな成長や自己実現につながっていくことを期待させる光景が多く見られました。
参加学生の声
- 「他者視点で物事を考える力」は現場の人と意見を出し合う中で活きたなど、社会人になってからもワークショップで培ってきた力をそのまま活かすことができるのだという話が印象に残った。社会人として働く中で大学での経験を活かせるとわかり、社会人としてやっていく自信につなげられた。
- 自分と異なる地域、年度のWS参加者と深く話し合いができる機会を設けていただき、地域連携というテーマのもと、輪を広げることにつながった。また、自分自身が行った活動の振り返りとしても、素晴らしい機会になった。
- 地域連携WSに参加した学生の皆さんのその後の活躍を知り、私も頑張ろう!と元気をいただくことができました。学年が上がるごとに、他の学年や学部の皆さんと話す機会が減るので、今回このような場を設けてくださり大変ありがたく感じています。学びの多い、充実した時間となりました。