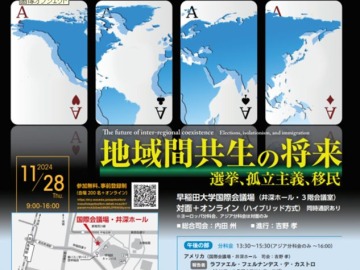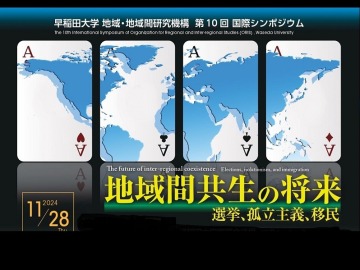【午後の部:アジア分科会】 戦後の米国・東アジアにおける移民/難民の諸問題
司会:梅森直之(早稲田大学政治経済学術院 教授)

アジア分科会は、報告者として東栄一郎教授(ペンシルベニア大学歴史学部)、鶴園裕基准教授(香川大学法学部)が登壇し、コメンテータの土佐弘之教授(ノートルダム清心女子大学国際文化学部)、篠田徹教授(早稲田大学社会科学総合学術院)とともに議論を深めていく構成だ。進行役の梅森直之教授(早稲田大学政治経済学術院)は冒頭で、「移民/難民の問題はグローバルな政治における中心的な問題点として浮上している。今日は、アメリカ、東アジアという2つの視点からこの問題を考え直してみたい」と論点を明らかにし、分科会をスタートした。
[報告1]東栄一郎/ペンシルベニア大学歴史学部 教授
「戦後日本における日系二世兵士の軍事神話の興隆:(反)人種主義と民主主義のシンボリズムと再軍備問題 」

東栄一郎(ペンシルベニア大学歴史学部 教授)
東教授は、これまであまり語られることがなかったアメリカ国籍を持つ日系二世語学兵に焦点を当て、占領下の日本との関わりを論じた。
東教授によれば、GHQは日系二世兵を日本人との媒介者として活用すると同時に、非白人の民主化の生きたシンボルとして敵国日本人に提示するというねらいがあったという。一方、日本国内では、日系二世の志願兵で結成された第442連隊の英雄譚を伝える映画や出版物などが制作されていた。そこには日系一世による日本式教育の結果、二世兵士がアメリカの民主化にいかに貢献したかが描かれ、日系二世を日本人化する修辞的操作が見られるようになる。さらに、基礎訓練を受ける二世兵士の世話を自主的に行ったことで知られるアメリカの実業家、アール・フィンチが来日したことにより、第442連隊の英雄神話はいっそう大衆の関心を集めることになる。それは、日本の再軍備問題に強く結びついていると東教授は指摘する。
「吉田茂首相ら要人との会談を果たしたフィンチの言動は、占領下の日本人に、日系二世兵の軍事的英雄伝を自らの誇るべき業績と認識する思考を呼び覚ましたのです」
このような動きは、軍隊に対する日本国民の態度を和らげ、日米両国の指導者層が目論む日本の再軍備という目的を後押しする結果につながったという。戦前の文化的、血統的本質主義といった価値観は、現代においても、日系二世の心情や行動が小説やテレビドラマの中で日本人として描かれるなど、今も連綿と受け継がれていると指摘して報告を結んだ。
[報告2]鶴園裕基/香川大学法学部 准教授
「戦後アジアの脱植民地化と『難民化』する中国系移動者:1950年代を中心に」

鶴園裕基(香川大学法学部 准教授)
続いて登壇した鶴園准教授は、中国系の移動者に着目し、制度史、国際関係史の観点から問題の所在を明らかにしていった。
この報告における中国系難民(Displaced Chinese)とは、戦後の戦乱や弾圧によって元の居住地から移動を余儀なくされ、居所を失った中国系の人々のことだ。冷戦期のアジアでは、戦後の脱植民地化で移動を強いられた人が大量に発生したものの、レッセフェール的な移動の自由がアジアから消滅した結果、中国系難民が出現。彼らは政治的なアレンジメントのもと「救済」の対象となるが、国際難民レジームはほぼ適用されず、難民問題として認知されない状況下で、その存在は政治的・社会的問題を引き起こしていく。
鶴園准教授は中国、イギリス、アメリカを例に中国系難民の問題を紐解いたうえで、「難民(refugee)というラベルは、反共主義的な宣伝価値が当該個人にあると認定し、その国際移動を許可する理由付けの一つでしかなかった」と指摘。実際に中国系難民の大多数は難民ラベルではなく、経済的価値、軍事的価値など国際移動を許可するに足る価値が認定されて再定住が図られたという。最後に鶴園准教授は、難民性をめぐるポリティックスについて「ある集団が難民でないなら、彼らを何と呼称し、その移動をどう正当化するのか。また、ある集団が難民であり得るなら、誰が難民として救済に値し、誰が値しないのか。この2点をめぐる政治的なかけひきか展開されていたのではないか」と考察。今後の研究では、中国系難民の難民性をめぐる具体的な問題を明らかにしていくことが課題だとして締めくくった。
[討論・質疑応答]土佐弘之/ノートルダム清心女子大学国際文化学部 教授
篠田徹/早稲田大学社会科学総合学術院 教授

土佐弘之(ノートルダム清心女子大学国際文化学部 教授)
2つの報告を受けて、討論者によりコメントおよび会場をふくめ質疑応答が行われた。
土佐教授は「第2次世界大戦とその後の帝国の崩壊、さらには国共内戦、朝鮮戦争といった諸戦争に伴う人の移動にからむレイシズムとそれに関する政治の動きなど、その複雑性を確認した」とコメント。「粗野なレイシズム」「洗練されたレイシズム」といった視点で現在の人種主義をどうとらえていくか、といった新たな議論を提起した。

篠田徹(早稲田大学社会科学総合学術院 教授)
篠田教授は、「レイスという視点を取り入れることで、日本史はもちろん戦前戦後のアジア史は、オセロの色ががらりと変わるように全く異なる視点が見えてくるのではないか」と感想を述べた。レイスとは、文化的あるいは生物学的出自を理由に集団を身分秩序の中に置くということだが、日系二世兵士も中国系難民の問題も、レイスの視点を基軸において概観することで新たな側面が見えてくるのではないかと指摘した。
続く質疑応答では、今回の報告では語られなかったジェンダーの視点など、新たな着眼点が加わり、その後の議論をさらに深めることとなった。