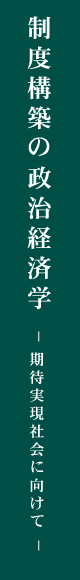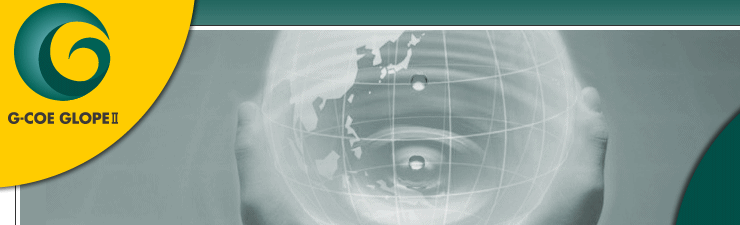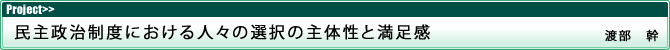
2008年度の活動報告
本研究は、選挙をはじめとする集団意思決定の場で、人々はどのような条件下において、自らの個人的選択に関して納得しやすいか検証するために社会科学実験を行った。われわれが注目したのは人々の選択の主体性である。選択に際して、必要な情報を取得するための情報源、選択肢の数など、選択における個人の自由意思が介在する程度が大きくなればなるほど、人々は結果の如何に関わらず自分の投票に納得し、集団的決定の結果を自らの選択の結果として受け入れるであると考えられる。
実験は2009 年2 月3 日(火)10:00〜17:15に43名の早稲田大学学部生を対象に行われた。そこでは、被験者たちは4つのグループにランダムに分けられた。一つのグループは4人の候補者で戦われる仮想的な選挙において、各候補者のマニフェストから閲覧する争点を自分で選んだ上、好きなだけ見ることができる(CCグループ)。二番目のグループはマニフェストから閲覧する争点がランダムに与えられた上、20秒間しかそれを見ることができない(TTグループ)。第三、第四のグループはそれぞれ第二のグループに与えられた処置のうちどちらか一方だけを与えられた(CTグループと、TCグループ)。これらの処置の後、投票する候補者を決めるわけだが、ここでポイントはマニフェストは全ての候補者について抽象的で一般的で同じ内容であるため(プレテストで確認済み)、投票選択の決め手とはならないということである。最後に被験者は各候補者のマニフェストを好きなだけ見ることができ、最初の投票決定を変えたいかどうか聞かれる。ここでの仮説は「情報がランダムに開示された上、開示時間が20 秒に制限されたグループの被験者(情報取得の自由度の少ない)は、マニフェストを全て開示された後、投票先を変えたいと思いやすい」というものである。
結果、情報がランダムに開示された上、開示時間が20 秒に制限されたグループの被験者は、他のグループの被験者より投票先を変える割合が高かった(45%)。しかし情報を選択した上、開示時間が任意のグループの被験者が最も投票先を変えにくかったかというとそうでもない(40%)。最も投票先を変えた被験者が少なかったのは、情報を選択した上、情報開示が20 秒に制限されたグループであった(18%)。来年度には、実験を精緻化させ、より重要な成果を出したい。