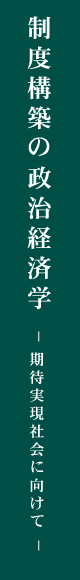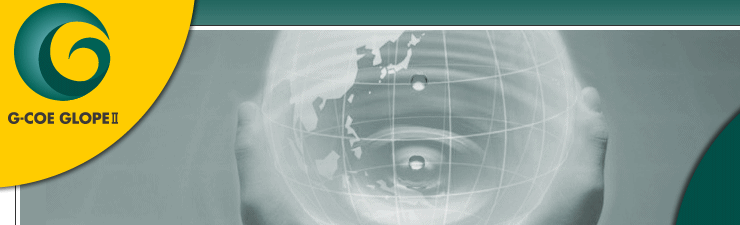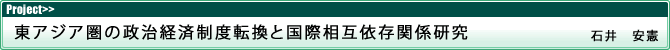
2010年度の活動報告
于洋が中心となって,中国から二人の研究者を招き,3月4日に日中経済セミナーを開催した.そこでは中国の年金債務と労働市場についての専門家から最近の研究が報告される一方,日本からは大学院生の孫豊葉が,中国に進出した日本企業での賃金支払いにおけるジェンダー格差について実証分析の結果を報告した.
大東一郎は,自由貿易地域における直接投資政策、発展途上国における環境保護政策、生産的消費仮説の下での経済成長理論に関する研究論文を、国内外の学会、コンファレンス等で発表した際に得たコメントを取り入れて改訂し、3点を完成させた。
佐藤綾野は,2010年3月のバングラデシュの現地調査にもとづいたマイクロファイナンスの研究(共同研究:米沢女子短期大学鈴木久美氏、早稲田大学経済学研究科松田慎一氏) ,情報フローを利用した東アジア内の資本移動の分析、情報フローに基づいて分析することを研究,Admati and Pfleiderer (1988)による株式市場におけるマイクロストラクチャー理論を為替市場に応用した研究を実施した(共同研究:早稲田大学秋葉弘哉教授、早稲田大学経済学研究科松田慎一氏、富山大学北村能寛氏).
木村公一朗は,先進国からの海外直接投資(FDI)が、途上国企業の成長にどのような影響をおよぼすのかについて、中国電子産業に属する38業種をケースに取り上げ実証分析した。具体的には、企業の成長を表す付加価値額やTFPを、各業種の固定資産に占める外資企業の比率に回帰することで、そのパラメータを計測した。その結果、各業種のパラメータが統計学的に有意な水準でプラスであればFDIは成長を促進し、マイナスであれば阻害し、有意な水準でなければゼロ効果であると判断した。また、業種の特徴を特定化するため、外資企業と中国企業のあいだの技術格差や、両者の相対的な経験値の差も計測した。
芹澤伸子は産業育成や工業化における日本の関与が近年著しいベトナムの対外直接投資政策及び対内直接投資受入れ態勢や諸規制の問題点について、現地調査を行った。これによって得た知見に基づき、政治経済制度の異なる当事国における社会・経済活動と貿易政策の問題を理論的に考察する.
小西秀樹は,中国のような地方財政制度をキャリア・コンサーン型の政策担当者によるヤードスティック競争ととらえたとき,伝統的な分権と集権の間の効率性優位論がどのように変わってくるのか,理論的に検討した.また田場弓子との共同論文では,自由貿易協定の形成について利益集団政治の視点から新たな理論モデルを開発した.田場弓子はこの成果を2月のTokyo-Irvineカンファレンス(カリフォルニア大学アーバイン校にて開催)で報告した.