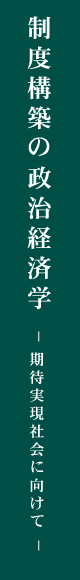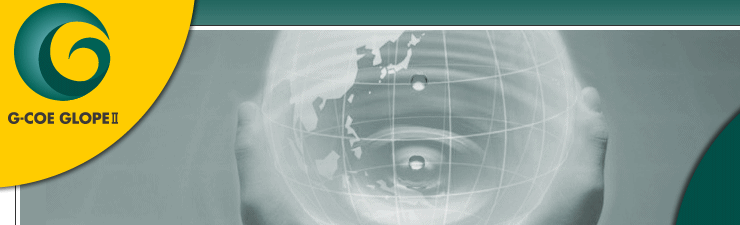2011年度の活動予定・活動目標
COE−GLOPEIIにおける研究・教育課題は、1)世界的にもその希少性ゆえに、効率的で持続可能な利用が必要とされており、それを確実なものにするための制度の構築が急務に求められている水資源を取り上げ、理論的側面と実証的側面の両面から分析を加えることと、2)農業・農村・社会開発の分野において、生産性の向上と効率性の改善を可能にするような制度・政策の確立に結びつく実証研究を行うことであります。さらに3)経済発展と環境保全の両立を目指す制度・政策の構築に関する政策的含意を導入できる実証分析を行います。実験経済学の手法も取り入れ、ミクロ・マクロの両面から検討を加えることに独自性があり、先進的な研究拠点となることを目指しています。
研究活動内容
(1) 上記の研究・教育課題1に関しては、まず日本の利根川の事例を用いて、水利権に関する制度・政策の変化や、中長期的な渇水などの問題回避のための水資源の首都圏から千葉・埼玉・茨城への移送が地域の経済・社会発展に与える影響を検証する手法の確立を図り、同時に有益な政策的含意の導入をする実証研究を実施します。さらに、水資源保全のための制度デザインに関連する実験経済学的手法をとった先行研究(Garrido, 2007)をベンチマークにして、これを深化させた実験をパイロット的に、ベトナム・ラオスのラボとフィールドで行い、結果の違い、質問表の内容を精査する作業を行い、論文の作成をします。
上記の研究課題2に関しては、水資源のベトナム・ラオスを中心とするメコンデルタの水資源利用に関するデータを使い、生産効率をtechnical efficiency, allocative efficiency, scale efficiencyに分解し、それぞれの貢献を利潤への貢献として貨幣単位で表すことを実証的に行い、学術論文の作成を行います。これまでのところ、directional distance functionを使った、生産効率をtechnical efficiency, allocative efficiency, scale efficiencyに分解し、それぞれの貢献を利潤への貢献として貨幣単位で表すことを実証的に行った研究や、シャドウプライスの算出や生産性の分解を伴った実証研究は、世界的に行われておらず、先進的な研究を実施することになります。
(ベトナムにおいては、経済の自由化が進む一方で、社会主義の政治体制を維持しており、公的な部門の果たす役割が周辺国に比べてまだ大きいが、水資源の維持・管理をするという側面からパフォーマンスをみると、周辺国に比べても遜色が無いほど効率的・効率的になっています。水資源管理の分野においても、世界的な規模で民営化、水資源取引市場の開発・発展が進んできている中で、なぜ民営化しなくても、水資源の維持・管理がうまくいくのか、適切な説明ができるような研究体制の確立を院生協力者の江良を中心に図りたいと思っています。さらに、同じメコン川流域に位置し、水資源を管理する制度や政策が、ベトナムほど発達していないラオスの事例に分析の対象を拡大して、比較研究を実施し、より一般化した政策的含意の導入をはかりたいと考えています。ラオスは、ベトナムより水資源を含む生産投入財市場が政府により管理されています。ラオスとベトナムの水資源管理に関するアプローチは違い、その政策・制度の違いが生産効率や生産性の推移に及ぼす影響について検討をします。)
第3番目の研究課題に関しては、directional distance functionを使いノンパラメトリックな手法で実証研究を実施し、研究結果を国際的な雑誌に投稿します。
(2)学会・ワークショップ・シンポジウム・セミナーへの参加と報告内容
GLOPEIIのワークショップとして、5月以降1月まで8月を除き月一回FRPIワークショップを実施します。7月には、研究・教育課題1の分野の専門家であるSmith教授が来日する機会をとらえて「水資源を中長期的にわたり有効利用するための政策・制度分析」に関するワークショップを開く予定です。その他の講師候補は、進化ゲームを中国における水管理制度の研究に応用している伊藤順一農林水産政策研究所主席研究員などを考えています。上記(2)の院生の江良を中心とする研究プロジェクトの内容・成果に関しては、火曜セミナーもしくは、全体ワークショップで報告します。
教育活動内容
(1) 大学院生への指導内容
大学院生が院生協力者として、直接プロジェクトに参加することにより、データ収集方法、実験の実施方法、研究手法、国際的な雑誌に投稿する学術論文の作成作業のノウハウの伝授が可能になります。また大学院社会科学研究科の授業、研究指導、学内各種ワークショップ、上記に記述した本担当者が企画・実施したGLOPEIIワークショップ、院生特別講義を通じて、広く早稲田大学の大学院生に対して研究テーマの提供、分析手法の技術移転を行います。