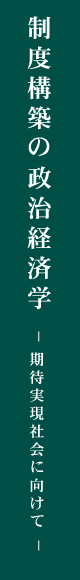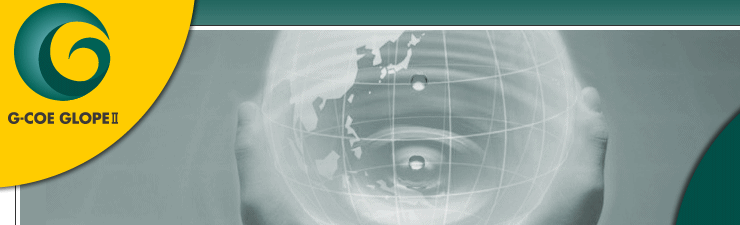2010年度の活動報告
1)上記の研究・教育課題1に関しては、まず日本の利根川の事例を用いて、水利権に関する制度・政策の変化や、中長期的な渇水などの問題回避のための水資源の首都圏から千葉・埼玉・茨城への移送が地域の経済・社会発展に与える影響を検証する手法の確立を図り、同時に有益な政策的含意の導入をする実証研究を実施しました。そこでは、昨年度構築したデータベースを用いて、政策シュミレーション分析をおこなうために必要となる生産関係を示す係数を推計しました。水資源を生産関数に含めた研究はこれまでのところ日本農業に関しては少なく、水資源のシャドウプライスも求めることができました。
上記の研究課題2に関しては、水資源のベトナム・ラオスを中心とするメコンデルタの水資源利用に関するデータを使い、生産効率をtechnical efficiency, allocative efficiency, scale efficiencyに分解し、それぞれの貢献を利潤への貢献として貨幣単位で表すことを実証的に行い、学術論文の作成を行います。これまでのところ、directional distance functionを使った、生産効率をtechnical efficiency, allocative efficiency, scale efficiencyに分解し、それぞれの貢献を利潤への貢献として貨幣単位で表すことを実証的に行った研究や、シャドウプライスの算出や生産性の分解を伴った実証研究は、世界的に行われておらず、先進的な研究を実施しました。その開発した分析手法を議論した論文は、Journal of Agricultural Economics(Agricultural Economic Societyの学術雑誌)に投稿し、アクセプとされ、2011年7月に掲載されることになりました。
ベトナムにおいては、経済の自由化が進む一方で、社会主義の政治体制を維持しており、公的な部門の果たす役割が周辺国に比べてまだ大きいが、水資源の維持・管理をするという側面からパフォーマンスをみると、周辺国に比べても遜色が無いほど効率的・効率的になっています。水資源管理の分野においても、世界的な規模で民営化、水資源取引市場の開発・発展が進んできている中で、なぜ民営化しなくても、水資源の維持・管理がうまくいくのか、適切な説明ができるような研究体制の確立を院生協力者の江良を中心に図りました。さらに、同じメコン川流域に位置し、水資源を管理する制度や政策が、ベトナムほど発達していないラオスの事例に分析の対象を拡大して、比較研究を実施し、より一般化した政策的含意の導入をはかりました。GLOPEIIの支援で個票データの収集が可能となりました。そして、江良は2010年6月に日米研究機構とGLOPEIIが共催する国際会議学生セミナーで、ベトナムで収集したデータの分析結果を報告し、日米研究機構のディスカッションペーパーとしてその内容を公表しました。
第3番目の研究課題に関しては、directional distance functionを使いノンパラメトリックな手法で実証研究を実施しました。
2)学会・ワークショップ・シンポジウム・セミナーへの参加と報告内容
6月には、上記のように江良が研究課題2について、報告をしました。また、同じく6月に弦間が韓国農業経済学会の日韓中シンポジウムで、研究課題2に関する報告をしました。9月には米国のMicroeconomics of Competitivenessに関する専門家のBochniarz教授が客員教授として来日する機会を使い、教育・研究課題3に関係して「エネルギーの安全保障と食料の安全保障の共存と気候変動問題に対するコミュニティレベルにおける取り組みの日米比較研究」に関する講演会を日米研究機構と産業経営研究所の共催で実施しました。さらに、2月にはUSJI(米国ワシントンDC)において、Bochniarz教授との共同研究内容を報告しました。
3) 該当期間の研究成果(中間結果を含む)
研究課題1に関しては、政策分析を実施する一般均衡・動学成長モデルを使う政策分析の枠組みを使う上で必要となる係数の独自の計測ができました。
研究課題2に関しては、ベトナム以外にも、ラオスを含めより包括的なメコンデルタの水資源利用に関するデータベースの構築と分析が完了しました。