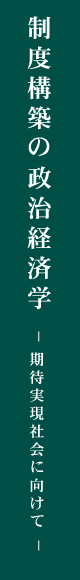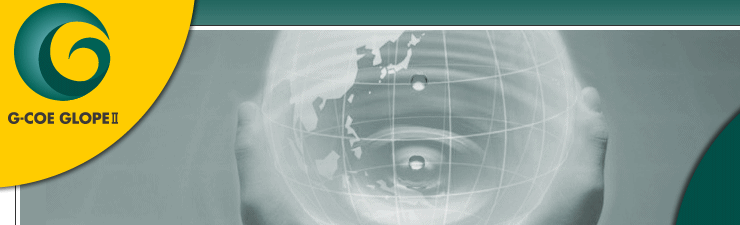2011年度の活動報告
(1)絶対的基準と相対的基準による罰則制度の比較(参加者 船木、上條、竹内あい、二本杉)
社会的ジレンマ状況において協力行動を導くには、懲罰が効果的なことが知られている。本研究では中央集権的罰則制度において、罰則適用が絶対的基準(ある閾値以下の全員が罰せられる)に基づくか、相対的基準(ある閾値以下でかつ、最も貢献度の少ない者が罰せられる)に基づくか、により人々の行動・協力度がどのように変化するかの大規模な実験を行った。その結果と分析に基づき論文を完成させ、国際学術誌に投稿した。なお、この内容は内外の学会で報告されている。この実験の分析結果を説明するためには、人々の他者に対する「ねたみ」が重要な要因である可能性が発見されたので、その可能性を検討するために、新たな追加実験を行った。それは、実験参加者への他者の結果に関する期ごとに得られる情報を制限する実験を行うことである。この情報制限から他者へのねたみが抑制され、均衡からの逸脱行動の減少が観察された。現在、この結果に関しても論文を作成している。これらの内容も内外の学会で報告されている。
(2)制度導入の手続き的公平性による影響(参加者 船木、上條、竹内あい)
本研究は21COE-GLOPE の研究の直接的な発展研究である。社会的ジレンマ状況に分権的懲罰あるいは報酬制度を導入することにより、協力度が変化することはすでに多くの先行研究がある。21COE-GLOPE における実験研究においてこの分権的制度決定のタイミングおよび選択の手続きの公平性(多数決か独裁か)についていくつかの興味深い実験結果を見ることができたが、最終的な結論は得られていない。その研究を続行するための実験デザインについて何度か再検討のためのミーティングを行い議論を続けている。2012年度中に再度の実験を行い、最終的な結論を論文としてまとめる。
(3)混雑状況緩和に関する制度選択(参加者 船木、Fortat、Veszteg)
様々な混雑状況において、皆が行列を作り秩序を保って行動する場合と我先に駆け込み混沌となる状況が生ずることがある。この状況を鹿狩りゲームのモデルを用いて分析し、そこにおいて、様々な制度(罰則、示唆、顔写真の提示など)を導入してその効果を比較するための実験を行った。さらに、フランスにおいても同様の実験を実施し、その比較を行った。これとは別に、エネルギーの利用に関する混雑状況を分析するためのゲームモデルを構築し、実験を行った。これに関してもさまざまな制度の効果を比較した。論文の作成を進め、本年度中に完成させ、国際学術誌に投稿する予定である。さらに、世論調査においても、同様においても関連する設問を設定し、同時に分析を進めている。
(4)アイトラッカーによる分析(参加者 船木、宇都、日野)
アイトラッカーを用いた様々な実験を計画し、アイトラッカーの利用講習会や、勉強会を行った。
上記に関連して定期的にセミナーを、現代政治経済研究所 船木部会(略称 木曜セミナー)・他のプロジェクトと共催で合計12回行った。なお、本年度は東日本震災の影響により、海外からの研究者招聘は行わなかった。ただし、慶応大学の大垣教授の招聘によりノッチンガム大学のゲヒター教授が早稲田大学を訪問し、両教授と共に(2)に関連する実験を行った。