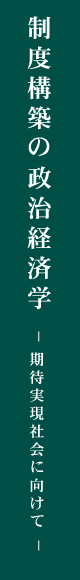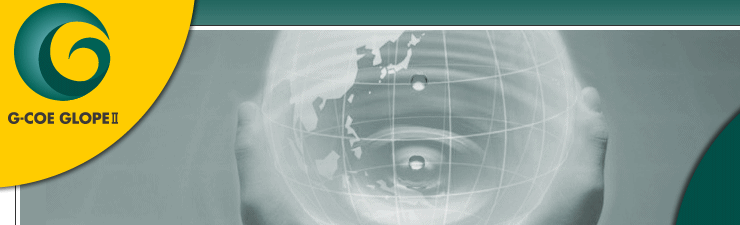2009年度の活動報告
(1)ワークショップ・研究会・学会による国内外研究者との交流
今年度は主に2件の国際ワークショップを実施したが、その軸となったのはDr.Kellam Marisa (Texas A&M University)による連続講義(2009年6月19日、26日、7月3日)である。ここでは講演者自身の研究報告と議論を通じた交流だけでなく、大学院生に対する具体的指導も行われた。12月18日にはGLOPEII訪問研究員であるDr. Curini Luigi氏(The University of Millan)のワークショップも実施した。
また海外での研究交流や研究成果の発信、あるいは国際的発信能力の向上も積極的に推進した。久保は2009年9月に欧州政治研究連合(ECPR)の研究大会で分離主義運動について旧ユーゴ地域の事例を中心に報告を行い、2009年12月の国際会議では少数民族の武装蜂起に対する国家当局の対応の規定要因についてセルビアとマケドニアの比較分析を行った。関はGLOPEII第1回国際シンポジウムでの報告内容をもとに製作された著作への寄稿を果たした。中井と東島は政治学最大規模学会の一つであるIPSA(2009年7月、チリ)にて研究報告を実施したが、この際東島はGLOPEIIの校正支援をうけ、中井もCOE助手研究費にて出張した。尾崎も他プロジェクトを通じてだがCOE予算の支援をうけてSPSA(2010年1月、米国)にて研究報告を実施し、津田はロシア語による学会報告を行った。なお院生協力者の東島と関は2009年秋より米国の大学に留学している。2010年3月にGLOPE支援によって行われるアカデミック英語能力向上集中講座にも複数の大学院生が積極的に参加し国際的発信能力を向上させた。
(2)大学院生間の輪読会・研究会
助手や大学院生らが自発的にかつ目的意識をもって行う勉強会・研究会も行われた。前年度に引き続き質的研究がもつ方法論的諸相をを検討するため、Alexander L. George and Andrew Bennett, Case studies and theory development in the social sciences (Cambridge: MIT Press, 2005)をテキストとした輪読会を継続して実施し、前期期間中にこれを読了した。後期にはゲーム理論と事例研究を接続する試み(政治学におけるAnalytic Narrative, 経済学におけるComparative and Historical Institutional Analysis)にかかわる論文(Buthe 2002 APSR, Greif and Laitin 2004 APSR)を読み合わせた。
さらに昨年度に続き2回目となる第2回比較政治経済分科会を2010年2月27日に実施する。筑波大学とJSPS特別研究員(PD)の若手研究者(浅野康子氏、渡辺敦子氏)を招聘し、本プロジェクト協力者2名(川橋郁子、尾崎敦司)を含めた研究報告と交流が行われる。コメンテーターには立教大学の小川有美教授など学外の研究者を招く予定であり、高い水準の議論が活発に交わされるであろう。
(3)GLOPE-II活動への積極的参与
本プロジェクトメンバー院生協力者はGLOPEIIの研究活動に積極的にかかわっている。COE助手である中井は10月のランチタイムセミナー・12月の若手国際シンポジウムで報告を行った。尾崎もまた12月の若手国際シンポジウムと、2月の第2回比較政治経済分科会での報告を行う。同分科会では川橋も研究報告を実施し、これら3名は火曜セミナー(政治経済合同研究グループ)へも参加している(中井・川橋は国際政治経済モデル班、尾崎は実験・世論調査・統計分析班)。東島は6月にランチタイムセミナーにて、津田は12月の実務者セミナーにてそれぞれ報告を行った。