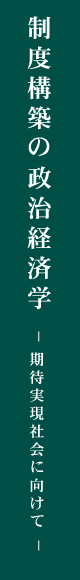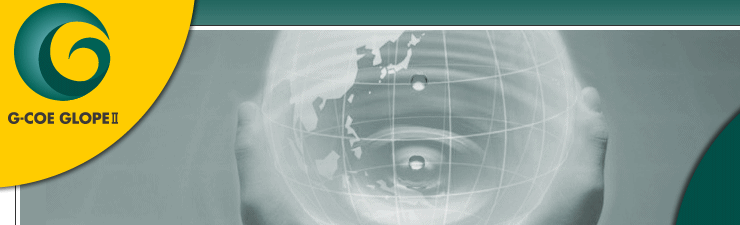2008年度の活動報告
本年度は、研究メンバーを中心とする研究会を定期的に開催し、研究活動の活発化をはかった。その一環として、大学院生を中心に、Alexander L. George and Andrew Bennett, Case studies and theory development in the social sciences (Cambridge: MIT Press, 2005)をテキストとした方法論研究会が2008年12月から2009年1月まで3回にかけて行われ、メンバー間の方法論の共有と理解の深化を目指した。また本プロジェクトは、GLOPEで大学院生によって組織されていた比較政治分科会を継承し、GLOPEIIにおいても比較政治経済分科会を開催する。第1回比較政治経済分科会は2009年2月28日に行われ、北海道大学と東京大学から若手研究者を招聘し、プロジェクトメンバーの大学院生2名(東島雅昌、中井遼)を含めた4名による研究報告が行われる。
本プロジェクトのもう一つの柱として進められたのが国内外の研究者との研究交流である。今年度、本プロジェクトの主催によってすでに2回の国際ワークショップが開催され、3月に3回目のワークショップが開催される予定である。WSに参加し研究報告を行った研究者の出身国は米国、英国、ルーマニア、ウクライナと多岐にわたり、比較政治学、旧共産主義圏の政治研究において最先端の研究を行う著名研究者や気鋭の若手研究者である。ワークショップの参加者氏名と所属大学は下記の通りである。
Richard Sakwa (University of Kent at Canterbury); Peter Rutland (Wesleyan University); Martin Potucek (Charles University); Rasma Karklins (University of Illinois at Chicago); Valentin Yakushik (Kyivo-Mohyla Academy University); Anatoliy Kruglashov (Chernivtsi National University); Dan Dungaciu (Bucharest University)
また同じく海外の研究者との研究交流、ならびに研究成果の発信を目的とし、研究協力者の久保は2009年2月13日〜17日まで米国・ニューヨークに滞在し、国際研究学会(ISN)の第50回年次研究大会において、旧ユーゴスラビア地域の民主化と民族問題の相互作用に関する研究発表を行った。この研究発表は東欧、バルカン、ロシア、環黒海地域の体制変動後の制度構築、アイデンティティの変容などを比較分析することをめざしたパネルの一環であり、研究発表を通じ、研究成果を国際的に発信し、米国、ギリシャ、ブルガリアなどの研究者と意見交換をすることができ、大変有意義なものとなった。また中井は2009年1月に京都大学を訪問し、バルト3国の政党システムに関する研究報告を行った。この研究会は、北海道大学、名古屋大学、京都大学などの旧共産主義諸国の選挙・政党システムの専門家によって構成されるものであり、研究報告を通じて旧共産主義諸国の政党システムに関する比較分析に大いに貢献した。
本プロジェクトメンバーの大学院生はその他、GLOPEIIの活動に積極的に参加している。関は2009年1月の国際シンポジウムにおいて研究報告を行った。関、尾崎は火曜セミナーにおいて文献の発表を担当した。中井はランチタイムセミナーにおいて研究報告を行った。また本プロジェクトメンバーの大部分は、他のプロジェクトの下で行われているゲーム理論やシミュレーション分析手法などのワークショップに積極的に参加し、あらたな研究手法を習得しようと試みており、そうした努力は研究成果において形となって現れつつある。