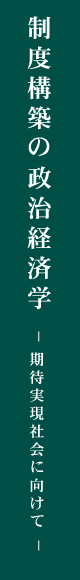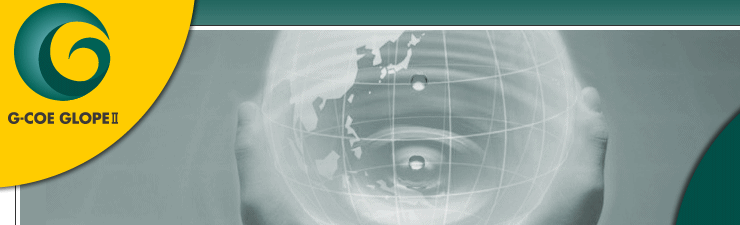活動予定・研究目標
政治理論(政治哲学)と厚生経済学(社会的選択理論)の実質的な統合は、政治理論から見れば形式的でかつ功利主義の影響を色濃く残す社会的選択理論では扱いうる領域が部分的でしかも極めて小さく、有効なアプローチとは思えないのに対し、社会的選択理論からすれば政治社会を見るための構想・視点としての政治理論は論理的厳密性に欠け制度設計には役立たないと思われるので、きわめて困難な作業である。高度な理論レベルで協力関係を築こうとしても、両者の方法論的対立が浮き彫りにされるだけで、協力・協調の可能性を見つけることは難しい。そこで、具体的な問題を例にとり、政治理論と厚生経済学(社会的選択理論)がその問題に対しどのような答えを与えるのかを、セミナーなどを定期的に開いて繰り返し提示しあうという戦略をとる。そして、それぞれがどこに比較優位を持ち、どこに協調・協力の可能性を見出すことができるのかを繰り返し検討する。
では、このような作業をどの領域で行うべきか。GCOEの申請書には、具体的な問題として、年金、問題、環境問題、地域紛争の問題が取り上げられていた。ここでは、少し広く捉えて社会保障制度の再構築をテーマに具体的な制度設計に向けて、政治哲学と厚生経済学がどのような答えを用意しうるかを検討していく。私と区別された公の原理としての公共性は、各人が自らの私的善を追求するための前提条件を人々に等しく整備・保障する社会的次元に関わる原理、具体的には生活保障としての社会保障全般を制御する原理である。通常の社会保障が市場競争の敗者を事後的に救済し新たな競争への再挑戦の機会を確保することと見做すのに対し、われわれは社会保障を、事前の資源の再配分を通じて「生の見通し」の改善を図り自律的生活を促進していくためのシステムと見做す。その中には通常の保障はすべて含まれるが、特に労働ないし雇用保障は重要な位置を占めることになる。
このような議論の過程で政治哲学と厚生経済学が問題意識を共有し、それぞれの提案する分析枠組みやそこから導かれる具体的な制度設計などの政策提言を異なる観点から繰り返し検討することで、新たな協力関係を築くことができよう。具体的な作業は政治哲学と経済学の協力によって完成したMurphy and Nagel (2002), "The Myth of the Ownership," Oxford. に倣い、それぞれの立場からの問題提起を広く集め、それぞれの立場から解答を与え、別の立場からのコメントを受け、応答し改善するという作業を繰り返す。