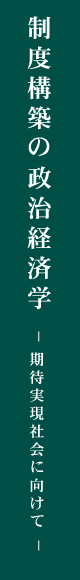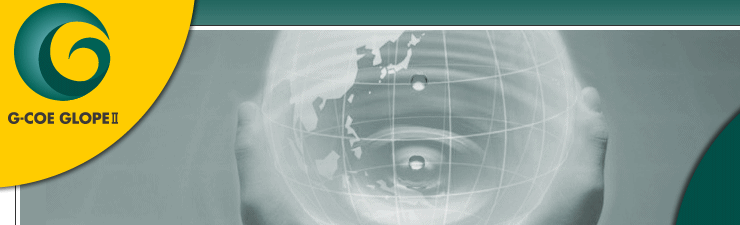活動予定・研究目標
経済学において、「期待」は、経済主体が様々な事象に対して抱く主観的確率として表現されている。たとえば、他人の行動に対する期待は、その他人がとりうる行動を確率的に表現することでモデル化される。また、人は、他人が自分に対して抱く期待を推測しながら行動するが、そうした状況も同様に主観的確率でモデル化されてきた。一方、経済学における「制度」は、狭義には、社会のルール=条件として外的に与えられたものであるのに対し、広義には、個々人の相互作用の結果=均衡として実現したものである。本プロジェクトでは、制度を所与とした人々が「期待」をどのように形成し、行動するのかに分析の焦点をあてる。
具体的な分析対象として、オークションを所与の制度として選ぶ。その理由として第一に、経済の根底をなす財の生産→交換→消費の流れにおいて、オークションが効率性をもたらす代表的な制度だからである。公共事業における事業者の選定や,米国における無線周波数の利用権の配分など,現実にもこれを目的とする制度を設計することは多く,オークション理論の成果が活用されている。第二に、オークション制度を狭義にとらえても、その制度と期待の相互作用を分析することには高い政策応用性があるからである。市場制度のなかから、オークション制度を切り出して分析の俎上にのせ、市場制度を現実に即した形で「視覚化」することを試みる。オークション制度についての研究は、理論的にも実証的にも、また実験研究も蓄積がある。本プロジェクトはそれらを推し進めるために、新しいオークション形態を研究テーマとしている。すなわち、理論的に結果が予想できないものや、制度と期待形成の関係が未知のものを分析する。こうした共通認識のもと、各研究協力者は連携しつつ、下記のサブテーマの理論、実験、シミュレーション研究を行う。
(1) 組み合わせオークションの研究:複数財オークションの経済実験を行い、オークション入札者の行動を観察し、その成果を制度設計に応用することを目的とする。組み合わせオークションが、通常の1財オークションと異なる点として、i) 結果を予測する際に均衡概念による理論的な考察が難しいこと、ii) 複数財が同時に取引されるため入札者間で談合が成立しやすいこと、そして iii)組み合わせの数が取引される財に対して指数関数的に増加するので、入札者が最適な入札を見出すことが困難であるということが挙げられる。本研究で、経済実験によって統制された条件下で人々の期待形成とその相互作用を観察したい。複数財のオークションの研究としてはKelso and Crawford (1982), Gul and Stacchetti (2000), Milgrom (2000), and Ausubel (2006) Maskin (2005)などが挙げられるが、さらに、楊再福が最近考案した上記の欠点を補う新しいメカニズムについても実験を行う。
(2) スポンサーリンクオークションの研究:これはweb上の検索エンジンに入力された検索ワードに関連したテキスト広告を,検索結果とともに掲載し利用者に提示する広告配信手法のことであり,オークション方式によって売買されている。広告主は広告を表示させたいキーワードを指定した上でクリック単価を入札し,この入札額に従って,掲載順位,広告料が決定するのが特徴である。現在,大手検索エンジンは一般化セカンドプライスオークションを採用している。Edelman et al. (2007) ではこれとVCG(Vickrey-Clarke-Groves)メカニズムについて,入札の安定性,収益性の理論的な比較をおこなっており, GSPの収益性の高さを評価している。しかし現実の市場において,検索エンジン企業側の期待した入札行動がとられ,理論上の均衡状態が達成されているかどうかは定かではない。そこで本研究では,実験を行うことで,これらを比較検討する。さらに,この観察結果から,GSPにおける入札者の行動基準を,シミュレーションを通じて分析する。これらの結果から入札者の行動およびかれらの期待形成プロセスを明らかしたい。
(3)参加業者が共謀し落札価格を操作しすると,制度の帰結は一般に非効率な分配となる。この研究では、参加者たちがどのように他の参加者の行動を予想し,共謀を形成してその利益を分配するかという点について理論的考察を行う。具体的には,協力ゲームのひとつのクラスであるring gameによって表現される,買い手の共謀を許したオークションモデルにおいて,オークションから得られる余剰の分配方法に関する理論的分析を行う。さらに(1)(2)の研究の背後の理論分析も行う。