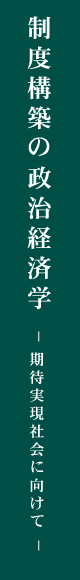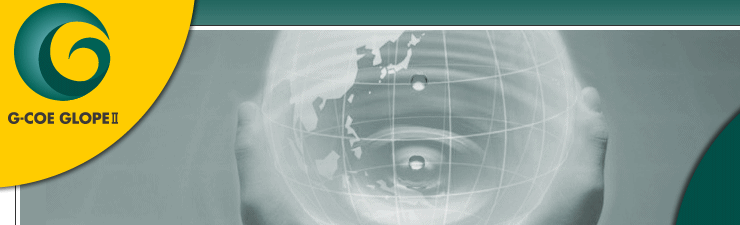2008年度の活動予定・活動目標
期待実現社会の構築に不可欠な理念として、諸制度の持続可能性とその下で人々が獲得する福祉の持続可能性を挙げることができる。持続可能性とは世代間衡平性が維持される経路の性質であるとされるものの、その内容に関しては研究者の間でも合意が成立していない。福祉の概念も同様である。したがって、福祉の概念を拡充し、世代間衡平性を内包する持続可能な福祉概念を確立すること、その福祉概念を用いてさまざまな政治経済環境における発展経路を導くことが課題となろう。さらに、資源・環境の持つ持続可能性への制約を明確に組み込んだ動学分析も重要な課題となる。
このような持続可能な制度と福祉の動学的研究は、資源・環境の使用と管理に関する制度的安定性・持続可能性を分析するもので、次のようないくつかのテーマを含む。第1に、人々が資源・特に共有資源を共同で使用・維持・管理しなければならない動学的な状況では、誰がどれだけ資源を使用し利益を得るか、各人は資源・環境の維持・管理のための費用をどれだけ負担するか、といった集団的意思決定問題を解決しなければならない。天然資源の費消とそれに基づく環境破壊などの問題を回避するためには、いかなるルールを設定しどのような協力関係を築くか、それによって生じる余剰をいかなる衡平原則に基づいて分配するかを決定しなければならない。第2に、特定の政治経済環境を前提せず、動学的な効用・消費・貯蓄の諸経路を比較するさまざまな基準を公理的に特徴づけ、基準の優劣を検討することも必要である。この領域では、近年社会的選択理論において盛んに議論されている世代間衡平性の基準形成可能性等の問題が参照されなければならない。第3に、個別の政治経済環境を前提として、そこでの動的資源配分問題の解として導かれた帰結を社会的厚生や世代間衡平性の観点から特徴づけることが必要である。たとえば、市場システムがもたらす動学的経路の規範的特徴づけという、最適成長論がこれまで取り上げてきた問題の再検討があるし、経済政策の変更によって新たに出現しうる経路の評価、それに基づく政策の評価という課題がある。第4に、シミュレーションの利用が考えられる。たとえば、ロールズのマキシミン原理に適合的な動学的経路を解析的に導出することが困難な場合には、スーパーコンピュータを用いた数値解析によるシミュレーションが近似解を見つけるための有益な方法となるであろう。