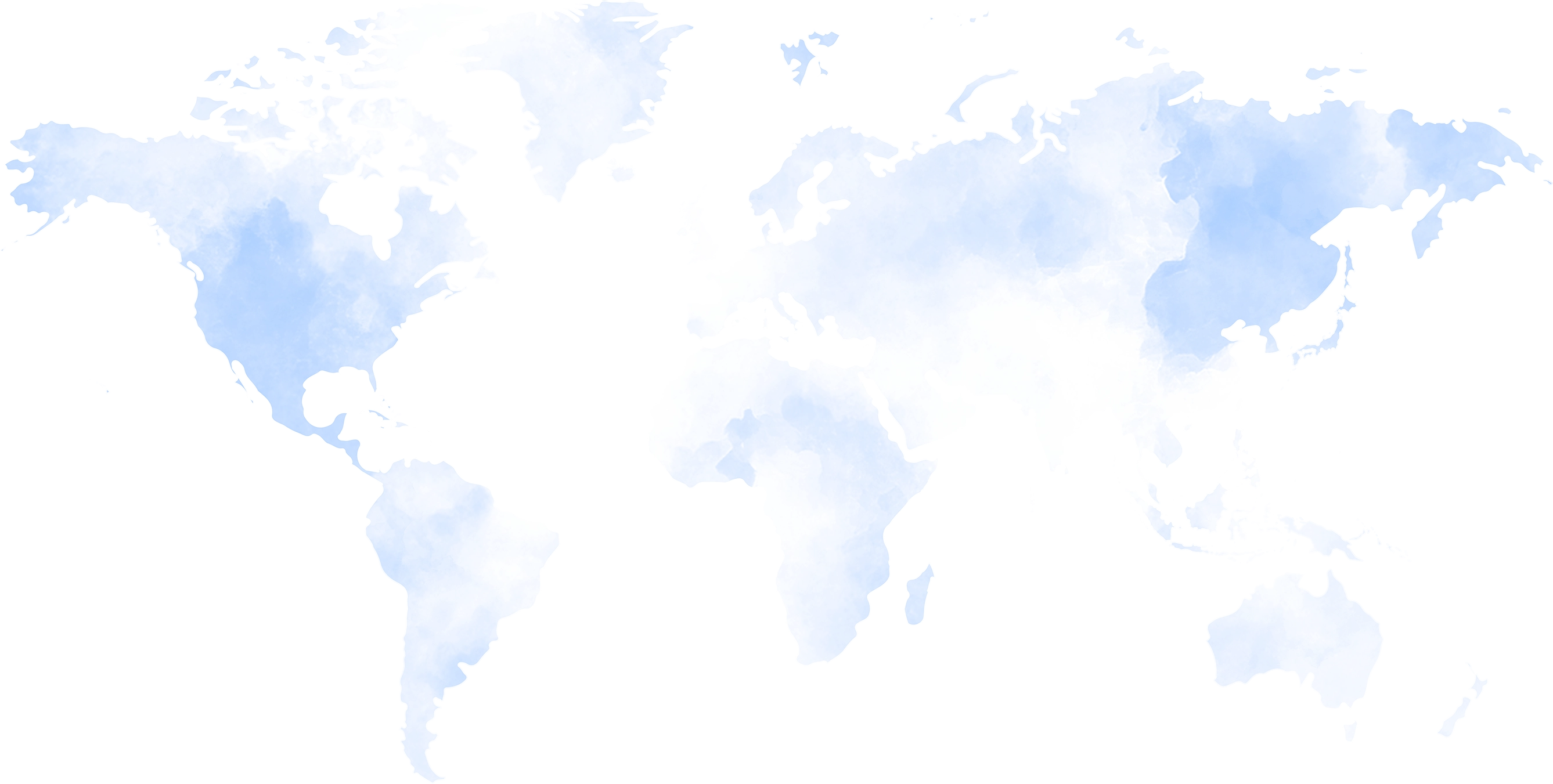
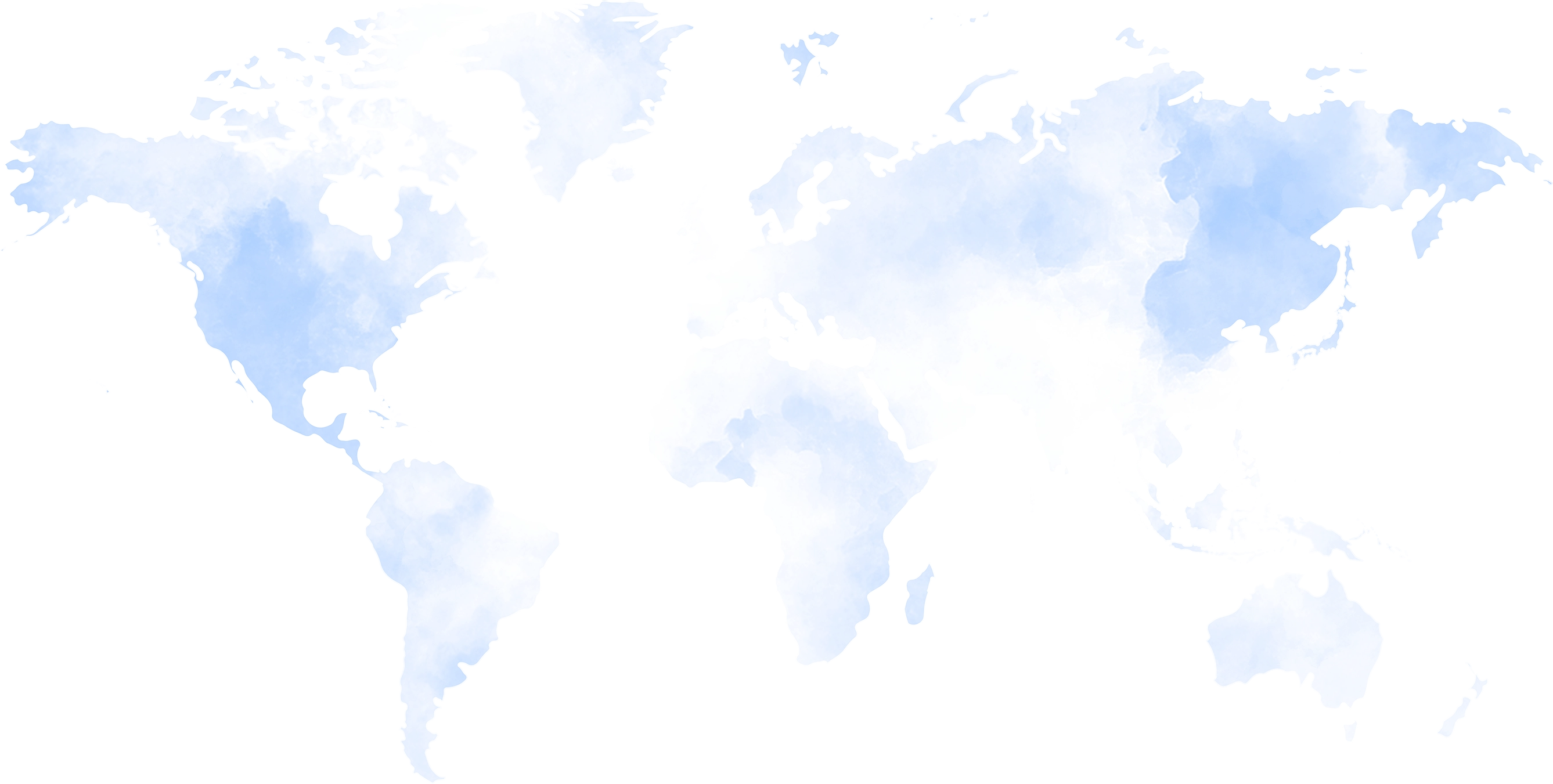
早稲田びと

紛争の傷跡が残るボスニア・ヘルツェゴビナの地で、サッカーを通じて平和の種を蒔く
SHOHEI HIGUCHI
樋口 昌平 氏
2001年人間科学部スポーツ科学科卒
Jリーグ等に勤務後、日本サッカー協会で宮本恒靖会長のアシスタントを務める。併せてボスニア・ヘルツェゴビナで民族融和を目指すスポーツアカデミー「マリモスト」を運営。
WASEDA DNA WASEDA DNA WASEDA DNA WASEDA DNA
大手民放テレビ局、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)を経て日本サッカー協会(JFA)へ。早稲田大学人間科学部スポーツ科学科を卒業後、独自のキャリアを歩んでいる樋口昌平さん。現在はJFAで宮本恒靖会長をサポートしながら、民族の垣根を越えたスポーツアカデミー「Little Bridge」の運営に取り組んでいます。樋口さんの活動は、大隈重信の志「一身一家一国の為のみならず、進んで世界に貢献する抱負が無ければならぬ」を、スポーツというフィールドで体現しています。

オリンピックへの憧れが導いた早稲田への道
「あんな風に速く走れるようになりたい」。小学4年生の時にテレビで観た1988年ソウルオリンピックが、樋口昌平さんがスポーツを始めるきっかけになりました。当時世界中で話題になったアメリカのカール・ルイスとカナダのベン・ジョンソンの世界最速決戦に心を奪われ、小学校5年生から陸上競技の道へ。高校3年の進路選択の頃には「スポーツの仕事に携わりたい」と考えるようになっていました。
早稲田大学人間科学部スポーツ科学科(現在のスポーツ科学部)への進学は、その夢の実現への第一歩でした。大学入学後は陸上競技とは区切りをつけ、自身にとって新たなスポーツであるサッカーと関わるようになります。

「自分がいるべき場所なのだろうか?」新卒入社したテレビ局での挫折
大学3年の終わりがけに「自分が制作したスポーツ中継を世界中の人に届けて、子どもたちがスポーツを始めるきっかけを作りたい」という思いで在京民放テレビ局の採用試験を受け、内定を獲得。しかし、入社して配属されたのは希望していたスポーツ局ではなく、営業局。そんな樋口さんに転機が訪れたのは入社2年目の2002年6月のことでした。
日本と韓国で共催となったFIFAワールドカップ日韓大会。6月9日に横浜国際総合競技場で開催された予選グループの第2戦で日本代表がロシア代表を破り、W杯初勝利を挙げるという歴史的な日になりました。実は、この試合の中継制作を担当していたのが、樋口さんが所属していたテレビ局。
しかし、樋口さんはその歴史的な日に、スタジアムではなく営業として映画イベントの会場にいたのでした。もともと「この仕事は本当に自分のやりたかったことだろうか?」という疑問を抱いていた樋口さんでしたが、イベント終了後に自宅のテレビで日本代表の歴史的な勝利を見て大学院の受験を決意。会社に退職を申し出ます。
テレビ局退職後、無事に大学院の受験を通過。4月の入学までに時間のあった樋口さんに早稲田大学の先輩から「時間があるんだったらJリーグでバイトしない?」というオファーが舞い込み、二つ返事で快諾。当初は大学院に入学するまでの短期アルバイトの予定でしたが、約束の期間がすぎると他部署からも声がかかり、その部署でのアルバイトが終わると、また次の部署から声がかかり、そうしているうちにJリーグの職員へのオファーが届きます。「スポーツの感動を人に届ける仕事がしたい」。かねてからの願いが叶った瞬間でした。
キャリアを決定づけた
元サッカー日本代表・宮本恒靖氏との出会い
2013年、現在の活動へとつながる転機が訪れます。それが、元サッカー日本代表であり、現・JFA会長である宮本恒靖氏との出会いでした。家族の事情で、地元である福岡での転職を検討していた樋口さんの元へ、宮本氏のマネジメント会社からオファーが届いたのです。一旦は事情を伝え断りを入れた樋口さんでしたが、当時は珍しかったフルリモートでの勤務で良いからやってほしいというオファーを受けることにしました。それ以降、現役引退後に新たなキャリアを歩み始めた宮本氏を裏からサポートし続けます。
所属組織が変わった今も、その関係は続いています。現在、JFAに所属する樋口さんは宮本会長のアシスタントとして、多岐にわたる業務をサポートしています。全国を飛び回る忙しい日々のモチベーションとなっているのは、スポーツで世の中に貢献したいという、変わらない想い。
「通勤の電車でサッカー日本代表やJリーグクラブのグッズを身につけている方や、週末にスタジアムに向かうユニフォーム姿の家族を見ると、いまだに感動しています。一過性のブームではなく、サッカーが文化として根付いてきているんだなと実感します」。
紛争の記憶が残るボスニアで立ち上がった
「Mali Most」プロジェクト
JFAの仕事と並行し、樋口さんはスポーツを通じた国際貢献活動を行うNPO法人「Little Bridge」の代表理事としても活動しています。きっかけは宮本氏がFIFAマスター(国際サッカー連盟が主宰する修士課程プログラム)在学中に行なった「ボスニア・ヘルツェゴビナのモスタルに、民族融和と多民族共栄に寄与するような子供向けのスポーツアカデミーを設立することは可能か」という共同研究でした。2013年8月、その研究が新聞で紹介されると、樋口さんのもとにJリーグ時代の同僚を通じてJICA(国際協力機構:日本の政府開発援助(ODA)を担う機関)のボスニア・ヘルツェゴビナの担当から連絡があり、2014年2月にはプロジェクト実現に向けて現地への視察が実現しました。
初めて同地を訪れた樋口さんは「サラエボ空港からホテルへ向かうタクシーの窓から見えた光景は衝撃的でした」と振り返ります。終結から20年近くが経過しているにも関わらず、建物には無数の銃弾の跡が残り、紛争の傷跡が街のいたるところに生々しく刻まれていました。現地政府関係機関とのミーティングでは「実現すれば素晴らしいプロジェクトだとは思うけど、あなたたちが考えている以上に対立は根深く残っている。実際に対立している民族の子ども同士が一緒にスポーツをするなんて無理だよ」という悲観的な声も。
Jリーグ職員時代にジェフユナイテッド千葉に3年間出向していた経験のある樋口さん。クラブのレジェンド、イビチャ・オシムさんの出身国でもあるボスニア・ヘルツェゴビナには特別な縁を感じていました。「オシムさんはボスニア・ヘルツェゴビナでは本当に偉大な存在なんです。民族の対立感情が根強く残る同地ですが、オシムさんはどの民族からも本当に信頼されている。このプロジェクトは絶対に実現させたいと感じました」。

民族が複雑に交錯する国で、共生の種を育む
ボスニア・ヘルツェゴビナは、主にボスニア系、クロアチア系、セルビア系の3つの民族が暮らしている多民族多宗教国家です。民族によって教育課程が異なり、歴史認識も異なる。1995年のデイトン合意から約30年が経過した今も、戦禍の記憶が人々の心に深く刻まれています。
現地では、民族ごとに学校が異なり、スポーツクラブも分かれているのが一般的です。当然ながら子どもたちは自分の民族のスポーツクラブで活動しているので、違う民族の子どもたちと触れ合う機会はほとんどありません。そんな環境下で、樋口さんたちは民族にかかわらず、希望すれば誰もが参加できるスポーツアカデミー「Mali Most(マリモスト:現地の言葉で「小さな橋」の意味)」をボスニア・ヘルツェゴビナ南部の町であるモスタルに開設しました。モスタルはかつての紛争の激戦地の一つ。街を南北に流れるネレトヴァ川を挟んで激しい戦闘が行われた歴史があります。街の中心にあるクラブハウスの立地も、どの民族の子どもでも参加しやすいようにと、かつての紛争時の境界線に近い中立的な場所が選定されました。「かつて対立していた歴史があったとしても、一緒にスポーツをすることで、他者への理解やリスペクトが育まれるはず」。関係者のそうした思いが、Little Bridgeの活動を支えています。
マリモストは民族にかかわらず参加できるアカデミーですが、設立して数年くらいは、そのことを知らない保護者がアカデミーの見学に来てから、異なる民族の子どもたちと一緒に活動することを知って怒って帰ってしまうというケースもあったそうです。約10年にわたる地道な活動を通じて、モスタルの街でも徐々に活動の理解が深まってきています。

それを象徴するのが2018年に日本の子どもたちがモスタルを訪れた際の出来事です。前年にマリモストの子どもたちが日本を訪問して日本の子どもたちとのスポーツ交流を実施していたのですが、この年は逆に日本の子どもたちがマリモストを訪れることに。「日本の子どもたちが来るなら、大歓待しなきゃいけない」と、アカデミーに参加する子どもたちの保護者が民族の垣根を越えて協力し、歓迎のバーベキューを企画してくれたのです。紛争時代には生まれていなかった子どもたちと違って、保護者たちは紛争の記憶が色濃く残る世代です。異なる民族の人間とはほとんど交流しないという方もいる中で、マリモストでは子どもたちの活動が保護者にも影響を与えています。

「子どもを通じて保護者たちにも変化が起こり、民族を超えた交流も生まれています。これは僕らのプロジェクトとして本当に意味のあることです」と樋口さんは語ります。こうした参加者同士の交流シーンは、今では日常的に目にすることができるようになってきました。
最初に活動に参加した子どもたちの中には今や20歳を超えている子もいます。このプロジェクトに関わった人がモスタルの街に増えていくことで、一過性のものではなく、多民族が共生する場を日常にしたい。そんな想いで、Little Bridgeは活動を続けています。
「日常の中に多民族が共存する場が生まれることで、人々の意識や街の景色が変わっていく。それが持続可能な平和構築の鍵だと考えています」
早稲田で育まれた「たくましい知性」と「しなやかな感性」
時に大胆な決断をしながら、実現したい未来に向かって挑戦していく。そんな樋口さんの志と実行力はどのように養われたのでしょうか?
樋口さんは自身の活動のモチベーションを「利己的な利他主義」と表現します。この価値観は大隈重信の「一身一家一国の為のみならず、進んで世界に貢献する抱負が無ければならぬ」という言葉にも通じています。
「社会に貢献できることが、自分にとってもうれしいことなんです。自分のためだけでなく、社会や世界に貢献することを考えてほしい。それが自身の幸せにも繋がるはずです」。
スポーツを通じて世界に貢献する樋口さんの挑戦は、これからも続いていきます。

My Waseda University My Waseda UniversityMy Waseda University My Waseda University
わたしの早
稲
田
大
学

私が早稲田に入学したのは1997年。入学式の当時の奥島総長の挨拶で「Think globally, Act locally」というフレーズを聞いたのは心に残っています。当時の自分は、現在みたいな活動をするようになるとは思ってなかったはずですけど。人間科学部スポーツ科学科は所沢キャンパスでしたが、他学部の友人とも多くの交流を持ち、多くの刺激を受けました。仲間とサークルでサッカーをし、所属していたスポーツ社会学ゼミでは授業が終わっても先生や仲間と夜遅くまで語り合う日々でした。自由闊達な校風の中で「たくましく挑戦すること」と「しなやかに人と関わること」を自然に学び、それが今の自分の活動の礎になっています。
早稲田大学
創立150周年記念
事業募金への
寄付のお願い
次の時代を切り拓くための挑戦を続けるために──。皆さまからのご支援や期待が、進化を力強く後押しします。ぜひともお力添えいただき、ともに未来を築いていただけますようお願い申し上げます。





