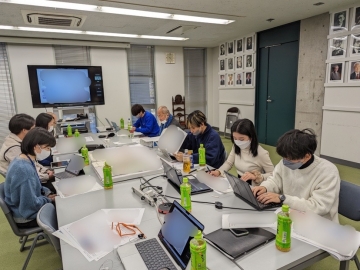「現代に生まれた自分たちだからこそ、忘れてはいけないものがある」
大学院創造理工学研究科 建築学専攻 修士課程 2年 黒澤 優太(くろさわ・ゆうた)

西早稲田キャンパス 63号館にて
大学院で建築を学び、2022年11月「第14回ハーフェレ学生デザインコンペティション2022」では優秀賞、2023年7月「第10回POLUS学生・建築デザインコンペティション」では最優秀賞を受賞するなど、未来の建築を担う人物として注目される黒澤優太さん。これまで手掛けてきた作品には、世の中に抱く違和感や日常で得られた気付きなどさまざまな思いを落とし込んでいるといいます。今回はその受賞作品の内容を中心に、建築に対する思いや将来の展望について聞きました。
――「第10回POLUS学生・建築デザインコンペティション」での最優秀賞受賞、おめでとうございます。率直な感想を聞かせてください。
「POLUS学生・建築デザインコンペティション」は、数多くある学生・建築コンペの中でも非常に規模が大きく、今回の応募作品は362点にも及びます。また、審査員に有名な建築家の方が多く、審査委員長の西沢立衛さんは、石川県にある金沢21世紀美術館などの建築デザインを手掛け、「SANAA」という日本人建築家ユニットでも世界的に有名な方。このコンペには今までも何度か応募してきたのですが、学生最後の年にこのように結果に結びついたことが1番うれしいです。
――最優秀賞作品は『大工と暮らす木工ヤードのある家』という作品ですが、この作品のアイデアはどこから得たのですか?
これは社会の効率性や利便性への過度な追求に対する違和感から着想を得ました。固く動かないものやメンテナンスいらずの建物やプロダクトも非常に便利ではありますが、手間を掛けることで人とモノの間に、ある種の信頼関係のようなものが生じていると考えています。簡単にいうと愛着のようなものです。昔ながらの日本住宅であれば畳や障子を張り替えるなど、住まい手自らが住まいと関わり共存していく形がありました。このような“住まい手と住まいの関係”は、近代化以降のモノで、ありふれた世界に生まれた僕らだからこそ忘れてはいけないものだと思っています。それをどうにかデザインのアイデアに取り入れられないかという考えが、この作品の根底にあります。

「第10回POLUS学生・建築デザインコンペティション」最優秀賞作品の『大工と暮らす木工ヤードのある家』。作り手である大工と住民が共同生活を行い、一丸となって自ら暮らしを創造していくという斬新なアイデアが評価された
――このコンペティションで1番苦労したことはなんですか?
このコンペは1次審査から2次審査までの間で、362点に及ぶ全応募作品の中から5作品にまで絞られます。まずはそこをどう突破するかが重要なのですが、その作戦を練るのに多くの時間を要しました。1次審査では模型などの制作はなく、A2のアートボード1枚の中で全てを伝える必要があります。そのため、大きく見せるものと細かく伝えることの優先順位やその表現手法を意識することで、目に留まるようなビジュアライズを考えました。また、高度なプレゼンテーション能力も求められるため、どんな議論を展開したいかを意識しつつ、研究室の友人などから客観的な意見をもらいながらブラッシュアップを続けました。
1次審査を突破したら、2次審査ではいよいよ模型作りを行いますが、その作業もかなりの体力が必要になります。他のプロジェクトの兼ね合いもあったため、友人の助けを借りながら締め切りギリギリまで完成させずに取り組んだことも、今では良い思い出です(笑)。

「第10回POLUS学生・建築デザインコンペティション」での写真(右下が黒澤さん)
――そもそも、黒澤さんが建築学を志したきっかけは?
昔から図工や絵を描くことが好きで、“つくる”こと自体に興味がありました。時間を忘れて没頭できる「ものづくり」の心地良さを幼い頃から実感として持っていたと思います。中でも建築を選んだ理由は、美術や音楽とは違い、必要不可欠なインフラとして存在しているという点が非常に大きいです。
大学で建築を学び始めてからは建築の文脈で社会学や哲学などに触れる機会も多くあり、自分の中にあるものづくりの解像度が次第に高まっていきました。最近では「シュルレアリスム」思想に関心を持っています。
――「シュルレアリスム」とは、具体的にどのような考え方なのでしょうか?
超現実主義ともいわれ、20世紀にフランスで起こった芸術運動をきっかけに有名になった思想で、絵画ではサルバドール・ダリやルネ・マグリットなどに代表されます。例えば、さまざまな素材を組み合わせて創作するコラージュという技法を駆使して、絶対に出合うことのない二つのものを組み合わせるといった手法もこの考えから派生しています。2022年優秀賞を受賞した「ハーフェレ学生デザインコンペティション」でも、この手法が一つのヒントになりました。
この設計は、記憶というカタチを持たない不連続な断片にカタチを与えて、建築としての全体性を獲得するまでを描いた試論です。具体的には文章に出てきた風景や心情描写を友人にわざと誤読してもらうことで空間に置き換えるなど、コミュニケーションを通して記憶を文章、スケッチ、空間と徐々に高次元化していきます。偶然性や他者性を介しながら設計をしていくというところでは、「シュルレアリスム」に通ずる部分があると思います。

「第14回ハーフェレ学生デザインコンペティション2022」優秀賞作品『海を収めて』。人の記憶から生まれるさまざまな情景を1つの空間に落とし込んだ作品
――一方、研究室ではどのようなプロジェクトに取り組んでいるのでしょう?
私は法政大学のデザイン工学部建築学科に所属していたのですが、当時から古谷誠章先生(理工学術院教授)の研究室に興味を持っていました。多くのプロジェクトや多様性あふれる雰囲気に憧れて大学院を受験しましたが、実際に入ってみると本当に数多くのプロジェクトがあることに驚きました。常時10個ほど動いているプロジェクトに、学生1人当たり3~4個参加しており、被災地支援や次世代医療建築 、他学部との合同研究など分野もさまざまです。例えば、企業と関わるプロジェクトでは、普段あまり意識することのない利用者の声や経済性など、現実的な問題に踏み込んで提案できたことが貴重な経験となりました。実践しながら建築空間を学べることも、自身の成長にもつながっていると感じます。
また、古谷研究室はさまざまな場所から多くの留学生が集い、研究室メンバーの約半分を占めます。外国の建築に対する価値観や背景は日本と全く異なるものも多く、とても刺激的です。さらに、外国との違いを実感することで日本建築にしかない魅力も再認識することができました。
写真左:大成建設株式会社との合同プロジェクト、次世代医療研究会とのミーティングの様子
写真右:合同プロジェクトで北海道を視察した際の集合写真
――黒澤さんの将来に対する展望を教えてください。
4月から企業に就職する予定です。誰に対してどんな解像度を持って建築をつくっていきたいのかとても悩みましたが、多くの人々が利用する大規模なプロジェクトを手掛けたいという思いからゼネコンを選びました。今は、渋谷のミヤシタパークを始めとした商業ビルのあり方について関心があります。オンラインショッピングなどが普及し、購買行為などの当たり前が変わる今だからこそ、商品を売っている実空間の意味が問い直される時代になっています。単なる売り買いを超えた新しい価値を提供できるような挑戦をしていきたいですね。また、近年の地域の風土や伝統を軽視した計画や、そこに元々あったコミュニティーを壊しかねない過度な開発行為に自分は懐疑的で、だからこそ都市の文脈の先にあるような建築設計やまちづくりに挑戦していきたいです。
第863回
取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)
社会科学部 3年 堤 壮太郎
【プロフィール】

静岡高等学校卒業、法政大学デザイン工学部建築学科卒業。早稲田の建築学専攻に憧れを抱き大学院創造理工学部建築学専攻に入学。音楽と自然が好きで、自然の感じられる音楽フェスなどに行くのが趣味。好きなバンドはくるり、カネコアヤノ、yonawo。
Webサイト:https://yutakurosawa.com/work