
社会問題ってなんだか敷居が高い…そう思う早大生も多いかもしれません。新コーナー「教えて! わせだ論客」では、社会が抱える特定の問題に着目し、4人の教員からそれをひもとくヒントを教えてもらいます。
2023年度のテーマは「平和をどう守る?」。ロシアによるウクライナ侵攻などで世界情勢が不安定になる中で、あらためて平和とは何かを考えます。3人目のゲストは、中世ロシア文学と中世ロシア史を研究する三浦清美教授(文学学術院)です。ロシアの歴史からウクライナ侵攻を読み解く前編に引き続き、後編ではロシアの宗教観や、早大生へのメッセージなどを伺いました。
学生たちは、大学での学びを通して平和にどう貢献できるでしょうか?
文学や歴史学を通した学びは、相手を知り理解することにつながります。知ることを急ぐ必要はないし、知らないことを恥ずかしいと思わなくていいので、じっくりと知性の“ため”を作っていってください。
プーチン大統領の権威を下支えする「宗教的な統治者」とは
ロシアのウクライナ侵攻は「プーチン大統領の戦争」と言われることもあります。中世ロシア史を専門とする三浦先生から見て、プーチン大統領はなぜ侵攻に踏み切ったのでしょうか?
ウクライナ侵攻に至った理由の一つには、前編でお話したようなロシア人とウクライナ人に一体性を見いだすような歴史観が挙げられます。また、抑制が利かなくなったがゆえの“権力への過信”も背景にあると感じています。
人間は完璧な生き物ではありませんから、大きな権力を背負わされているうちに「自分はなんでもできる」と全能感を持ってしまうのは不思議なことではありません。2014年のクリミア併合がうまくいきすぎたことも、プーチン大統領の権力への過信に拍車をかけたのではないかと思います。

(写真提供:共同通信イメージズ)
そんなプーチン大統領のウクライナ侵攻を、ロシア人はどのように見ているのでしょうか?
ウクライナ侵攻以降も、大きな都市やその近郊では市民は穏便な日々を過ごせていますが、一方で、世界情勢を揺るがす戦争が起こっていることも事実です。だからロシア人は、複雑な思いを抱えているのではないでしょうか。
ロシア内部から見たプーチン大統領のイメージと、世界各国から対外的に見たプーチン大統領のイメージには乖離(かいり)があります。西側諸国から見れば、今のプーチン大統領は冷酷非道な侵略者ということになりますが、ロシア人はそう見ていないと感じます。実際に、侵攻当初は国内で戦争反対を唱える運動が起きたものの、世論調査ではプーチン大統領の国内支持率は変わらず高い結果が出ています。

2022年、モスクワ・赤の広場を歩く市民(写真提供:共同通信イメージズ)
私は、今回の侵攻前に何度もロシアに足を運び、現地の方と話してきました。そこで感じたのは、ロシア人が抱える「西側文化の流入に対する割り切れない思い」でした。というのも、ロシアにとってのグローバル化は、「精神」を軽視してアメリカナイズされることと重なる面も大きかったのです。ロシア市民も、西側文化の流入で生活が安定し豊かになったことを喜ぶ一方で、相入れない違和感があったようでした。
この割り切れなさと、1991年のソ連崩壊から立ち直らせて、西側諸国と互角に対抗できる強い国を作ったという観点とが絡み合い、プーチン大統領の支持にもつながっているように思えます。

強国を築いたプーチン大統領が支持される理由には、ロシアの宗教的な背景があるのでしょうか?
まさにその通りです。国内で主流のロシア正教は、ローマ・カトリック教会ではなく、ギリシア正教がルーツですが、その特徴的な2つの考え方が関係しています。
1つ目は、統治者は天上の神・パントクラトールの地上における代理人であるとする「アウトクラトール」です。ローマ・カトリックの世界では、ローマ教皇が持つ宗教的権威と、諸国の王や皇帝が持つ世俗権力が分離されていました。それに対し、ギリシア正教は、国の頂点に立つ統治者を「神の代理人」として見なしたのです。
2つ目は、神であるキリストが人間になった以上、人間もキリストのまねびをして神になる努力を惜しんではならないとする「テオーシス」という思想です。キリストは完全な人間であり完全な神であった。だからこそ人間もそうあろうと考えるわけです。

クリスマス礼拝を執り行うロシア正教会のキリル総主教(写真提供:共同通信イメージズ)
これらの考え方は、政治的な局面にも大きく影響しています。絶対的な統治者を欲する伝統的なロシアの意識はその一例です。
そして統治者は、神の代理人としてやり遂げなければという義務感や、聖霊としての神と一体であるような充足感を持って政治と向き合う部分もあるでしょう。プーチン大統領のウクライナ侵攻にも、このような感覚があったのではないかと見ています。
とはいえ、「アウトクラトール」「テオーシス」の考え方自体が悪というわけではありません。例えば、過去には統治者がその絶対的な権力を過剰にふりかざすことなく、抑制的に行使して治めた時代もありました。前編で紹介したアレクセイ帝がその一人です。
また、「テオーシス」による感性のあり方はロシア人を強く鼓舞するものでもあります。「努力を重ねてキリストに近づこう」「キリストと苦しみを分かち合い、大きなことをやり遂げよう」といった感覚は、文学、音楽、スポーツなど多分野でのロシア人の活躍の後押しになっている気がしています。

2014年のソチ五輪では、フィギュアスケート団体を含め11個の金メダルを獲得した(写真提供:共同通信イメージズ)
知識や疑問の積み重ねが、これからを生き抜く「知性」になっていく
私たちが文学や歴史学を学ぶ意義を改めて教えてください。
平和を守るためにまず必要なのは「相手を知る」ことだと考えています。文学や歴史学での学びは、いろいろなことを知るだけでなく、理解力や想像力を育てることにもつながるんです。
国の成り立ちや歴史を知ったからといって、すぐに戦争が終結するわけではないので、大学で得る学びや知識は遠回りに思えるかもしれません。しかし、だからといって学生の皆さんには知ることを投げ出さないでもらえたらうれしいですね。
最後に、学生たちに向けてメッセージをお願いします。
知ることを急ぐ必要はないし、知らないことを恥ずかしいと思う必要もありません。大切なのは、「なぜだろう?」とか「分からないぞ」という自分なりの疑問を自分自身の中にためていくことです。その“ため”の蓄積がふとしたタイミングでつながり、世界を生き抜くための知性となっていきます。
例えばロシアとウクライナの動向にしても、「なんでこんな戦争を仕掛けたんだろう?」「ロシア人はどう感じているんだろう?」など、自分が抱いた疑問を大事にしてください。「自分には関係ない」と切り捨てずに、日々の生活を送ってもらえたらと思います。
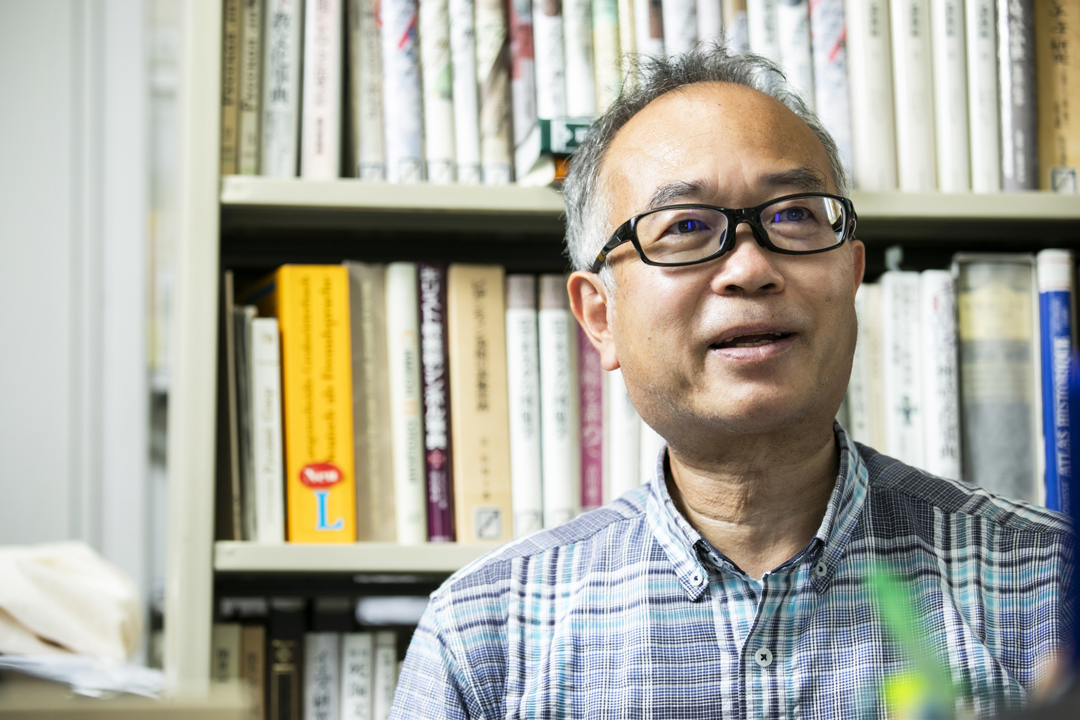
三浦 清美(みうら・きよはる)
文学学術院教授。博士(文学)。専門分野は、中世ロシア文学と中世ロシア史。著書に『ロシアの源流-中心なき森と草原から第三のローマへ-』(講談社、2003)、『ロシアの思考回路 その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』(扶桑社、2022)など。
取材・文:市川 茜(2017年文化構想学部卒)
撮影:布川 航太
画像デザイン:内田 涼
▼前編はこちら!








