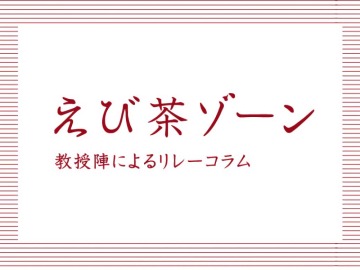
何かしらの問題を解決するためには課題設定能力と課題解決能力が必要であるが、昔に比べると今は高等教育の環境整備も進み、昨今の大学生は課題解決能力(の一部)が伸長しているようだ。他方、課題設定能力については依然改善点があるように感じる。例えば、私の授業では受講生から質問を提出してもらうが、皆、早稲田大学に入学できるほどに十分な学力があるにもかかわらず、「質問力」の格差が少なからず存在する。「今後の日本の在り方は?」のような、私がどう答えていいのか途方に暮れるような大きな質問から、「〇〇とは何ですか?」といった、ググれば分かるような小さな質問まである一方、本質に至る可能性を秘めた質問も時にある。
課題設定能力とは、誤解を恐れず言えば「質問力」に現れる。建設的な議論のためには適切なサイズの質問を問うことが重要であり、どの社会に行っても恐らく役立つスキルであろう。質問が大きすぎる場合はそれを切り分ける方法が、小さすぎる場合はそれが些末であると理解し本質に接近する方法が、それぞれ求められる。学問の府としての大学の意義は、こういった課題設定能力のための論理的思考訓練にもあろう。
質問力は一朝一夕で身に付くものではない。とにかくどのような質問でも、倦まず弛まず続けることで磨かれ得る。その最たる訓練が、卒業論文であろう。論文とは、基本的にはQ&Aである。意味のある問いを立て、答えを自分なりに見つける。それだけに注力できるのは本当にぜいたくな時間である。
と、学部生であった過去の怠惰な私に言ってやりたい。
(K)
第1153回








