誰もが暮らしやすい社会の実現に向けた支援活動を紹介。私たちの身近にも、さまざまな支援の形がある。
man-vo.

私たちは、サークル員一人ひとりが楽しみながらボランティア活動をすること、そして活動を通して学びややりがいを得ることを大切にしています。年間通して活動をしており、この夏は自閉症の子どもたちとプールで遊んだり、花火を一緒に見たりしました。他にも、特別養護老人ホームに入居されている方々とお話をさせていただいたり、そこで行われる「夕涼み会」というお祭りにも参加させていただきました。

思いやりの気持ちが大切です
障がいを持っている子どもたちは、その日ごとに調子が違います。活動ではその子どもたちに合わせながら、人との関わりの中で学ぶことに対して、私たちが少しでもその手助けになればいいと考えて活動しています。私たちの活動は小さなことの積み重ねであり、長い時間をかけた先の成果を見据えて関わることが大切だと思います。
活動をしていて一番うれしいことは、子どもたちや施設の利用者さんたちの笑顔が見られることです。相手のためになる活動ができたとき、またこの笑顔が見られるように、より良い活動にしていきたいと感じます。 (副幹事長 人間科学部3年 正木 佑典)
Profile:団体名は「human-volunteer」の略で、その名のとおり人に関わるボランティアをさせていただいております。誌面を通じて、少しでもボランティアに興味を持っていただければ幸いです。http://manvohp.web.fc2.com/
障がい学生支援室

皆さんは「情報保障」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。読んで字の通り、学生生活を送る上で必要な情報を、障がいのある学生も等しく得られるようにするための支援のことです。私は「利用学生が授業の雰囲気を共有できること」をモットーとして、聴覚に障がいのある学生の支援をしています。

ぜひ気軽に支援活動に参加してみてください!
 支援では、支援者が二人一組で障がい学生の隣に座って一緒に授業を受け、先生が話すことを二人で連携してノートに書き取ったり、パソコンに入力したりして視覚化しています。一見単純そうに見えますが、さまざまな苦労や工夫があります。例えば、先生が話すこと全てを書き取ることはできません。もちろん慣れるにつれて略語も使えるようになりますが、専門用語が頻出する授業では、言葉の取捨選択に苦労しました。一方で、ゼミなどでの学生同士のおしゃべりや、先生の冗談、笑い声なども含めた授業の「雰囲気」をうまく伝えられたときには、とてもやりがいを感じます。また利用学生や他の支援学生とも支援―利用の壁を越えて仲良くなり、交流が広がりました。
支援では、支援者が二人一組で障がい学生の隣に座って一緒に授業を受け、先生が話すことを二人で連携してノートに書き取ったり、パソコンに入力したりして視覚化しています。一見単純そうに見えますが、さまざまな苦労や工夫があります。例えば、先生が話すこと全てを書き取ることはできません。もちろん慣れるにつれて略語も使えるようになりますが、専門用語が頻出する授業では、言葉の取捨選択に苦労しました。一方で、ゼミなどでの学生同士のおしゃべりや、先生の冗談、笑い声なども含めた授業の「雰囲気」をうまく伝えられたときには、とてもやりがいを感じます。また利用学生や他の支援学生とも支援―利用の壁を越えて仲良くなり、交流が広がりました。
(法学部3年 高田 瑠璃子)
Profile:聴覚や視覚に障がいのある学生や、肢体に不自由のある学生に向けた修学支援をコーディネートする「障がい学生支援室」に支援者として登録しており、必要に応じてノートテイク講座などを受講した後、支援を行っている。
- http://www.waseda.jp/student/shienshitsu/
- Twitter:@wasedau_dsso
- Facebook:http://www.facebook.com/WasedaU.DSSO
手話さあくる

私たちは、「楽しんで手話を学ぶ」ことをモットーに、活動を行っています。
前期にはゲームを行いながら手話を学ぶレクリエーションを実施し、後期には手話イベントを行っています。昨年の手話イベントでは、サークル1年目が役者を務める手話劇を行いました。200人を超える来場者の中には、聴覚障がいがある方も多数いらっしゃって、サークル員にとって聴覚障がいへの理解が深まる機会になるとともに、聴覚障がいがある方同士、また聴覚障がいがある方と健聴者の交流の場にもなりました。

「見える言葉」でお話ししましょう!
 私たちが活動を行う中で難しいと感じることは、「情報保障」です。サークル員のほとんどが大学まで手話を勉強したことのない健聴の学生であるため、普段のコミュニケーションにおいて、どうしても音で聞こえてくる言葉に情報伝達を頼ってしまいがちです。聴覚障がいがある方は、音の情報が入ってこない、という当たり前の状況を健聴者が理解する必要があります。そして、聴覚障がいがある方と健聴者が同じ場にいる際に、そこで行われている会話の内容をどのように同じ情報として共有するか、ということを常に意識しています。(幹事長 法学部4年 向出 康智)
私たちが活動を行う中で難しいと感じることは、「情報保障」です。サークル員のほとんどが大学まで手話を勉強したことのない健聴の学生であるため、普段のコミュニケーションにおいて、どうしても音で聞こえてくる言葉に情報伝達を頼ってしまいがちです。聴覚障がいがある方は、音の情報が入ってこない、という当たり前の状況を健聴者が理解する必要があります。そして、聴覚障がいがある方と健聴者が同じ場にいる際に、そこで行われている会話の内容をどのように同じ情報として共有するか、ということを常に意識しています。(幹事長 法学部4年 向出 康智)
Profile: 毎週月・金曜の6~7限に活動を行う、約60人のアットホームなサークルで、前期は手話を使ったレクリエーション、後期には手話イベントを行っています。他大学との交流会や聴覚特別支援学校のボランティアを行うこともあります。
- http://hands.ifdef.jp/
- Twitter:@syuwaseda
特定非営利活動法人ReBit

ReBit は『LGBT の子どももありのままでオトナになれる社会』を目指す団体です。LGBTとは同性愛者や性同一性障がい者などの性的マイノリティを指し、日本では人口の約5・2%を占めるといわれています。
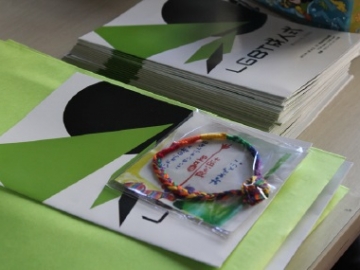
しかし、LGBTは教育・社会保障・法律などさまざまな制度から取りこぼされ、日常生活においてもいないものとされています。こうした現状は、LGBTの約3人に2人が一度は自殺を考えるという深刻な事態を招いており、特に希死念慮が高まる時期は第二次性徴期(おおよそ8、9歳から17、18歳まで)といわれています。しかし、同性愛に関して教育現場で適切な情報提供を受けられなかった人は93%にのぼり、LGBTについて正しい知識を得る機会がないままオトナになります。

ありのままでオトナになれる社会へ
この現状を変え、互いの違いを受け入れあえる社会にするために、ReBitは小学校〜大学・教育委員会などで110回以上、LGBTに関する出張授業や研修を実施してきました。また、「ありのままの自分を祝福する日」として、世田谷区後援のもと、全国7カ所で「LGBT成人式」を計25 回開催し、約1800名が参加。2013年度より、LGBTの就活生に向けた支援にも取り組んでいます。(代表理事 2013年商学部卒業 藥師 実芳)
Profile:2009年に学生団体「Re:Bit」として設立後、翌年より大学公認サークルとなり、2014年にはNPO法人に。少しずつ(Bit)を繰り返す(Re)ことで社会がよくなるように、大学生を中心にLGBTの人もそうでない人も共に活動している。
(『新鐘』No.81掲載記事より)
※記事の内容、教員の職位および学生の所属・学年などは取材当時(2014年)のものです。








