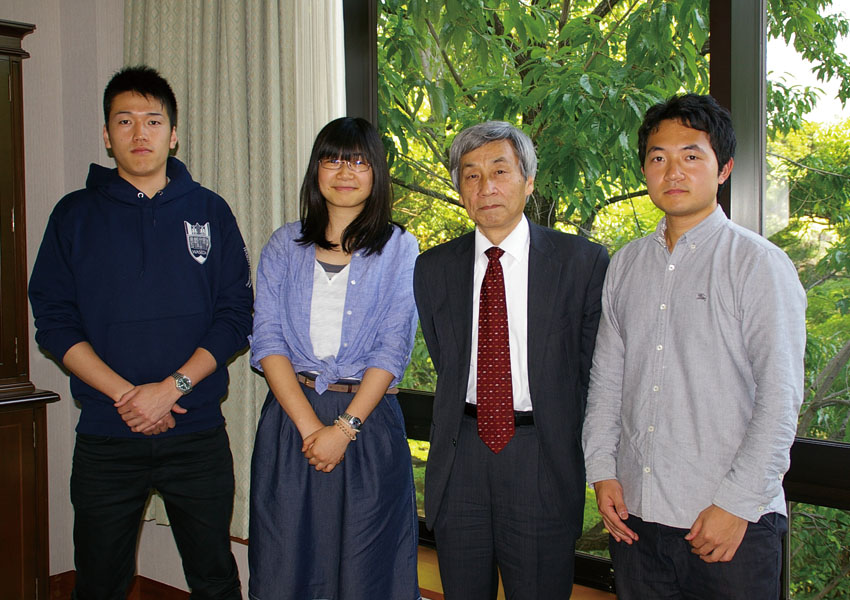 アジアのリーディングユニバーシティを目指し、中長期のロードマップとして作成された「Waseda Vision 150」。未来の早稲田に学生はどのように関わっていくべきか、3人の学生が、橋本周司副総長にお話を伺った。
アジアのリーディングユニバーシティを目指し、中長期のロードマップとして作成された「Waseda Vision 150」。未来の早稲田に学生はどのように関わっていくべきか、3人の学生が、橋本周司副総長にお話を伺った。

副総長(理工学術院教授) 橋本 周司

商学部3年 山下 健志
お話を伺った先生
副総長(理工学術院教授) 橋本 周司(はしもと しゅうじ)
理工学術院長などを歴任。理事会での担当業務は、学事統括、教務、研究推進、学生、文化推進、経営企画。
インタビューした学生
・山下 健志(やました たけし) 商学部3年
広島県出身。「早稲田祭2013」運営スタッフの代表を務める。
・冷 澄 (れい ちょう) 政治j学研究科修士1年

政治学研究科修士1年 冷 澄
上海出身の留学生。大学院では、ジャーナリズムコースに所属。

人間科学部4年 菅田 武嗣
・菅田 武嗣(すがた ぶじ) 人間科学部4年
佐賀学生稲門会の副幹事長。WAVOC気仙沼チームの一員としても活動中。
テーマ1
グローバル化について教えてください!
冷 「Waseda Vision 150」を拝見するとグローバル化に関する項目が多く見られましたが、現在の外国人留学生の割合を見てみると、特定地域の学生が非常に多くて偏りを感じます。かく言う私も中国からの留学生ですが…。
橋本 さまざまな価値観の中で学ぶという観点から言うと、確かにもう少し多様性があった方が好ましいかもしれませんね。そのためには、アジア諸国はもちろんのこと、欧米などからも積極的に留学生を呼び込む必要があると思っています。
山下 多様性を確保するために、具体的な施策はありますか?
橋本 やはり重要なのは広報活動でしょう。実際、数年前から「早稲田からWASEDAへ」というスローガンを掲げてグローバル化に力を入れていますが、早稲田大学で行われている魅力的な講義を、
インターネットで世界へ配信することもアイデアの一つとして考えています。
菅田 その一方で、早稲田大学の魅力は、地方から多くの学生が集まってくるところにもあると思っています。
橋本 その通りです。世界中から留学生を集めたり、卒業して世界に羽ばたくことだけが“グローバル”ではありません。卒業後、地元に戻って仕事をする学生もたくさんいることでしょう。その時に、世界の現状を見渡した上で、地域に貢献できる仕事ができるかどうか、また、そのような人材を育てることができるかどうか、それが本当の意味でのグローバルユニバーシティの在り方だと思います。
テーマ2
奨学金についての改革案はありますか?
菅田 私は佐賀学生稲門会の副幹事長を務めているのですが、地方からの学生が減少傾向にあると聞いています。経済的な理由などさまざまな背景があると思いますが、奨学金などの支援制度についてはどのようなアイデアをお持ちですか?
橋本 今まさに奨学金の制度を抜本的に見直しているところです。具体的に言うと、大学に入学してから奨学金の審査を行うのではなく、合格した時点で給付が確定するような奨学金の割合を増やしていこうと考えています。入学してから給付の有無が決まるというのでは奨学金を当てにできませんし、地方の学生は安心して上京できないでしょうから。
冷 私も台湾の企業から奨学金をいただいていますが、勉強に集中するには、やはり一定の経済支援は欠かせません。
橋本 奨学金に加えて「スチューデント・ジョブ」の充実を考えています。学内での学生アルバイトのことですが、研究に深く関わるような仕事もありますし、地方出身者や留学生の大きな助けになることを期待しています。
テーマ3
早稲田らしさを発信するために!
山下 個人的な印象としては、アカデミックな面ばかりが扱われていて、「これって早稲田大学の本来あるべき姿なのかな?」と疑問を感じました。“早稲田らしさ”とは、体育各部やサークルの活動が盛んなことだったり、「早稲田祭」のようなイベントだったり、または地域との交流だったり、学生の自由で活発な活動の中にあると思うんです。
橋本 実は、13ある核心戦略の一つに「早稲田を核とする新たなコミュニティーの形成」という項目があるのですが、それはまさに学生たちの盛んな活動を後押ししたいという想いが込められています。特に早稲田大学は、演劇や音楽、ダンスなどの文化系サークルが盛んですから、彼らの活躍の場所と時間をさらにつくろうと、早稲田祭のようなイベントの頻度を増やすことも検討しています。
菅田 早稲田らしさの発信ということで言うと、今後、大学が主体となって、早稲田大学や早大生の情報を発信していくようなことはお考えですか?
橋本 ゆくゆくはあらゆることを“オープン化”できればと思っています。つまり、学生のアカデミックな活動から体育各部やサークルの活動に至るまで、全ての記録や情報を一元化して、外部から気軽に検索できるようにするという試みです。もし実現すれば、就職活動の仕組みも大きく変わるかもしれませんよ。エントリーシートを書くのではなく、企業側がデータベースにアクセスして、採用条件にマッチした学生をスカウトする。熱心に活動する学生にとってはやりがいが生まれるでしょうし、それこそが本当の意味での広報活動ではないでしょうか。
まとめ
プロジェクト実現に必要なこと!
山下 お話を伺う中で、早稲田らしさを保ちながらも、次世代に向けて進化していくことが大切だと感じました。
橋本 そうですね。そういった早稲田のDNAをベースにしながら、新しい価値を積み上げられたらと思います。ただ、最近感じるのは、近頃の早大生は少しお行儀が良すぎるかなということ。というのも、いつからか学生が大学にとっての“お客さん”になってしまった。大学側が用意したサービスを利用するだけでなく、学生側からも要望の声をもっと上げてほしいと思います。学生こそが大学の“主人公”なんですから。学生と教員と職員が共通のイメージを持って、早稲田大学の未来のために次なる一歩を踏み出せたらと思います。
冷 そういった意見を交換したり、学生と教職員とが交流できる場がもっとあればいいのですが……。
橋本 その一環として、昨年に行われた「Student Competition」を今年も開催する予定です。前回は遠慮があるのか、真面目な提案が多かった。次回は我々が考えつかないようなとびっきりのアイデアをお待ちしています。20年後の早稲田のことをもっともっと語り合いましょう!
「Waseda VisioN 150」とは
2012年11月15日、早稲田大学は今から20年後の創立150周年(2032年)を見据えた中長期ビジョン「Waseda Vision 150」を発表しました。早大生がどのような教育・研究の中で何を身に付けて世界へ羽ばたくのか、早稲田の研究はどのように世界の幸福に貢献しているのか、そして、早稲田を巣立った校友(卒業生)がどのような姿で、世界や地域を支える一員として活躍しているのか、そういった姿を示したものです。そして、これらビジョンの実現のため、今から着手すべき戦略を掲げて、大学全体で推進していきます。
4つのビィジョン
1. 世界に貢献する高い志を持った学生
2. 世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究
3. グローバルリーダーとして社会を支える卒業生
4. アジアの大学のモデルとなる進化する大学
URL:http://www.waseda.jp/keiei/vision150/index.html
VISIONのコラム
早稲田大学では「Waseda Vision 150」の一環で、2013年度から1年を4つの授業実施期間に分ける「クォーター制」を導入。クォーター制によって、世界中の大学のアカデミックカレンダーに柔軟に対応できるようになり、海外留学生の受け入れや日本人学生の海外留学が活発化するなど、さらなる国際化の進展が期待できます。
現在、早稲田大学では夏休みを挟んだ春学期(16週)と秋学期(16週)を区切りとするセメスター制を主として採用していますが、クォーター制は各学期をそれぞれ半分にした8週間で1科目を完結します。例えば、セメスター制では週1回行っている授業を、クォーター制では週2回行うことで、短期間で集中的に学ぶことも可能になります。

インタビュー中の様子








