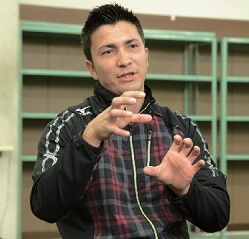競技のために身体機能を極限まで追い込むアスリートたち。ライバルより抜きんでるには、より効果的なトレーニングを行う必要があります。岡田純一スポーツ科学学術院教授が、世界で活躍する校友・学生アスリート3人の強さの秘密を科学的に検証します。

スポーツ科学学術院教授 岡田 純一(おかだ・じゅんいち)
早稲田大学教育学部教育学科体育学専修卒業後、順天堂大学大学院、東京大学大学院に学ぶ。1995年より早稲田大学人間科学部専任講師。同助教授、同大学スポーツ科学部助教授、同学術院准教授を経て現職。専門はトレーニング科学、バイオメカニクス。早稲田大学ウェイトリフティング部監督。
 ショートトラックスピードスケート選手 菊池 萌水(きくち・もえみ)
ショートトラックスピードスケート選手 菊池 萌水(きくち・もえみ)
ショートトラックスピードスケート選手。早稲田大学社会科学部3年生。2010年に開催された全日本ジュニアショートトラック選手権大会で総合優勝。13年に開催されたソチオリンピックで代表に選出。
 長距離選手 竹澤 健介(たけざわ・けんすけ)
長距離選手 竹澤 健介(たけざわ・けんすけ)
長距離選手。2009年早稲田大学スポーツ科学部卒業。学生時代、早稲田大学競走部の主将を務める。大学卒業後、ヱスビー食品を経て住友電工に所属。08年に開催された北京オリンピックで代表に選出。
 やり投げ選手 ディーン 元気(でぃーん・げんき)
やり投げ選手 ディーン 元気(でぃーん・げんき)
やり投げ選手。2014年早稲田大学スポーツ科学部卒業後、ミズノに所属。12年に開催されたロンドンオリンピックで10位、14年に開催された日本選手権で3位となっている。
世界で勝ち抜くためのトレーニング法
岡田:まず、それぞれの競技特性を紹介してもらえますか?
ディーン:やり投げは、他の投てき種目と違い、助走をつけて行います。この助走速度は、やりの飛距離を左右する要素の一つ。そのためパワーだけではなく、総合的な身体能力が求められる競技です。
竹澤:長距離は、スタミナが求められる競技であるとともに、いかにスピードを殺さずに長い距離を走り切るかが重要になります。
菊池:スピードスケートのショートトラックは、500m、1000m、1500m、3000mの距離を滑り、各レースの着順によって総合点を競います。タイムトライアルではないため、レースの運び方が鍵になります。
岡田:競技によって求められる要素がまったく違うわけですね。トレーニング法で重視していることは?
ディーン:安定した成績を残すため、故障しない体を作ることを心掛けています。臀部の内側の筋肉、肩甲骨の下の筋肉といった小さな筋肉を重点的に鍛えたことで、故障を防ぐことにつながりました。
岡田:「スポーツ動作とは、多くの異なる筋群が関与して、多関節を協調させる運動様式である」という基本的な考え方があります。やり投げの場合、体幹の前屈、ひねりなどの一連の投げ動作を通して運動エネルギーを流動させ、そのエネルギーを最終的にやりに集中させる。けがが減ったということは、小さな筋肉がしっかり働き、複数の筋肉の連動性が高まった証拠です。
竹澤:私のトレーニング法にも、ディーン選手と通じる部分があります。小さな筋肉である内転筋を鍛えることで、スピードを保ちながら効率よく走るフォームを追求しています。
岡田:内転筋はどのように鍛えているのですか?
竹澤:上り坂を走るイメージで平地を走るようにしています。これにより、前方への推進力が高まっただけでなく、疲れてきたときに「足が流れる」ことがなくなりました。

上り坂を走るイメージで平地を走り、内転筋を鍛える
岡田:上り坂をイメージすることで、ブレのない脚の回転運動を生み出すこと、そのために内転筋群の動員を高めることが促されます。また、前傾姿勢による推進力で走ることを意識すると、自ずとつま先に近い部分で着地することになります。この走行は着地の衝撃が少ないだけでなく、次の蹴りだしに備える動作時に発生するブレーキ作用が起こりにくく、滑らかな走りとなり、エネルギーの消耗を抑えてくれることでしょう。これまで、長距離走ではかかとから接地し、爪先で蹴りだす動作が基本とされてきました。走り方は確実に進化していますね。氷上の競技ではどうでしょう?
菊池:スピードスケートのレースでは、滑り続ける持久力もさることながら、スタートダッシュと、100分の1秒を争う場面で相手を抜き去るスピードが大きくものをいいます。その際、血中乳酸濃度の上昇に伴う無酸素的持久力が求められるため、フォーム練習とインターバルトレーニングを組み合わせて練習しています。
岡田:500mから1500mあたりの距離は無酸素性代謝が優位に働いているということですね。したがって、乳酸耐性含めて、無酸素的エネルギー供給系の強化が重要なカギになってきます。
菊池:はい、試合では1日に8本ほど滑りますが、レースとレースの間に与えられる休憩時間は20分ほど。何本目のレースにも体がフレッシュな状態で臨めるよう、セルフケアによってできるだけ早く疲労回復し、次のレースに備えることを心がけています。
岡田:疲労回復には、ストレッチによる筋肉のケアが有効です。しかし、高い出力を得る、あるいは疲労を後まで残しにくくするという観点からいえば、ストレッチの取り入れ方に注意する必要があります。運動前には身体能力の発揮にもつながるとして、ダイナミック(動的)ストレッチが注目されています。同じ姿勢を保つ従来のスタティック(静的)ストレッチのような受動的なストレッチではなく、能動的に筋肉を伸張させることがパフォーマンスへの好影響を期待できるというわけです。さらに、練習中、例えばセット間にもストレッチをマメに行うことが、疲労の蓄積を軽減して運動レベルの維持につながるでしょう。
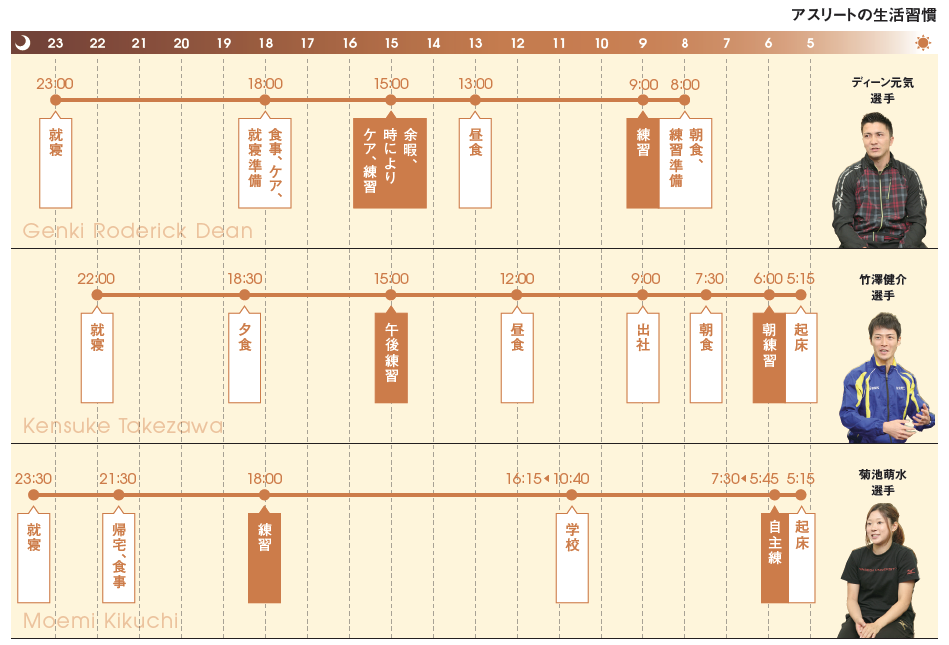
試合前の精神統一方法は?
岡田:試合前のルーティーンは?
ディーン:ウォーミングアップは音楽を聞きながら行います。曲は決まって、目標とする選手のベストプレー動画のBGMです。これを聞くと、理想のフォームをイメージしやすく、試合中の自分の動きも動画を見る感覚で俯瞰できるようになりました。

大きい筋肉だけでなく、小さな筋肉も鍛え全身を連動させる
竹澤:僕の場合、試合前はとにかく無の状態を心掛けています。考えたり話したりすると、エネルギーを使うので。
菊池:私もあまり気持ちを高めないようにしています。昔、レースとレースの間の休憩時間に次のレースのことを考えすぎて、体が動かなくなってしまったことがあったんです。
岡田:バイオメカニクス的視点から、理想的なフォームにはある程度基本形となるものがありますが、メンタルコントロールは選手によってそれぞれ異なるので、話を聞くことができて興味深かったです。また、共通項も見つかりました。状況や結果から自分なりに心身相関のメカニズムを追求し、自身にプラスに働くように努めているという点です。さすが、トップアスリートですね。
早大の後輩、また、仲間の早大生に向けて
ディーン:学生のときは、分野を問わず、いろいろなことに挑戦できます。まずそのことに気づくこと、そして何か目標を持って、その目標を叶える努力をする。そうすると、学生生活がもっと輝くと思います。
竹澤:たとえ気が進まない授業でも、自分の姿勢しだいで、新しい自分に出会えたり、新たな目標が見つかったりします。「やるからには、やってみよう!」という気持ちを大切に!
菊池:私は学生アスリートとして勉強と部活動を両立させながら、世界のトップレベルで戦える選手を目指して、より一層練習に励みたいと思います。また、社会科学部の授業を通じて、視野を広げてスポーツを捉えることで、いろいろな物の見方、考え方を知りたいと思っています。

インターバルトレーニングで、高い無酸素性持久力を身に付ける
(『新鐘』No.81掲載記事より)
※記事の内容、教員の職位および学生の所属・学年などは取材当時(2014年)のものです。