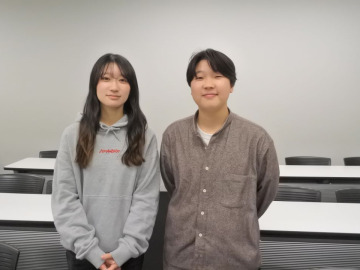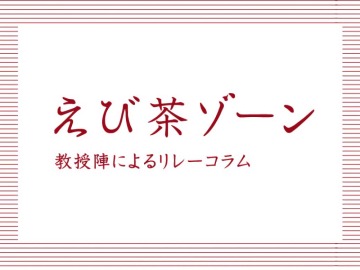
唐の杜甫が「飲中八仙歌」において「李白は酒を一斗(唐代の一斗は約6リットル)飲むと、100篇もの詩を作る」(「李白一斗詩百篇」)と歌うように、漢詩(中国古典詩)には酒杯を重ね、豪放に飲む描写が少なくない。一方、同じ唐の白居易は「一盃復た一盃、多くとも三四を過ぎず、便ち心中の適を得て、尽く身外の事を忘る」(『陶潜の体に効う詩』)といい、わずかな酒量でも飲酒の楽しみを得ている。また、酒がしばしば歌われる漢詩においても、詩人によって酒量は異なっていた。
時空を異にするわれわれも詩人の“表現”を通してその酒量や飲酒の様子を理解でき、また彼らの酒に対するさまざまな思いを共有できる。言うまでもなく、その理解や共有は読者の実体験に基づくとは限らない。
現在、わが国では20歳未満の飲酒は法律で禁じられており、大学もその順守を学生に求めている。社会でもアルハラという言葉が市民権を得るようになって久しい。しかし、酒そのものが悪なのではない。それを扱う人の問題である。
人は酒を歌う文学を享受できるように、そのような事件や事故への悲しみや憤りも十分想像できるはずである。法令やルール、社会の目が厳しくなっているにもかかわらず、本学も含めて酒を巡る事件や事故がなお続く今だからこそ、このことを強く思わずにはいられない。
(K)
第1176回