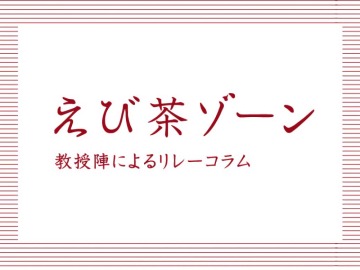
現在、日本に住む外国人は340万人を超え、過去最高となっている。皆さんも多くの外国人と共に学んだり働いたり、身近に接しているはずだ。在留外国人の出身地は195カ国・地域にも及び、その多くが英語を母語としていない。実は、日本に住む外国人の約8割が、日常的な会話は日本語で問題ないと答えている。日本では「日本語」が外国人とコミュニケーションする際の共通言語なのである。
しかし、日本で生まれて育ったわけではない方々にとって、やはり日本語は母語よりも難しい。そこで現在、多文化共生施策の一つとして、政府や自治体が積極的な利用を促しているのが「やさしい日本語」である。「やさしい日本語」とは、一般的に使われている日本語を外国人にも分かりやすいように簡単に話したり、書いたりする日本語のことである。2024年1月1日の能登半島地震の際、「津波(つなみ)! 避難(ひなん)!」「つなみ! にげて!」など漢字にフリガナを付けたり、平仮名の簡単な言葉で表記したりする画面がテレビで放送されたのを覚えている方もいるのではないだろうか。
現在、日本は外国人の受け入れを進める政策を取っている。背景には少子高齢化による労働力の不足もある。また、小・中・高校では日本語指導が必要な外国にルーツを持つ児童・生徒が増加している。私たちが社会生活を営む中で、コミュニケーションを欠かすことはできない。お互いを知り、共に生きるために、「ことば」をどのように使うかが、これからの私たちに問われている。
(N.Y.)
第1170回








