エントロピー概論 (社会科学部設置オープン科目)
教育学部3年 西村 和浩(にしむら かずひろ)
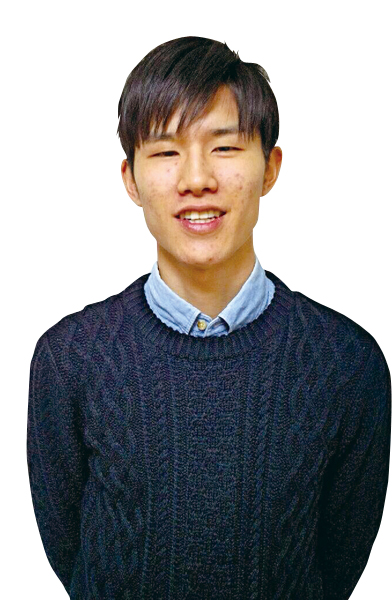 「エントロピー」は多くの理系学生が大学1、2年次に学ぶ熱力学や統計力学に出てくる言葉です。難しそうな言葉に聞こえるかもしれませんが、「世界は秩序ある状態から無秩序な状態へと進行していく」というエントロピーの概念は私たちの身の回りにたくさん隠れています。
「エントロピー」は多くの理系学生が大学1、2年次に学ぶ熱力学や統計力学に出てくる言葉です。難しそうな言葉に聞こえるかもしれませんが、「世界は秩序ある状態から無秩序な状態へと進行していく」というエントロピーの概念は私たちの身の回りにたくさん隠れています。
例えば生物の多様性が挙げられます。前述の概念を拡張すると、「世界は時間がたつにつれて確率的に起こりやすい現象が増えていく」と言い換えられます。生物たちが自分の遺伝子を子孫に残せるように振る舞うと仮定すると、さまざまな性質を持った子孫をたくさん残そうとするはずです。なぜならその方が天変地異の際、自分の遺伝子が途絶えず子孫に受け継がれていく確率が高くなるからです。長い年月このような生物たちの戦略が繰り返された結果、現在の多様性が生まれたと考えることができます。これは時間がたつにつれ無秩序(≒多様)な状態へと変化していったといえます。
他にも、周囲との温度差を利用して動き続ける「水飲み鳥」や生態系の物質循環、食物連鎖など、私たちの生活の至るところにエントロピーの概念は顔を出します。輪湖博(わこひろし)教授による「エントロピー概論」は、そのような身近な例を挙げながら、数式を使った厳密性にはこだわらず、エントロピーを感覚的に理解していく授業です。15週かけてじっくりと理解を深めていくカリキュラムになっているので、エネルギー保存則や気体運動論、カルノーサイクルなどといったエントロピーを理解する上で必須となる知識についても授業中にしっかりと扱います。理系の方はもちろん、数式は苦手だけれど理系の学問にも触れてみたいと考える文系の方でも、気軽にエントロピーの概念を学ぶことのできる講義です。










