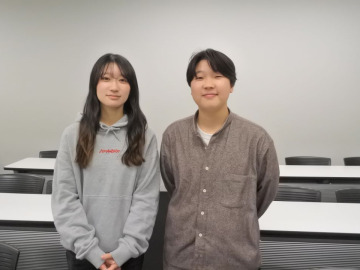「子どもの貧困のことを少しでも知ってみようと思うきっかけを作りたい」
社会科学部 4年 人見 玲奈(ひとみ・れいな)

絵本制作の転機があった「こはぜ珈琲」の店前にて
何らかの理由により家庭にいられなくなった15~20歳の子どもたちの、自立を促す暮らしの場である自立援助ホーム。社会科学部の人見玲奈さんはそんな自立援助ホームにてアルバイトで職員として働き、子どもたちの生活を支え、また、その認知を広めるための絵本制作に励んでいます。今回は、自立援助ホームで働くことになったきっかけや絵本制作に至った経緯、子どもの貧困問題に対する思いなどを聞きました。
――自立援助ホームで働くことになったきっかけを教えてください。
大学1年生のときの授業で児童福祉に興味を持ったことがきっかけでした。元々幼少期から母子家庭で育ったことや、ある時まで養父と暮らしていたこともあって、事あるごとに「他の家と何か違う」と漠然とした違和感を抱くことがありました。そんな私自身の原体験もあって、子どもの貧困や児童虐待の構造をもっと客観的に学びたいと思うようになったんです。授業では福祉について広く学ぶ中で、子どもの貧困についてディスカッションする機会があったのですが、ある学生が「貧困を抱える子どもも勉強を頑張っていい大学、いい会社に入れば、問題は解決するのではないか」という話をしていて、自己責任論のようなその発言にモヤモヤとした感情を抱いてしまって。そこで、貧困を抱える子どもたちの現状に興味を持ち調べていく中で、自立援助ホームという存在を知りました。
自立援助ホームは児童養護施設と異なり、義務教育を終えた子どもたちが暮らしています。そのため、生活のためのお金は自ら稼がなければならないのが前提で、金銭面でのサポートが少ないのですが、当時の自分と同じ19歳の人もいるという事実が衝撃的でした。そうして調べていくうちに出合ったのが、千葉県にある「みんなのいえ」です。この施設が他と違ったのは、さまざまな事情によりWebサイトを持たず連絡先すら公開しない施設が多い中、現場のリアルを積極的に発信している点でした。そして、その暮らしの様子や職員の考え方を知る中で、だんだんと私もこの施設に関わりたいと思うようになり、気付いたら「自分も働かせてほしい!」と直談判のメールを送っていたんです。当時は求人募集など行っていなかったので、今振り返るとその意志は我ながらかなり強いものだったのだと思います。
実際の業務内容は、家事業務から就労支援、支援金の手続きなど多岐に渡っていました。その中でも、施設の子どもたちの相談に乗る機会が多く、心を開いてくれたと実感できた瞬間は大きくやりがいに繋がりましたし、今でも強く印象に残っています。自立を目指す子どもたちの背中を押す「おとな」の立場として、彼らが社会や自分自身と向き合い前向きに成長していく姿には、大きく心を動かされてきましたし、多くのことを学ばされてきました。

自立援助ホーム「みんなのいえ」で、職員として自立支援に携わっていた頃。左から2人目のピンクのTシャツが人見さん
――現在はその「みんなのいえ」をテーマに絵本を制作していると聞きました。制作に至った経緯を教えてください。
自立援助ホームに対する認知度の低さや無意識な偏見を実感したことが、絵本制作を意識したきっかけです。私が自立援助ホームで働いていることを友達に話すと、あまり踏み込まないでおこうといった雰囲気になることが度々あるのですが、恐らく世間的には「施設出身の子どもたちはかわいそう」というネガティブなイメージを持たれているからだと思います。だからこそ、自立援助ホームは明るく前向きな場所だと知ってもらうきっかけとして、分かりやすく手に取りやすい絵本という形でその事実を伝えていきたいと考えるようになりました。
ただ私は絵心が無いので、その点をどうしようかなと日々考えていました。そこで出合ったのが、友人とたまたま足を運んだ大隈通り商店街にある「こはぜ珈琲」の店内に描かれたイラストでした。個性的なタッチに一目ぼれしてしまい、店長にこのイラストについて伺ったところ、なんとそこでアルバイトをされている方が描いているとのことでした。早速その方にコンタクトを取り、企画書を提案しイラストを依頼したところ、即参加OKのお返事を頂けて。こうして、2023年の1月から『スダチのナカミ』というタイトルの絵本作りを本格的にスタートさせました。

絵本作家のまるささん(左)と、人見さん(右)
――絵本制作でこだわったポイントなどはありますか。
絵本制作では、私が企画、構成、脚本などイラスト以外ほとんど全ての役割を担い、絵本作家のまるささんとも意見を出し合いながら制作を進めました。まず最初に取り掛かった『スダチのナカミ』という絵本は、自立援助ホームでの何気ない日常を職員視点で切り取った内容になっています。そこで意識したポイントは、施設での暮らしをできるだけリアルに伝えること。例えば、私が職員として実際に体験したエピソードを盛り込むことはもちろん、「みんなのいえ」以外の自立援助ホームにも取材し、さまざまな職員さんの体験エピソードや、働く中で大切にしていることなどをお聞きしました。
そして、もう一冊『くるまにのりたい』という絵本も制作しています。こちらは実際に施設で暮らし自立した方をモデルに、その成長を描いた物語です。『スダチのナカミ』とは対照的に、主人公の子ども視点で物語を描いているのがポイントです。

絵本製作に携わった方々。左から、写真・映像デザイン担当者、まるささん、人見さん、印刷会社の方
――絵本制作で大変だったことについて教えてください。
絵本制作にはイラスト依頼費や製本費などさまざまな費用が必要だったので、2023年12月にクラウドファンディングをすることにしたのですが、目標金額の設定やその使途、リターンの内容などこのプロジェクトを具現化し募集ページを制作するのが大変でした。クラファンの時期は期末試験やレポートの他、バイトや就活にも追われていたのでパンクしそうで…。目標額を達成できるかとても不安だったのですが、開始初日で目標額の40%もご支援いただき、ありがたいことに1週間足らずで目標額の100万円を達成することができました。最初は知り合いの方々からのご支援だったのですが、だんだんと知らない人からもご支援を頂けて。全国自立援助ホーム協議会の事務局長ともご縁があり、全国の関係機関に周知していただくなど、つながりがつながりを呼んで今回の目標が達成できたのだと実感しています。
また、絵本作家の方に私が絵本で表現したいイメージをうまく言語化して伝えることも非常に難しかったです。自立援助ホーム自体が世間的にあまり知られていないので、絵本作家の方に自立援助ホームの取材に立ち会っていただき、そのリアルに触れていただくことで、少しずつ方向性を定めることができました。今こうやって製本の実現に向けて着実に歩みを進められているのは、本当に多くの方の支えがあったからだと思います。

5月27日完成予定の『スダチのナカミ』(左)と『くるまにのりたい』(右)の見本
――児童福祉に興味を持った理由は大学の授業がきっかけとのことでしたが、早稲田大学に入学した理由を教えてください。
大学では留学をしたい思いが強かったので、海外の提携校が多く、留学の選択肢が多い早稲田大学を目指しました。結局、国内で児童福祉についての学びを深めることを選んだため留学はしていないのですが、周りの学生も国際色豊かで多様性に富んでいる大学なので入学して良かったなと感じています。また、奨学金が充実していたのも進学理由の1つです。

高校時代は英国での長期留学も経験した人見さん
――最後に、今後の展望や社会に対する思いを教えてください。
絵本制作の展望としては、絵本を届ける方法がクラファンのリターンと寄贈という2パターンしかないことが現状なので、出版社の方とコンタクトを取りながら、書店に並ぶような流通経路を開拓したいと考えています。私自身の将来の展望としては、就職先の企業で公共性の高い事業に携わり、児童福祉を含めさまざまな社会問題にアプローチしていきたいです。私自身の子ども時代には戻れないけれど、これからを生きる子どもたちのために、今後一人の大人としてできることを考え続けたいです。世の中には虐待や貧困と関わりのない人生を歩んでいる方はたくさんいます。だからこそ、そんな人たちに対しても子どもの貧困のことを少しでも知ってみようと思うきっかけをもっと作っていきたいです。まずは、この絵本がそのきっかけの一つになったらと願っています。
第869回
取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)
社会科学部 4年 堤 壮太郎
【プロフィール】

京都府出身。京都先端科学大学附属高等学校卒業。高校時代は10カ月間英国に留学。趣味は料理とうつわ収集。星野源さんとネコが好き。写真は絵本作家のまるささんと出会った「こはぜ珈琲」にて。
絵本の制作過程を更新している『スダチのナカミ』のInstagram:@sudachi_nakami