助けを求め、人との出会いを大切にすることが、充実した大学生活の鍵になる
社会科学部 3年 イマナリエバ アキライ
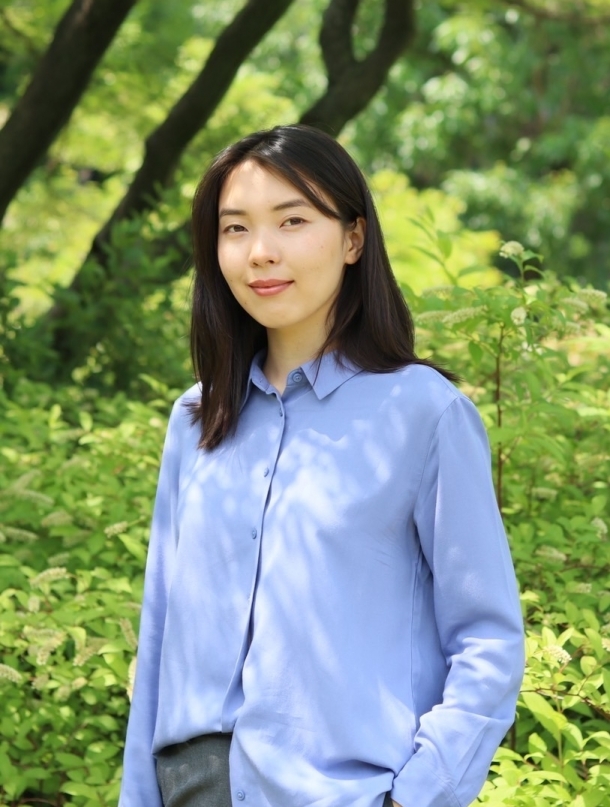
中央アジアに位置するキルギス共和国、ビシュケク出身の私は10代の頃、早稲田大学の留学生になることを夢見ていました。国際的な環境とTAISIプログラム(幅広い教養とコミュニケーション能力でグローバルに活躍できる学生を育成する、社会科学部の英語学位プログラム)に憧れていたんです。この留学を経験することで、人間的に成長できる機会に満ちあふれた大学生活になることを期待していました。
ところがパンデミックのため、1年生のときは故郷のキルギスにとどまり、オンラインで授業を受講せざるを得なくなり、国際的な交流はいつ再開されるのか、将来はどうなるのかと不安が募っていました。そんなとき、当時早稲田大学で教壇に立っていた相馬拓也先生と、人生を変えるような出会いがありました。
キルギス共和国日本人材開発センター(KRJC)の紹介で先生と出会った私は、フィールド・アシスタントとしてユキヒョウの調査に携わり、伝統的な生態学的知識や生物学的研究を中心としたプロジェクトに参加することができました。さらに研究チームの心強いサポートを受けて、安全な環境下でキルギスのイシク・クル地域の山間部での調査を成功させたのです。先生から受けた指導と得た知識は、その学期に他の授業で得た知識と合わさり、学業と自分自身に対する自信を深めることができました。

イシク・クル地域へのフィールドトリップ。標高約3,000メートルの山で、前回の遠征で設置したカメラなどの資料を回収するのが目的でした
また、来日して2年生を終え、さらに視野を広げ、ソーシャル・イノベーション(社会問題に対する革新的な解決法)をより深く掘り下げて学びたいと思ったとき、SPICE/Stanford-Waseda Intensive Course on Sustainable Business and Social Innovation(スタンフォード大学のSPICEと早稲田大学社会科学部で共同開催するプログラム)に出合いました。早稲田の教員とゲストスピーカーとのコラボレーションによるこの集中講義も、私の成長につながりました。
特に印象に残っているのは、グループでのブレーンストーミングで、日本社会にまん延する「孤独死」という切実な問題に取り組んだこと。この取り組みは、グループになって互いに協力し、批判的思考力を磨くための絶好の機会になりました。さらに発表後、私たちのアイデアは他のグループのメンバーだけでなく、来日した専門家たちからもフィードバックを受けることができたのです。自分の居心地のいい場所から抜け出し、創造する限界に挑戦したことで、私はグループでも大きな成長を遂げることができました。
写真左:2023年7月、ソーシャル・イノベーション・フォーラムにも参加し、シンガポール市民の異文化コミュニケーションに理解を深め、アジアの抱える問題について議論しました。筆者は後列右から2人目
写真右:早稲田キャンパスの大隈庭園で友人と。筆者は後列中央

シンガポールで開催されたソーシャル・イノベーション・フォーラム最終日、空港で撮影した一枚。10代の頃、この空港の複雑な構造とシンガポールのエコシステムに引かれていました。この写真は私の人生の節目となり、個人的な夢の達成を象徴しています
早稲田大学に来て、時には助けを求めながら人との出会いを大切にすることが、充実した大学生活の鍵であることを学びました。大学は成長を促し、自分の道を見つけることをサポートをしてくれる、育成的なコミュニティーです。私のこの旅(留学という名の旅)の経験は、皆さんの周りに多くのチャンスがあることの証しです。リスクを恐れず、自分が達成できると信じている以上の偉業を目指してください。
~日本に来て驚いたこと~
キルギスと日本は、一般的なライフスタイルや食の好み、文化的なアプローチ、そして地理的なことなど、いくつかの面で大きな違いがあります。中でも大きく異なることの一つは、来日した誰もがすぐに気付くことですが、人々の集団行動の様子です。この秩序と社会的規範の順守は、キルギスではあまり見たことがありません。キルギスの首都の人口密度が比較的低いことや、特定の行動規範が見えにくいなど、さまざまな要因が重なっているためではないかと思います。
例えば新宿駅はとても複雑な駅の一つです。混雑する空間の中で、多くの人はルールを守り、通路の特定の側(通常は左側)を歩く、エスカレーターのマナーを守る、出口で整然と並ぶなど、スムーズに進んでいるように見えます。私にとって、このような両国の顕著な違いは、母国を研究し続ける一方で、日本の社会的側面をより深く掘り下げたいという興味をさらにかき立てるものなのです。

TAISIプログラムの友人と。ストレス解消のため、東京で中央アジア料理と中東料理を食べ歩きするのが趣味です(筆者は左端)










