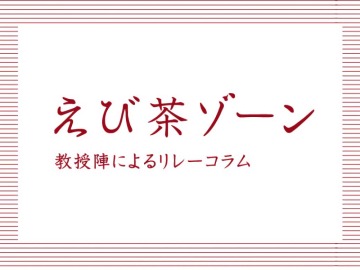
その昔、イギリス経済史の大家、故吉岡昭彦東北大学名誉教授は、著書『インドとイギリス』(岩波新書、1975年)の末尾で「インドを解くカギはロンドンにあり」と喝破された。独立以前のインドを考える上で、ロンドン郊外にあるイギリス国立公文書館に残された文書が重要な史料であることには誰も異論がない。
同じことが、中国にも当てはまることをご存じだろうか。在華イギリス政府外交官は、中国に関する大量の交渉記録を残している。社会経済史研究者にとって興味深いのは、最末端の領事が中国側地方官との間で行った交渉記録と、上海共同租界裁判所の裁判記録である。私は大学院生時代以来、この文書の虜(とりこ)となり、その中から見つけた新発見の英文、漢文文書を根拠に、従来の定説を塗り替えてきた。
私が現在、取り組んでいるのは、日本では絶対に見ることができない、早稲田大学創立期から日中戦争にかけての時期(1882~1937年頃)に作成された英文、漢文文書を、ロンドンに直接赴いて入手し、これを同じくメリーランド州にあるアメリカ国立公文書館や、六本木にある外務省外交史料館に出向いて手に入れた、アメリカ、日本政府の未公刊領事報告記録と突き合わせて、中国の対外経済関係史解釈を塗り替える作業である。恐ろしく手間がかかる作業であるが、これを行っていると、現在の多国籍企業が中国で直面する、さまざまな問題の由来が実によく分かるようになる。しかし、講義でその意義を説明し、これを読むゼミを開いても誰も振り向いてくれない。これが私の悩みの種である。
(M)
第1146回








