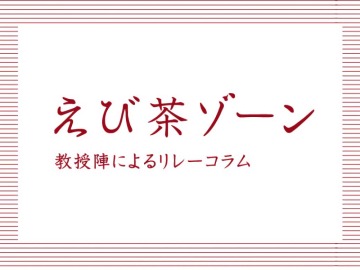
近年の大学生は、社会貢献意識が高まっていると感じる。大変喜ばしいことである。SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みが、中学・高校の教育で取り入れられている効果だろうか。あるいは、近年は企業も積極的にSDGsに取り組んでいるため、身近に感じているのかもしれない。
しかし同時に、大学生の姿勢として、「最短で正解にたどり着きたい」というマインドが強い点には問題を感じる。SDGsで取り組むべき課題には、正解はない。どの問題も長期間の積み重ねの上に発生しており、解決することに経済的メリットがないために放置され、現在に至ってしまっている。海洋プラスチックにしろ、教育格差にしろ、短期的に解決できる問題ではない。どんな行動を起こせばいいのか、正解は分からない。挑戦と失敗を繰り返しながら、小さな変化を起こし、自分なりの正解を創るしかない。そんな「コスパの悪い」長期的な取り組みに挑戦する学生は、実は少ないと感じている。一過性のファッション的な取り組みで終わっていないだろうか?
「コスパ」を社会貢献にまで求める姿勢は、なにも大学生に責任があるわけではない。おそらく大学入試のために、「正解のある問題に最短で正解を出す」トレーニングをしてきたことが原因ではないだろうか。大学人として責任を感じつつ、せめて大学生になったら「正解のない問題」に挑戦してほしい。そんな皆さんを応援するために、早稲田大学にはボランティアセンター(WAVOC)があるので、ぜひ活用してほしい。
(YI)
第1144回








