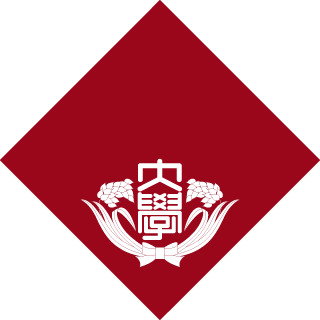日本財団パラリンピックサポートセンター常務理事 小澤直氏が語る、成功に近づくための考え方とは。
Jリーグを創設した川淵三郎キャプテン監修のもと、2017年から開催されてきた連続講義「早稲田2020講演会」。6月7日(月)にオンライン上で行われた第7回では、日本財団パラリンピックサポートセンター(以下、パラサポ)の常務理事を務めている小澤直氏が登壇されました。
講演のテーマは「スポーツの力をもっと自分や社会のために!~日本財団パラリンピックサポートセンターの挑戦~」。パラスポーツ推進のためにパラサポが行っている取り組みをはじめ、ご自身の学生時代や留学経験を通して学んだことについても語られました。
およそ1時間半にわたる講演会の中で、繰り返し訴えていらっしゃったのは「行動力」の大切さ。行動することで経験がどんどん増えていき、素晴らしい人と出会えたり、環境の変化を楽しむことができるようになるといいます。
小澤氏はご自身の人生の中で行動力を発揮したエピソードについて語られました。
高校1年生の夏。当時「甲子園に出て早稲田で野球をする」という夢を抱き、練習に励んでいましたが、通っていた高校の方針変更がきっかけで、所属していた野球部の部員の数が激減してしまいました。また、練習時間も放課後の2時間しか確保できないという窮地に立たされてしまいます。この時小学生のころからの夢は破れたかに見えました。ところが、小澤氏は考えることをやめず、できることを探し続けました。チームの司令塔となるべくキャッチャーへ転向し、対戦相手を徹底的に研究しました。そのような工夫を重ね、強豪校を相手に7試合連続逆転勝利というドラマチックな結果を手に、甲子園出場の悲願を達成したのです。
並外れた行動力は、留学経験にも表れています。留学する人がまだ少なかった時代に、海外でスポーツビジネスを学ぶ機会を探し続けていたという小澤氏。アメリカのマイナーリーグベースボールでのインターンを経験するなかで、アメリカの地域でスポーツが果たす役割や、人種差別の実態などを目の当たりにしたと語ります。さらに、オハイオ大学で学びたいという思いが高じ、教授に自分が載った新聞を送ったり、熱意を込めた手紙を書いたりすることもあったそうです。大学院入学を認められてからは、日本の書籍を読んで興味を持ったものがあると、一時帰国の際に出版社へ連絡を取り、著者に直接会いに行ったといいます。
小澤氏いわく、成功者から「運がよかった」という話をよく聞きますが、運は偶然によるものだけではなく、行動力を持って前に進むことで引き寄せられるものであると語ります。
27歳で日本財団に入会した小澤氏は、36歳のとき会長秘書の役職に就きます。ところが、実はこの「会長秘書」、もともとは存在しなかった役職でした。異動希望調査書の隅に小澤氏が書いた「会長の秘書をやりたい」という内容が会長の目に留まり、秘書を任されることになってできた役職なのです。小澤氏の強靭な行動力が、思わぬ巡り合わせを導いた瞬間です。

スポーツミュージアムを見学する小澤氏(奥)と説明する石井競技スポーツセンター長(手前)
このような経験を経て、小澤氏は日本財団パラリンピックサポートセンターの常務理事に就任することとなります。講演の後半では、多様な人々をつなぐ“接着剤”としてのパラスポーツを通じて、「ダイバーシティ&インクルージョン」社会を実現するパラサポの取り組みについて語られました。
まず日本を100人の村にたとえ、その中で7人は障がいを持つ人がいると説明されました。しかし現在、障がいを持つ人への理解や配慮はいまだ十分とは言えません。パラスポーツにおいてもパラサポを設立した2015年当初からは多少改善されたものの、まだ報道が少ないことや、パラスポーツをする環境が厳しいことなどに問題があると、小澤氏は指摘します。
また、障害者スポーツに対するイメージを変えるため、ポジティブな印象の薄い「障害者スポーツ」という呼称を使わずに「パラスポーツ」と呼ぶようにしたり、「i enjoy! 楽しむ人は強い」というキーメッセージを広めたりしました。その他、お洒落でユニバーサルデザインにも対応した共同オフィスを競技団体に提供したり、障がいを持つ人を講師に招いて講習会を開くなど、その取り組みは多岐にわたります。
小澤氏は、ロンドンで2012年に開催されたパラリンピックの大成功が共生社会の実現に寄与した前例を取り上げ、パラスポーツ推進の取り組みが成功することへの自信をのぞかせました。
最後に、「“何ができないか”ではなく“何ができるか”を考えてほしい」というメッセージで会は締めくくられました。それはパラスポーツに打ち込む人々の姿勢でもあり、成功に近づくための考え方でもあります。
日常生活の中で、日本財団やパラサポの活動を目にする機会は多いかと思います。しかし、
今回のように、運営に携わっている方から直接お話を聞くという機会はなかなかありません。この貴重な講演会は、パラスポーツが切り開く未来への期待を感じさせるとともに、私たちがこの時代を生きていく上でのヒントにも満ちた1時間半となりました。
文:VIVASEDA広報部門 スポーツ科学部1年 吉真 諒