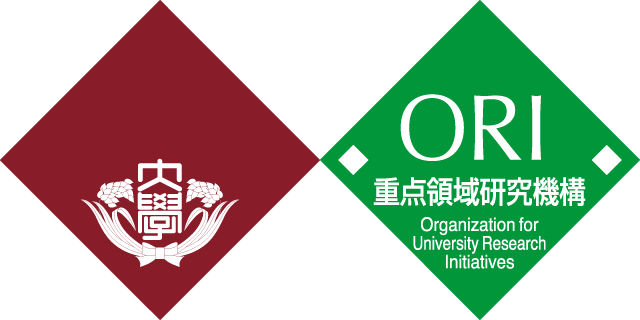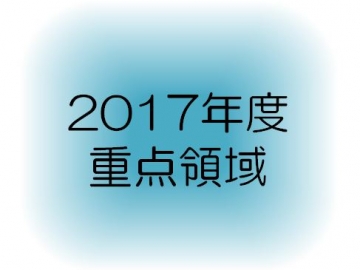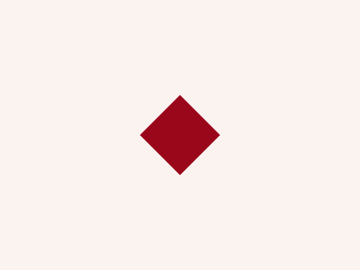所長:石渡 信一[いしわた しんいち]
理工学術院教授
研究テーマ
早稲田バイオサイエンス国際共同研究拠点の形成
研究概要
本学が保有するバイオサイエンスの最先端の研究テーマ(生命活動の原理、病態の解明、新しい医用マテリアルの研究開発など)を基に、シンガポールの研究機関[シンガポール科学技術研究庁(A*STAR)傘下の研究機関、シンガポール国立大学(NUS)、南洋工科大学(NTU)など]との国際共同研究体制を構築し、以下の課題に取組む。
- フィジカルバイオロジー:従来はマクロに捉えられていた「仕事(力)」と「熱(温度)」をミクロ・ナノレベルで扱う技術を開発し、生物学的に重要な事象を発見する。①生体に酷似した軟らかい場にある細胞を力学的に操作し応答を顕微解析して、筋細胞の分化メカニズムを理解し力による分化誘導を試みる。②水溶液中で高い時空間分解能を持ち温度だけを計測する手法を開発して、細胞内部のヘテロな熱的状態をイメージングする。がん細胞と心筋細胞が熱励起に応答する分子機構を解明し、それら組織の制御を目指す。NUS(特にメカノバイオロジー研究所)やNTU、A*STARとの共同研究を進める。
- ナノバイオテクノロジー:人工赤血球(ヘモグロビン小胞体)は、高純度高濃度ヒトヘモグロビン溶液をリン脂質小胞体に内包した微粒子(250nm)である。感染源を含まず、血液型が無く、常温で長期間保存ができ、輸血代替としての利用が期待されている。本研究では、酸素運搬機能を有する人工赤血球について、効率の高い製造法を構築するとともに、① 赤血球代替物としての自然災害や新興感染病に対する備えのほか、② 組織再生における酸素供給体、③細胞保護効果をもつ一酸化炭素の運搬体としての可能性も検討する。これらについて、NUS医学部、NUS生体工学部を含め国内外の研究機関との共同により、有効性と安全性を実証し、人工赤血球の新しい利用法を明らかにする。
- バイオイメージング: His-tagタンパク質(遺伝子組換え技術で調製)に対して高い親和性を有するアダプター分子を独自のスクリーニング法により開発してきた。これを発展させ、機能性ナノ粒子や機能性蛍光プローブの表面にHis-tagアダプター分子を結合させた新規プローブ群を構築する。また、新規プローブ群に消光剤や細胞導入部を持つHis オリゴマーと複合させることによるスイッチングや細胞内デリバリー可能なイメージングシステムの実現や、pH応答性リポソームによる機能性蛍光プローブの細胞内デリバリーの実現から、in vivo応用が可能なシステムを目指す。
- ケミカルバイオロジー:生体の情報伝達過程を可視化するために、蛍光タンパク質を基本としたバイオ機能性材料を新規に開発、改良、発展させる。そして、この機能性材料を生物個体内に導入することで、生きたまま生体内の機能動態を可視化しつつ、解析する。そして、この生物個体を用いて、細胞内情報伝達に影響を与える天然物質を検索し、単離する。また、化合物ライブラリーの検索も並行して試み、単離した化合物を様々な疾患モデル動物に投与し、疾患への有効性の検討も試みる。
これらのうち、新しい医療技術や研究手法に結びつく実学への応用については、早稲田大学バイオサイエンスシンガポール研究所(WABIOS)を足掛かりとしてシンガポールの強力な臨床研究インフラ、モニタリングネットワークを活用する。
研究所員
石渡 信一(理工学術院教授)
武岡 真司(理工学術院教授)
中尾 洋一(理工学術院教授)
鹿又 宣弘(理工学術院教授)
井上 貴文(理工学術院教授)
大島 登志男(理工学術院教授)
木下 一彦(理工学術院教授)
高野 光則(理工学術院教授)
常勤研究員
北口 哲也(主任研究員/研究院准教授)
鈴木 団(主任研究員/研究院准教授)
宗 慶太郎(主任研究員/研究院准教授)
招聘研究員
酒井 宏水(公立大学法人奈良県立医科大学医学部化学教室教授)
新井 敏
安田 賢二(東京医科歯科大学生体材料工学研究所教授)
連絡先
11 Biopolis Way #05-01/02 Helios, Singapore 138667
E-mail:[email protected]